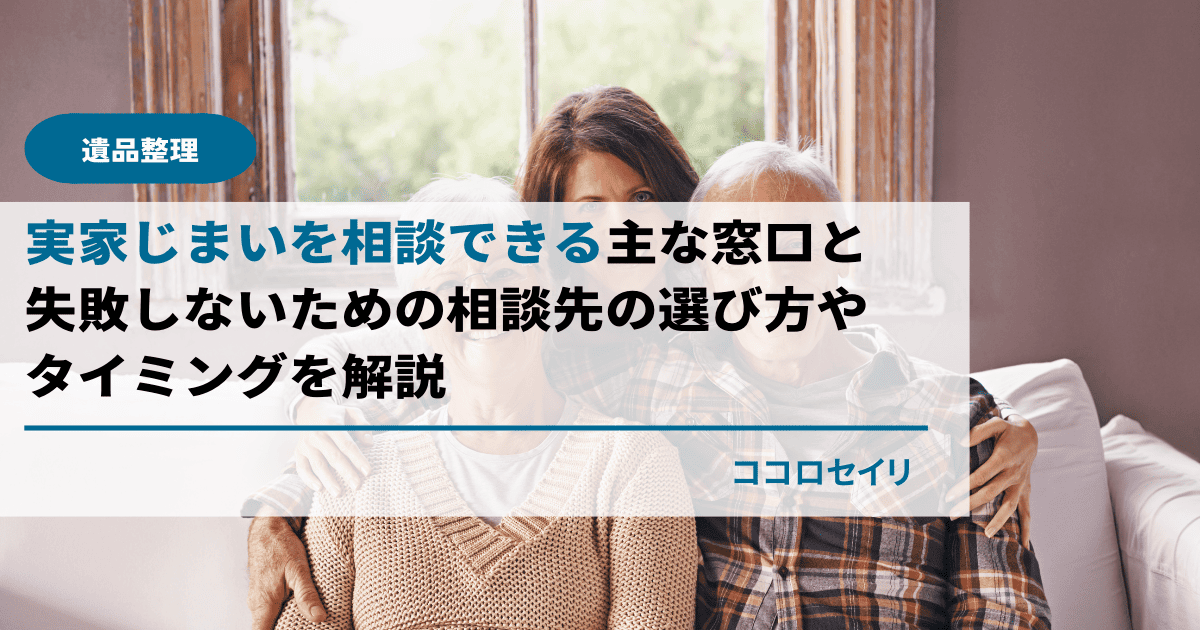「親が施設に入居したり、相続で実家を引き継いだものの誰も住まない」
そんな状況に直面したとき、「実家をどうするべきか…」「誰に相談したらいいのか分からない」と悩む方は少なくありません。
空き家のまま放置すれば、固定資産税や維持管理費がかかり続け、建物の老朽化や近隣トラブルの原因にもなります。さらに、相続登記や売却の期限が迫るケースもあり、早めの判断が必要になることもあります。
とはいえ、家財の整理や不動産手続き、税金の問題など、実家じまいは一人で解決するには大きな負担がかかるものです。
そんなときこそ、信頼できる相談先を見つけることが重要です。
この記事では、実家じまいを相談できる主な窓口と選び方、進め方や費用の目安、補助金制度までをわかりやすく解説します。
「後悔しない実家じまいを進めたい」「安心して専門家に相談したい」と考えている方は、ぜひ参考にしてください。
豊富な実績を持つ遺品整理の専門店「株式会社ココロセイリ」の代表取締役社長
目次
実家じまいを相談できる主な窓口
実家じまいは多岐にわたる専門知識が必要なため、一人で全てを抱え込むのは現実的ではありません。適切な専門家や業者に相談することで、スムーズかつ後悔なく進められます。ここでは、実家じまいに関して相談できる主な窓口とその役割を解説します。
不動産会社:売却・賃貸の専門家、査定、手続き代行。
実家を売却したい、あるいは賃貸に出したいと考えているなら、まず相談すべきは不動産会社です。不動産会社は物件の市場価値を査定し、売却活動や賃貸募集、契約手続きをサポートしてくれます。地域の市場動向に精通しているため、最適な売却価格や賃料設定のアドバイスも期待できます。相続した不動産の取り扱いに詳しい会社を選ぶのがポイントです。
遺品整理業者:片付け・不用品処分、供養。
長年住んでいた実家には、大量の家財や思い出の品が残されています。その片付けや処分に困った時に頼りになるのが遺品整理業者です。不用品の分別、搬出、処分はもちろん、故人の遺品を丁寧に扱ってくれるため、精神的な負担を大きく軽減できます。仏壇や位牌の供養(魂抜き)に対応してくれる業者もあります。
解体業者:建物解体、更地化。
実家が老朽化していて売却が難しい場合や、更地にして土地活用を考えている場合は、解体業者に相談します。建物の構造や規模によって解体費用は大きく異なるため、複数の業者から見積もりを取り、比較検討することが重要です体後の土地の整備についても相談できる場合があります。
司法書士:相続登記、不動産名義変更。
不動産を相続した場合、その名義を相続人に変更する「相続登記」は必須です。2024年4月からは相続登記が義務化され、期限内に手続きしないと過料が科される可能性があります。司法書士は、この複雑な相続登記や不動産の名義変更に関する手続きを専門に行うことができます。
税理士:相続税、譲渡所得税、各種控除。
実家じまいには、相続税や不動産を売却した際に発生する譲渡所得税など、税金の問題がつきものです。税理士はこれらの税金に関する相談に応じ、適切な節税対策や、活用できる控除制度(例:空き家譲渡所得の3,000万円特別控除)のアドバイス、確定申告のサポートをしてくれます。損をしないためにも、早めに相談することをおすすめします。
弁護士:親族間のトラブル、遺産分割協議。
実家じまいの過程で、親族間で意見の食い違いが生じたり、遺産分割で揉めたりするケースは少なくありません。このような家族間のトラブルが発生した場合や、法的な紛争に発展しそうな場合は、弁護士に相談しましょう。遺産分割協議の調整や、法的な視点からのアドバイス、代理交渉などを行ってくれます。
FP(ファイナンシャルプランナー):資金計画、ライフプラン。
実家じまいには、費用がかかるだけでなく、その後の生活設計にも影響を与えます。ファイナンシャルプランナー(FP)は、実家じまいの費用や売却益を含めた総合的な資金計画、そしてそれに応じたあなたの今後のライフプランについてアドバイスをしてくれます。経済的な不安を解消し、より良い将来設計を立てる手助けとなるでしょう。
空き家バンク・自治体の窓口:地域情報の提供、補助金情報。
お住まいの地域や実家のある自治体によっては、空き家バンクを運営していたり、空き家に関する相談窓口を設けていたりする場合があります。
このような窓口では、地域の空き家活用に関する情報提供や、解体費用・家財整理費用に関する独自の補助金制度について案内してくれることがあります。まずはお住まいの地域の自治体ホームページを確認してみるのも良いでしょう。
実家じまいを信頼できる相談先の選び方
実家じまいの相談先は多岐にわたりますが、どこに依頼するかで結果は大きく変わってきます。大切な実家を任せるわけですから、信頼できるパートナーを選ぶことが何よりも重要です。ここでは、失敗しないための相談先選びのポイントを解説します。
実家じまいの取り扱い実績。
まず確認したいのは、その会社や専門家が実家じまいや相続案件をどの程度扱ってきたかという実績です。単に不動産売買や遺品整理の経験があるだけでなく、実家じまい特有の複雑な感情面や、親族間の調整、多岐にわたる手続きへの理解があるかが重要です。ウェブサイトの事例紹介や、初回相談時に具体的な実績を尋ねてみましょう。
親身な対応とコミュニケーション
実家じまいは、物理的な作業だけでなく、精神的な側面も大きく影響します。担当者があなたの話に親身に耳を傾け、丁寧な説明をしてくれるか、質問に対して的確に、かつ分かりやすく回答してくれるかは非常に重要なポイントです。
一方的に話を進めたり、専門用語を多用して説明を怠ったりする業者には注意が必要です。安心して任せられるかどうかの判断基準として、担当者との相性も大切にしましょう。
見積もりの明瞭さ
費用に関する不安は、実家じまいを躊躇する大きな要因の一つです。相談先を選ぶ際は、見積もりの内訳が明確であるかを必ず確認してください。
何にいくら費用がかかるのか、追加費用が発生する可能性がある項目はどれかなど、詳細まで説明してくれる業者を選びましょう。曖昧な表現や「一式」といった大雑把な見積もりは避けるべきです。複数の業者から相見積もりを取り、比較検討することも重要です。
地域密着型であるか
実家のある地域に密着している不動産会社や業者は、その地域の特性や市場動向、法規制、さらには近隣の状況まで詳しく把握していることが多いです。これにより、より適切な売却戦略や、地域ならではの補助金情報などを得られる可能性があります。遠方からの実家じまいでは特に、現地に詳しいパートナーがいると心強いでしょう。
実家じまいを相談すべきタイミング
実家じまいは、始める時期を間違えると後悔につながったり、余計な手間や費用がかかったりすることがあります。適切なタイミングを見極めることが、スムーズな実家じまいへの第一歩です。ここでは、実家じまいを具体的に検討し、専門家へ相談すべき主なタイミングをご紹介します。
親が施設入居したとき(空き家化・管理負担増加)
親御さんが高齢者施設や老人ホームに入居し、実家が空き家になるタイミングは、実家じまいを検討する大きなきっかけの一つです。親が住まなくなった家は、管理が行き届かなくなり、急速に老朽化が進む可能性があります。
また、誰も住んでいなくても固定資産税などの維持費はかかり続けます。親御さんがまだお元気なうちに、今後の実家について意向を確認し、早めに相談を始めることで、後々のトラブルや負担を減らせます。
相続後、誰も住まない場合(税金・管理費が継続的に発生)
親御さんが亡くなり、実家を相続したものの、子ども世代がすでに持ち家を持っていたり、遠方に住んでいたりして、誰も住む予定がない場合も実家じまいを検討すべきタイミングです。
相続した実家をそのままにしておくと、固定資産税や維持管理費が継続的に発生し、経済的な負担となります。特に、2024年4月からは相続登記が義務化され、相続開始から3年以内に登記手続きをしないと過料が科せられる可能性もあります。早めに相談し、適切な対処法を見つけることが重要です。
老朽化や近隣への迷惑が心配なとき
実家が築年数を経て老朽化が進んでいる場合や、手入れが不き届きで近隣に迷惑をかけている可能性がある場合も、実家じまいを相談するタイミングです。例えば、庭の雑草が伸び放題になっている、建物の外壁が剥がれている、空き家特有の異臭がするといった状況は、近隣トラブルの原因となるだけでなく、行政から「特定空き家」に指定され、固定資産税の優遇措置が解除されてしまうリスクもあります。問題が大きくなる前に、専門家に相談して対策を講じましょう。
相続登記や売却の期限が迫っているとき
相続した実家について、相続登記の義務化により期限が迫っている場合や、売却を検討しているもののなかなか進まない、といった状況も相談のタイミングです。特に、特定の控除(例:空き家譲渡所得の3,000万円特別控除)を利用したい場合は、適用条件や期限があります。また、市場の動向や税金の変動によって売却に適したタイミングは異なります。期限に追われて焦って行動するよりも、早めに専門家と相談し、計画的に進めることが成功の鍵となります。
実家じまいの進め方|5つの基本ステップ
実家じまいは、いきなり家を売却したり解体したりするものではなく、段階を踏んで進めることでトラブルや後悔を防げます。ここでは、初めての方でも分かりやすいように、5つの基本ステップをご紹介します。
①親族間で方針を話し合う(トラブル回避のための合意形成)
実家じまいで最も重要なのは、親族全員が納得したうえで方針を決めることです。
誰が相続するのか、売却するのか、残す物や処分する物はどうするのか──こうした内容を曖昧にしたまま進めると、後になって「聞いていない」「そんなつもりじゃなかった」とトラブルが起こりがちです。
話し合いは早めに行い、できればメモや文書にまとめて共有しておくと安心です。
②家財・不用品を整理する(思い出品・価値ある物の仕分け)
実家には長年の生活で溜まった家具や家電、思い出の品が大量に残っていることが多く、これが大きな負担になります。
まずは必要な物・貴重品・残したい思い出品を仕分けし、それ以外は自治体の粗大ごみ回収や片付け業者を活用して処分していきます。
迷う品は写真に残したり、一部だけ記念に保管するなど、後悔しない整理方法を選びましょう。
③専門家に相談する(不動産・遺品整理・税務)
実家じまいは、不動産、税金、相続登記など複数の分野が絡みます。
すべてを自分で調べて進めるのは難しく、間違った判断で費用が増えたり、税金を余計に払うことになったりするリスクがあります。
不動産会社や司法書士、税理士、遺品整理業者などに相談し、手続きや費用の見通しを把握しましょう。複数の専門家に話を聞くことで、より良い選択肢を見つけやすくなります。
④売却・解体・賃貸など処分方法を決定
家の状態や立地、費用面を考慮し、実家をどうするのが最適かを決めます。
- 現状のまま売却するのか
- 解体して土地として売るのか
- リフォームして売却価格を上げるのか
- 賃貸として活用するのか
それぞれメリットとデメリットがあるため、専門家の意見を参考にしながら判断しましょう。将来的な管理の負担や税金も考慮して決めるのがポイントです。
⑤税金・補助金の手続きまで完了させる
実家じまいを終えるには、売却や解体だけでなく、税金の処理や補助金の申請などの手続きも必要です。
譲渡所得税の申告や相続税の支払い、場合によっては補助金を受け取るための申請書類の提出など、期限が決まっているものも多いため注意が必要です。
最後まできちんと対応することで、予期せぬ税負担や手続き漏れによるトラブルを防げます。
実家じまいの処分方法とメリット・デメリット
実家を手放す方法にはいくつかの選択肢があり、それぞれ費用や手間、売却までのスピードに違いがあります。
ここでは主な処分方法と、そのメリット・デメリットをわかりやすく解説します。
現状のまま売却
建物を解体せず、現在の状態のまま土地と建物を一緒に売却する方法です。
メリット
- 解体費用がかからず、初期コストを抑えられる
- 売却活動をすぐに開始でき、時間がかからない
- リフォームを行わないため、余計な投資を避けられる
デメリット
- 老朽化が激しい物件は買い手がつきにくい
- 建物の状態によっては想定より売却価格が下がることもある
- 買主が建物を解体する前提になるため、価格交渉で不利になりやすい
解体して更地で売却
建物を解体し、土地だけの状態にして売却する方法です。
メリット
- 更地は用途が自由で、買い手が見つかりやすい
- 古い建物の影響を受けず、土地本来の価値で売却できる
- 引き渡しまでのトラブルが少ない
デメリット
- 解体費用が必要(木造住宅で坪3万~5万円が目安)
- 解体後は固定資産税が上がる場合がある
- 売却がすぐに決まらないと負担が増えるリスクがある
リフォームして売却
ある程度の費用をかけて建物をリフォームし、価値を高めてから売却する方法です。
メリット
- 見た目や設備を改善でき、買い手がつきやすくなる
- 物件によってはリフォーム後に高値で売れる可能性がある
- すぐに住める状態で販売できるため需要が高まる
デメリット
- リフォーム費用がかかり、必ずしも投資回収できるとは限らない
- 工事期間が必要で売却開始が遅れる
- 老朽化が進んでいる家では大規模修繕が必要になることも
賃貸として活用
売却せずに賃貸物件として貸し出す方法です。
メリット
- 家賃収入が得られる
- 固定資産税や維持費を賃料でまかなえる
- 売却を迷っている場合でも、資産を活かしながら保有できる
デメリット
- 入居者募集や管理に手間がかかる
- リフォームや設備更新が必要になることが多い
- 空室リスクやトラブル対応が必要になる
実家じまいの費用相場と内訳
実家じまいを進める際には、想像以上にさまざまな費用が発生します。
不用品処分だけで済むケースもあれば、解体や売却手続きなどで数百万円単位の出費になることもあります。
ここでは一般的な費用の目安と内訳を紹介します。
遺品整理・不用品処分:15万~70万円以上
長年住んでいた家には、家具・家電・衣類・書類など大量の荷物が残っていることが多く、仕分けや処分に大きな手間と費用がかかります。
自分たちで処分できる量なら自治体の粗大ごみ回収を利用すれば安く済みますが、一軒家全体の片付けを専門業者に依頼すると15万円~70万円程度が目安です。
物量が多い、供養が必要な品がある、買取希望がある場合はさらに費用が変動します。
解体費用:坪3万~5万円(木造の場合)
古い建物を更地にして売却する場合、解体工事が必要です。
木造住宅の一般的な解体費用は坪単価3万~5万円が目安で、30坪の家なら90万~150万円ほどかかります。
コンクリート構造や狭小地での作業、アスベスト処理などが必要な場合は追加費用が発生します。
仲介手数料:売却価格の3%+6万円+消費税
不動産会社に売却を依頼した場合、契約成立後に仲介手数料を支払います。
3,000万円の物件を売却した場合、約96万円が手数料となります。
成功報酬制のため、売却が成立しなければ支払う必要はありませんが、相場を知っておくと安心です。
引っ越し・運搬費用:10~30万円
実家の中から必要な家財を運び出す場合、引っ越し業者や運搬サービスを利用する費用が発生します。
荷物の量や距離、作業員の人数によって変動し、繁忙期は高くなることもあります。
複数の業者から見積もりを取ると、費用を抑えやすくなります。
追加費用例(測量、境界確定、アスベスト処理など)
売却や解体をスムーズに進めるために、土地の境界確定や測量が必要になるケースがあります。
また、古い住宅ではアスベストが使用されている可能性があり、処理費用が追加されることもあります。
これらの費用は状況によって大きく差が出るため、事前に不動産会社や解体業者に確認しておきましょう。
実家じまいで活用できる補助金・税制優遇制度
実家じまいには多くの費用がかかりますが、条件を満たせば補助金や税制の優遇措置を受けられる場合があります。
制度を正しく理解し、事前に手続きを行うことで、負担を大幅に軽減できる可能性があります。
空き家譲渡所得3,000万円控除(申請条件)
相続した実家を売却した場合、一定の条件を満たすことで譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。
対象となる主な条件
- 被相続人(亡くなった親など)が一人暮らしで住んでいた家
- 相続後に誰も住まずに空き家になった家
- 耐震性がない場合は、解体または耐震改修後に売却すること
この控除を利用できると、課税対象額が大幅に減り、支払う税金を抑えることが可能です。
ただし、売却の翌年に確定申告が必要となり、必要書類も多いため、税理士に相談しながら進めると安心です。
自治体の解体費用補助(例:東京都)
各自治体では、老朽化した空き家を減らすために解体費用や家財処分費用を補助する制度を設けている場合があります。
例えば東京都の一部地域では、
- 家財整理費用の2分の1(上限5万円)
- 解体費用の2分の1(上限10万円)
といった補助金が交付されるケースがあります。
補助金制度は自治体によって内容や条件が大きく異なるため、実家がある地域の役所や空き家相談窓口に確認しておくことが大切です。
固定資産税の特例解除リスクと回避策
住宅が建っている土地は、固定資産税が軽減される「住宅用地特例」が適用されています。
しかし管理が行き届かず「特定空き家」「管理不全空き家」に指定されると、この特例が解除され、税額が最大6倍に増える可能性があります。
こうした税負担を避けるためにも、早めに売却や解体を進め、空き家状態を長引かせないことが重要です。
相続税・譲渡所得税の節税ポイント
相続税は相続開始から10カ月以内に申告・納付が必要です。売却のタイミングによっては税金が高くなる場合があり、相続前後の判断が重要です。
税理士に相談することで、相続財産の評価方法や控除の活用など、節税につながるアドバイスを受けられます。
実家じまいでよくある失敗と後悔しないための対策
実家じまいは、一生に何度も経験することではなく、多くの方が初めて取り組むものです。
そのため、後になって「こうしておけばよかった」と後悔するケースが少なくありません。
ここでは、よくある失敗例とその防止策を紹介します。
親と話し合わずに進めてトラブルに
実家じまいは、親が元気なうちに話し合いをしておくことが大切です。
親の意向を確認せずに処分を進めてしまうと、「本当は残してほしかった」「思い出の品を勝手に処分された」と後悔や親族間のトラブルにつながります。
対策
- できるだけ早い段階で親や家族と話し合い、記録に残しておく
- 感情的になりやすい話題なので、第三者や専門家を交えて冷静に決定する
思い出品を急いで処分して後悔
片付けを急ぐあまり、アルバムや記念品などをまとめて処分してしまい、後から「取っておけばよかった」と悔やむケースがあります。
対策
- 処分する前に写真を撮る、デジタル保存するなど記録を残す
- 残すか迷う品は一時保管スペースを活用し、時間をかけて判断する
売却価格や税金を確認せず損をする
不動産の売却価格を比較せず、1社の査定だけで決めてしまうと、相場より安く売ってしまうことがあります。
また、税金の控除や節税策を知らないまま進めると、余計な出費が増えることもあります。
対策
- 複数の不動産会社から査定を取り、条件を比較する
- 税理士に事前相談し、使える控除や申告方法を確認しておく
信頼できない業者に依頼して高額請求
遺品整理や解体工事を急いで決めた結果、見積もりが不透明な業者に依頼し、想定以上の高額請求を受けるトラブルもあります。
対策
- 作業内容や料金の内訳が明確かを必ず確認する
- 契約前に複数社から見積もりを取り、相場と比較する
- 口コミや実績をチェックし、信頼できる専門家を選ぶ
まとめ|実家じまいは早めの相談と専門家選びが成功のカギ
実家じまいは、親族間の調整、家財の片付け、不動産や税金の手続きなど、多くの工程が関わる大きな決断です。
「何から始めればいいかわからない」「誰に相談すればいいかわからない」と悩むのは当然のことですが、放置してしまうと費用も負担も増え、トラブルの原因になることがあります。
今回ご紹介したように、実家じまいは以下のステップで進めるのが安心です。
- 早めに親族間で方針を話し合う
- 家財や不用品を整理し、必要なものを残す
- 不動産会社や司法書士、税理士など専門家に相談する
- 売却・解体・賃貸など、最適な処分方法を決定する
- 税金や補助金制度を確認し、手続きを完了させる
特に重要なのは、信頼できる相談先を見つけることです。
複数の専門家から話を聞き、費用や対応内容を比較しながら、自分や家族の希望に合ったパートナーを選びましょう。
また、自治体の補助金制度や税制優遇を活用すれば、費用を大幅に抑えられる可能性もあります。
実家じまいは一人で抱え込まず、早めに相談を始めることで、後悔やトラブルを防ぎ、スムーズに次のステップへ進めます。
まずは信頼できる専門家や窓口に連絡し、現状の把握と今後の見通しを立てることから始めてみてください。
豊富な実績を持つ遺品整理の専門店「株式会社ココロセイリ」の代表取締役社長