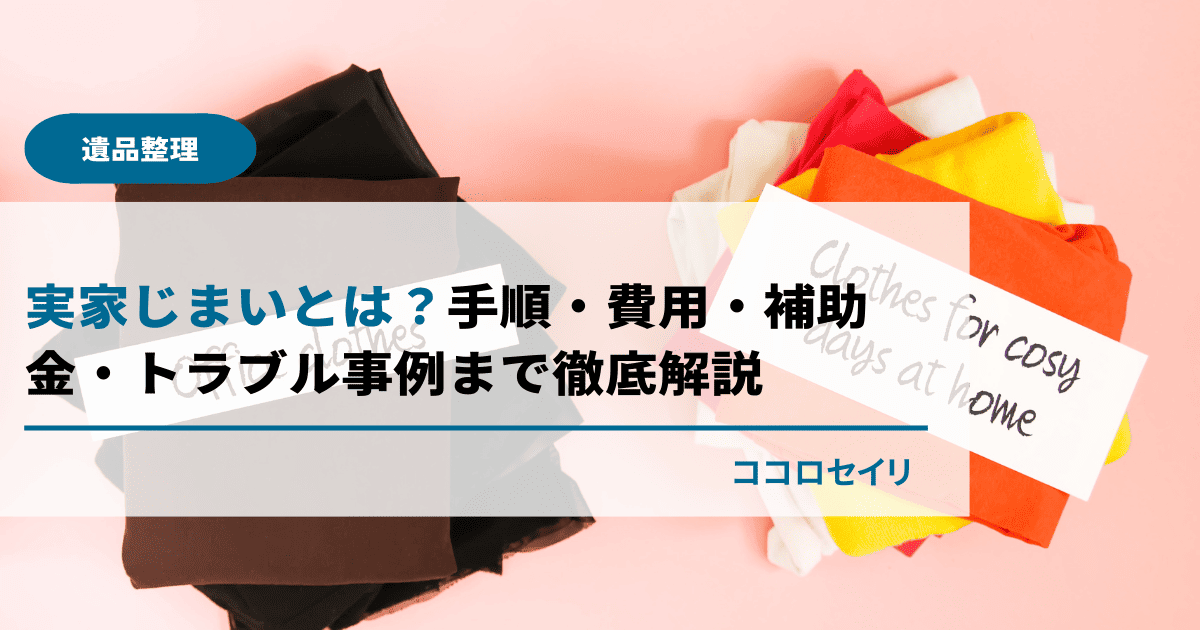「親が施設に入居した、相続が発生した、実家が空き家になって管理が難しくなった。」
こうしたタイミングで検討が必要になるのが「実家じまい」です。
しかし、いざ進めようと思っても、「実家じまいの手順が分からない」「費用がどれくらいかかるのか不安」「親族間トラブルや税金の問題が心配」という方は少なくありません。
実家じまいとは、家財整理や不用品処分、相続や登記などの手続きを経て、実家を売却・解体・賃貸などで手放す一連の流れを指します。
適切に進めないと、固定資産税や管理費の負担が増えたり、空き家対策の特定空き家に指定されて税金が上がるなど、思わぬトラブルが発生することもあります。
この記事では、「実家じまいの意味や家じまいとの違い」から「必要になるタイミング」「費用相場」「補助金や税制優遇」「よくあるトラブル事例と回避策」までを徹底解説します。
これから実家じまいを進めたい方が、費用を抑えつつスムーズに手続きを進められるよう、具体的な手順やプロが教えるポイントをわかりやすくまとめました。
豊富な実績を持つ遺品整理の専門店「株式会社ココロセイリ」の代表取締役社長
目次
実家じまいとは?意味と家じまいとの違い
「親が亡くなった後の実家をどうすればいいかわからない…」「相続した実家を手放すべきか悩んでいる…」
こうした悩みを持つ方が増える中で、近年よく耳にするようになったのが「実家じまい」という言葉です。
ここでは、実家じまいの意味や、「家じまい」との違いを分かりやすく解説します。
実家じまいの定義
実家じまいとは、親が住んでいた家を整理・処分する一連のプロセスのことです。
家財の片付け、不用品処分、相続登記などの法的手続きを経て、最終的に売却・解体・賃貸などで実家を手放すことを指します。
高齢化や核家族化が進む今、相続をきっかけに実家を持て余すケースが急増しています。
使わないまま放置すると、固定資産税や維持費がかかるだけでなく、「特定空き家」に指定され税金が増えるリスクもあります。
そのため、早めの実家じまいを検討することで、経済的負担や将来のトラブルを防ぐことができるのです。
「家じまい」との違い
似た言葉に「家じまい」がありますが、意味は少し異なります。
- 実家じまい:親が住んでいた実家を子どもや相続人が処分すること
- 家じまい:所有者本人が生前整理として家を片付け、最終的に住まいを手放すこと
つまり、誰が主体となって家を整理するかが大きな違いです。
実家じまいは親族の協力や相続の話し合いが必要なケースが多く、感情的な負担やトラブルに発展しやすいのが特徴です。
実家じまいが必要になる5つのタイミング
実家じまいは、多くの場合「避けて通れない問題」として突然訪れます。
しかし、実家をどうするかを後回しにすると、税金負担の増加や近隣トラブル、売却価格の低下などのリスクが大きくなることも少なくありません。
ここでは、実家じまいを考えるべき代表的な5つのタイミングをご紹介します。
親が施設に入所したとき
親が介護施設や高齢者向け住宅に入所すると、実家が空き家になるケースが多く見られます。
そのまま放置すると、固定資産税や管理費がかかるだけでなく、空き巣や老朽化のリスクも増加します。
親が元気なうちに、下記を一緒に話し合っておくと、後々のトラブル回避につながります。
- 今後の住まいの活用方法(売却・賃貸・維持管理)
- 家財道具の整理の進め方
親が亡くなり相続が発生したとき
相続が発生すると、実家の扱いについて兄弟姉妹や親族間での話し合いが必要です。
このときの判断が遅れると、相続税の申告期限(10か月以内)に間に合わない場合や、
遺産分割でもめて売却が進まないトラブルが起こりやすくなります。
専門家に早めに相談し、相続登記や不動産評価額の確認を行うことで、円滑に実家じまいを進められます。
相続した実家を手放すタイミング
相続後に実家を引き継いでも、別の場所で生活している場合や使う予定がない場合、維持管理が負担になることがあります。
空き家のまま放置すると、固定資産税や修繕費がかさみ、資産価値が下がることも。
相続から3年以内であれば、特例制度を活用して税金負担を減らせる可能性があるため、売却や解体のタイミングを早めに検討することが重要です。
維持管理が負担になったとき
「遠方に住んでいる、忙しくて実家の管理ができない」
こうした状況が続くと、草木の手入れや建物の劣化対策ができず、老朽化が進んでしまいます。
放置された家は「特定空き家」指定を受ける可能性があり、固定資産税が最大6倍に跳ね上がるリスクがあります。
負担が大きいと感じたら、早めに実家じまいを検討しましょう。
空き家による近隣トラブルが発生したとき
空き家を放置していると、次のような近隣トラブルにつながることがあります。
- 雑草やゴミの放置で景観を損ねる
- 老朽化で倒壊の危険がある
- 不法侵入や火災などの治安問題が起きる
行政から是正命令が出るケースもあり、最悪の場合、強制解体や費用負担を迫られることもあります。
こうした事態を避けるためには、早期の判断と対応が大切です。
実家じまいを先延ばしにするリスク
「まだ大丈夫」「もう少し様子を見よう」と実家じまいを後回しにしてしまう方は少なくありません。
しかし、空き家を放置すると 税金・維持費の負担増加、資産価値の低下、近隣トラブル など、思わぬリスクを抱えることになります。
ここでは、実家じまいを先延ばしにすることで起こりやすい4つのリスクをご紹介します。
税金や維持費の負担増
空き家でも、固定資産税や都市計画税、火災保険料、光熱費などの維持費は毎年発生します。
とくに誰も住んでいない家は劣化が早く、雨漏りやシロアリ被害などで修繕費が数十万~数百万円単位でかかることもあります。
結果として、「使わない家にお金だけが流れていく」という状況になりがちです。
早めに実家じまいを決断すれば、無駄な出費を抑えられる可能性があります。
「特定空き家」指定による固定資産税の増加
管理不足の空き家は行政から「特定空き家」に指定される場合があります。
特定空き家に認定されると、これまで適用されていた小規模住宅用地の特例が解除され、固定資産税が最大6倍に跳ね上がることも。
さらに、行政から改善命令や解体命令が出され、従わなければ強制撤去の上で費用請求されるリスクもあります。
「放置するだけ」でも予想以上の負担につながることを覚えておきましょう。
治安や景観の悪化、近隣トラブルの可能性
空き家は、防犯上のリスクが高く、不法侵入や不審火などのトラブルが起こりやすくなります。
また、雑草やゴミの放置、建物の外壁崩落などで近隣住民から苦情が寄せられるケースも少なくありません。
一度トラブルが発生すると、解決には時間とお金がかかることが多く、親族間の関係が悪化する原因にもなります。
売却価格が下がるリスク
実家を放置している間に老朽化が進むと、買い手がつきにくくなります。
建物の価値がゼロになり、最終的に更地にして売却せざるを得ないケースもあり、解体費用が数百万円単位でかかる可能性があります。
さらに、空き家が増える地域では地価が下がり、売却価格が想定より低くなることも珍しくありません。
早めの対応が資産価値を守るポイントです。
実家じまいにかかる費用の目安
実家じまいを進めるうえで、もっとも気になるのが「総額でどのくらいお金がかかるのか」という点です。
費用は家の広さや状態、処分方法によって変動しますが、一般的な目安を知っておくと、計画を立てやすくなります。
ここでは、主要な4つの費用項目と、費用を抑えるコツを解説します。
不用品処分・遺品整理の費用(1LDK~一軒家)
長年暮らした実家には家具や家電、衣類、思い出の品が大量に残っています。
これらを専門業者に依頼して片付ける場合、間取りごとの相場は以下のとおりです。
| 間取り | 費用相場(円) | 作業人数 | 作業時間 |
|---|---|---|---|
| 1K | 30,000~80,000円 | 2~3人 | 約1~3時間 |
| 1DK | 50,000~120,000円 | 2~4人 | 約2~5時間 |
| 1LDK | 70,000~150,000円 | 3~5人 | 約3~6時間 |
| 2DK | 90,000~200,000円 | 3~6人 | 約3~8時間 |
| 2LDK | 120,000~250,000円 | 4~7人 | 約4~10時間 |
| 3DK | 150,000~350,000円 | 5~8人 | 約5~12時間 |
| 3LDK | 180,000~400,000円 | 6~10人 | 約6~14時間 |
| 4LDK以上 | 250,000~600,000円 | 7~15人 | 約6~20時間 |
荷物の量や搬出条件(階段作業、駐車スペースの有無など)によっても変動します。
まだ使える家具や家電はリサイクル業者に買い取ってもらうことで、コストを抑えることが可能です。
不動産売却時の仲介手数料・税金
実家を売却する場合、不動産会社への仲介手数料が発生します。上限は「売却価格の3%+6万円+消費税」と法律で決められています。
例:3,000万円で売却した場合→ 仲介手数料:約96万円
加えて、売却益が出た場合は「譲渡所得税」が課税されますが、
相続した実家を売却する際には最大3,000万円の特別控除が使えるケースもあります。
事前に税理士や不動産会社に確認しておくと安心です。
解体費用の相場(構造別・坪数別)
築年数が古い実家や、買い手がつかない場合は解体して更地にすることもあります。
木造戸建て30坪の解体費用はおおよそ120万~150万円が相場です。
| 構造 | 30坪あたりの解体費用目安 |
|---|---|
| 木造 | 約120万~150万円 |
| 鉄骨造 | 約180万~210万円 |
| RC造(鉄筋コンクリート) | 約200万~250万円 |
アスベスト除去や地中埋設物の撤去が必要になると、さらに追加費用がかかることがあります。
引っ越し費用・その他諸経費
実家じまいと同時に親や家族が転居する場合は、引っ越し費用が発生します。
費用相場は10万~30万円程度で、荷物量や移動距離によって大きく変わります。
そのほかにも、相続登記の手数料(1万~10万円程度)、不用品処分での追加費用、遺品整理の特殊清掃などが必要になるケースもあります。
費用を抑えるコツ(買取サービス、リサイクル活用など)
実家じまいの費用をできるだけ抑えるには、以下の方法が効果的です。
- まだ使える家電・家具は買取サービスを利用する
- 自治体の粗大ゴミ回収を併用する
- 複数の業者から見積もりを取り、比較する
- 生前整理を早めに始めて、ゴミを減らしておく
こうした工夫をすることで、費用総額を10万~50万円以上削減できるケースもあります。
実家じまいの進め方・手順【6ステップ】
実家じまいは、思い出の整理や家族間の調整、法的な手続きなど、やるべきことが多く、どこから手をつけてよいかわからなくなる方も多いものです。
ここでは、初めての方でも迷わず進められるよう、6つのステップに分けて詳しく解説します。
STEP1|家族・親族で方向性を話し合う
まず最初に、家族や相続人全員で実家じまいの方向性を話し合います。
実家を「売却するのか」「賃貸に出すのか」「解体して土地を売るのか」を決めることが重要です。
- 実家に住む予定があるかどうか
- 費用は誰がどのように負担するか
- 遺品や思い出の品をどう分配するか
こうした点を事前に話し合い、トラブルを防ぐためにメモや議事録を残しておくと安心です。
STEP2|相続や登記など法的手続きを確認
実家じまいには、相続登記や名義変更などの手続きが必要です。
2024年4月から相続登記が義務化されており、相続発生から3年以内に登記をしないと、10万円以下の過料(罰金)が発生する可能性があります。
- 必要書類:戸籍謄本、遺産分割協議書、固定資産評価証明書など
- 専門家:司法書士に依頼するとスムーズに進められる
法的手続きが不十分だと、実家を売却・賃貸できなくなることもあるため、早めの対応が大切です。
STEP3|親の転居先や生活拠点を決める
親が健在で、施設入所や転居を伴う場合は、まず新しい住まいを決めましょう。
- 子どもや親族との同居
- サービス付き高齢者住宅や介護施設への入居
- 賃貸住宅への引っ越し
実家じまいの準備と並行して新生活の準備を進めることで、スムーズに移行できます。
STEP4|家の片付け・不用品処分を進める
次に、家の中の荷物を整理します。
思い出の品や貴重品を仕分けた上で、不要なものはリサイクルや不用品回収業者に依頼しましょう。
- 部屋ごとに「必要」「処分」「保留」で分類
- 写真や動画で思い出をデータ化
- 価値のある品は買取サービスを活用
荷物の量を減らすことで、処分費用や引っ越し費用を大きく節約できます。
STEP5|不動産を売却・解体・賃貸など選択肢を決める
片付けが終わったら、実家の活用方法を決めます。
- 売却:不動産会社を通じて土地や建物を売却
- 解体:老朽化が進んでいる場合は更地にして売却
- 賃貸:需要があれば賃貸に出して収入を得る
複数の不動産会社に査定を依頼し、相場を把握することで損を防げます。
STEP6|専門業者に依頼し、手続きを完了させる
最後に、必要に応じて専門業者に依頼して手続きを完了させます。
- 不動産会社:売却や賃貸契約の仲介
- 解体業者:建物の取り壊し
- 司法書士・税理士:登記や税金の手続き
複数の業者から見積もりを取り、内容を比較しながら進めることで、安心かつ費用を抑えた実家じまいが可能です。
実家じまいで活用できる補助金・税制優遇
実家じまいには、家財整理や解体、売却に伴う多くの費用が発生しますが、国や自治体が提供する補助金や税制優遇を上手に利用すれば、負担を大きく減らすことが可能です。
ここでは、代表的な3つの制度と、活用時の注意点を解説します。
空き家の譲渡所得3,000万円特別控除
相続した実家を売却する場合、一定の条件を満たすと「譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例」が利用できます。
この制度は、空き家を放置せず有効活用を促進するために設けられており、以下の条件を満たす必要があります。
- 被相続人(親など)が一人暮らしで住んでいた住宅
- 相続から3年以内に売却すること
- 1981年5月31日以前に建築された家屋であること
- 老人ホーム入所後に賃貸利用されていない住宅であること
この控除を使えば、譲渡所得税が大幅に減額されるため、実家じまいの費用負担を抑えられます。
自治体の補助金制度(解体費用・家財整理の補助など)
多くの自治体では、空き家の早期解消を目的とした補助金制度を設けています。
主な補助内容は以下の通りです。
- 解体費用の補助:解体費用の1/2を補助(上限50万円~100万円)
- 家財整理の補助:不用品処分や遺品整理費用の一部を補助(上限5万円~10万円)
- 空き家活用補助:リフォームや耐震改修などを行う際の補助
補助内容や上限金額は自治体によって異なるため、住まいがある市区町村の公式サイトや「空き家相談窓口」で最新情報を確認しましょう。
活用する際の注意点(期限・条件・必要書類)
補助金や税制優遇を活用するためには、いくつかの注意点があります。
- 期限がある:相続発生から3年以内、売却日や解体工事完了日が期限の対象となることが多い
- 事前申請が必要:補助金は事後申請が認められないケースがほとんど
- 必要書類の準備が必須:契約書、見積書、登記簿謄本、写真記録などを求められる
特に「知らなかった」ことで制度を利用できなかったケースが多いため、実家じまいを検討し始めた段階で専門家や自治体に相談するのがベストです。
実家じまいで起こりやすいトラブルと回避策
実家じまいは、多くの人にとって人生で一度きりの経験です。そのため段取りを誤ると、思わぬトラブルや余計な費用負担が発生するケースがあります。
ここでは、特に起こりやすいトラブル事例と、それを防ぐための具体的な回避策をご紹介します。
親族間のトラブル(遺品分配・費用負担)
築年数が古い、立地条件が悪いなどの理由で、なかなか実家が売れないことがあります。売却が長引くと、固定資産税や維持管理費がかさみ、負担が大きくなります。
回避策は次の通りです。
- 事前に複数の不動産会社へ査定を依頼し、相場を把握する
- 必要に応じて簡易リフォームや解体を検討し、売却しやすい状態にする
- 売却が難しい場合は、賃貸活用や不動産買取サービスを検討する
売却が進まない、買い手がつかない
実家の売却や相続手続きには、権利証や登記書類が必要です。しかし長年放置された実家では、これらの書類が紛失していることも少なくありません。
回避策は次の通りです。
- 早めに必要書類を探し、相続登記の確認をしておく
- 書類が見つからない場合は、司法書士に相談して再発行や代替書類の取得を依頼する
- デジタル化してクラウドなどに保管することで、紛失リスクを減らす
権利証・契約書が見つからない
遺産の多くを不動産が占める場合、売却代金が入る前に相続税の支払い期限(相続開始から10か月以内)が来てしまうことがあります。
回避策は次の通りです。
- 早めに実家の評価額を把握し、税金額を試算しておく
- 必要に応じて延納や物納制度を利用できるか税理士に相談する
- 売却や資産分割の計画を、相続が発生する前から家族で話し合っておく
相続税が払えないケース
遺産の多くを不動産が占める場合、売却代金が入る前に相続税の支払い期限(相続開始から10か月以内)が来てしまうことがあります。
回避策は次の通りです。
- 早めに実家の評価額を把握し、税金額を試算しておく
- 必要に応じて延納や物納制度を利用できるか税理士に相談する
- 売却や資産分割の計画を、相続が発生する前から家族で話し合っておく
トラブルを防ぐポイント(専門家・第三者機関の活用)
実家じまいは、感情面だけでなく法律や税金の知識も必要となります。素人だけで対応しようとすると、トラブルが発生しやすくなります。
回避策は次の通りです。
- 不動産会社、遺品整理業者、税理士、司法書士など、専門家のサポートを受ける
- 国や自治体が運営する「空き家相談窓口」を活用する
- 複数の専門家に相談し、最も安心できるプランを選ぶ
実家じまいをスムーズに進めるコツ
実家じまいは、片付けや手続きに時間も手間もかかる大仕事です。特に初めて経験する方にとっては、「何から手をつければいいかわからない」「家族と意見が合わない」といった悩みがつきものです。
ここでは、実家じまいを少しでも負担なく、スムーズに進めるためのコツをご紹介します。
生前整理の活用
親が元気なうちから少しずつ家の中を整理しておく「生前整理」は、実家じまいをスムーズにする最大のポイントです。
- 親の思い出の品や財産を一緒に確認できる
- 不要品を早めに処分し、作業量を減らせる
- 将来の相続トラブルを防ぎやすくなる
生前整理は「まだ早いのでは」と思われがちですが、親子で話し合いながら進めることで、後悔のない実家じまいにつながります。
写真やデータで思い出を残す方法
思い出の品を手放すのはつらいものです。無理に捨てる必要はありませんが、全てを残すのは現実的に難しい場合もあります。
- 形見やアルバムは写真に撮ってデジタル保存
- どうしても残したいものだけ厳選して保管
- クラウドサービスや外付けHDDで家族間共有も可能
データ化することで物理的な負担を減らしつつ、思い出をいつでも振り返れる環境をつくれます。
不用品買取サービスの利用
処分費用を少しでも抑えたい場合は、不用品買取サービスの活用がおすすめです。
- 家具や家電、ブランド品、骨董品などは買取対象になることがある
- 処分費用の負担が減り、場合によっては現金化できる
- 遺品整理業者が買取と処分をまとめて対応してくれるケースもある
複数の業者から見積もりを取り、買取価格や処分費用を比較するのがポイントです。
複数業者の見積りを取る重要性
実家じまいでは、遺品整理、不用品処分、不動産売却や解体など、さまざまな費用が発生します。同じ内容の作業でも業者によって金額が大きく異なることがあります。
- 最低でも2~3社以上に見積もりを依頼
- 作業内容と追加料金の有無を細かくチェック
- 口コミや実績も参考にして信頼できる業者を選ぶ
事前に比較・検討を行うことで、余計なトラブルやコストの増加を防げます。
まとめ|早めの実家じまいで負担を減らそう
実家じまいは、心身ともに負担が大きい作業です。親の思い出が詰まった家を整理することは、決して簡単ではありません。
しかし、放置してしまうと維持費や税金の負担が増えるだけでなく、売却価格の下落や近隣トラブルなど、将来的なリスクが大きくなります。
本記事で紹介したように、次のような準備を進めることで、実家じまいの負担を大きく減らすことができます。
- 家族や親族と早めに話し合う
- 生前整理を活用する
- 補助金や税制優遇を調べておく
- 専門業者に相談し、複数見積もりを取る
実家じまいは「今すぐやらなくてもいい」と思いがちですが、実際には早めの計画が成功のカギです。
親や家族と将来について話し合う機会を持ち、悔いのない選択をできるように準備を始めましょう。
豊富な実績を持つ遺品整理の専門店「株式会社ココロセイリ」の代表取締役社長