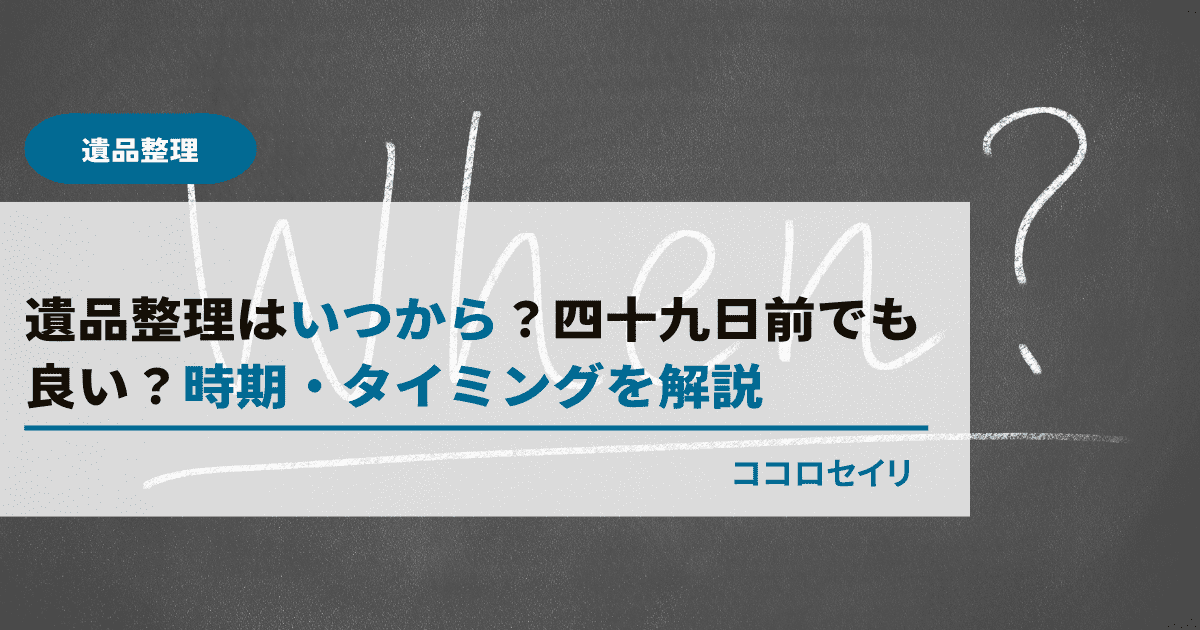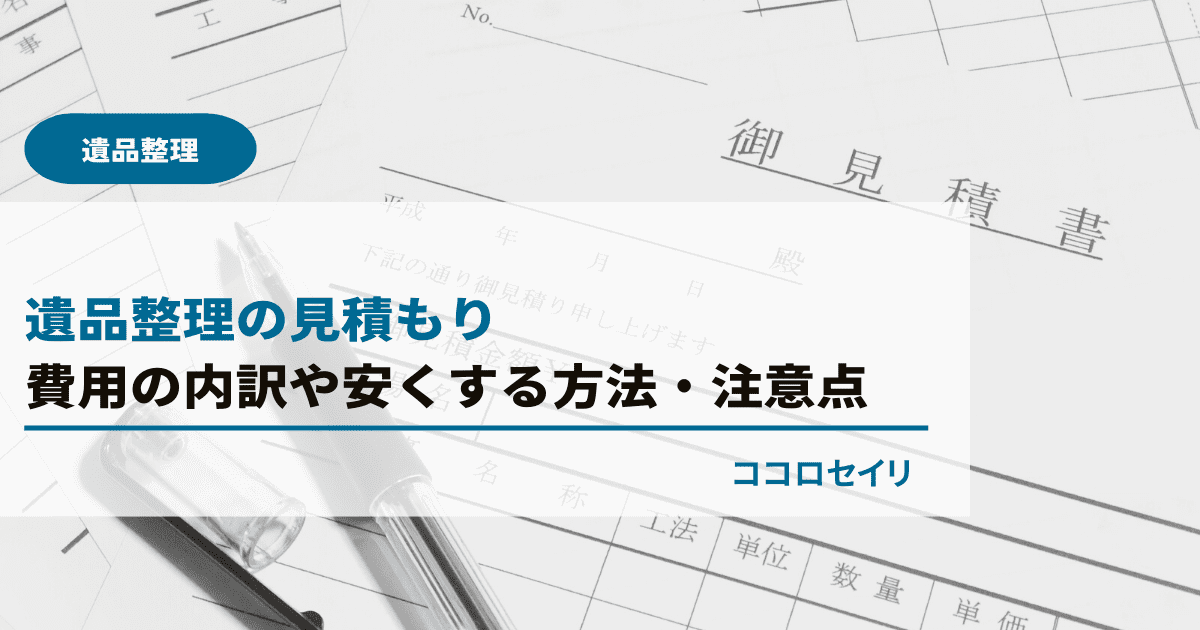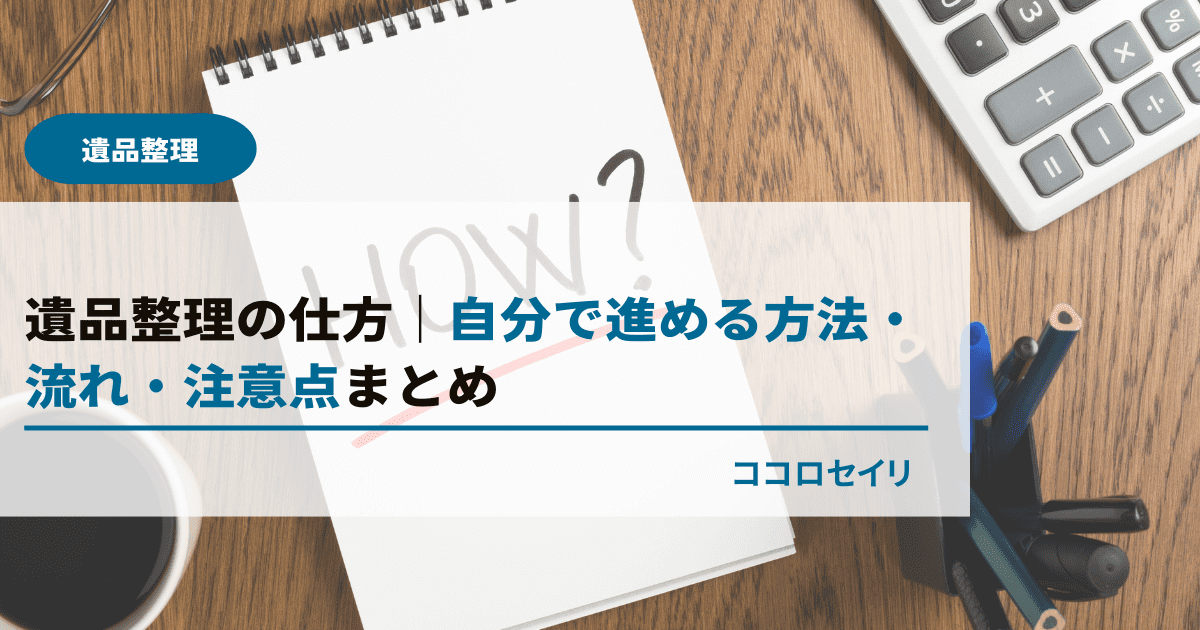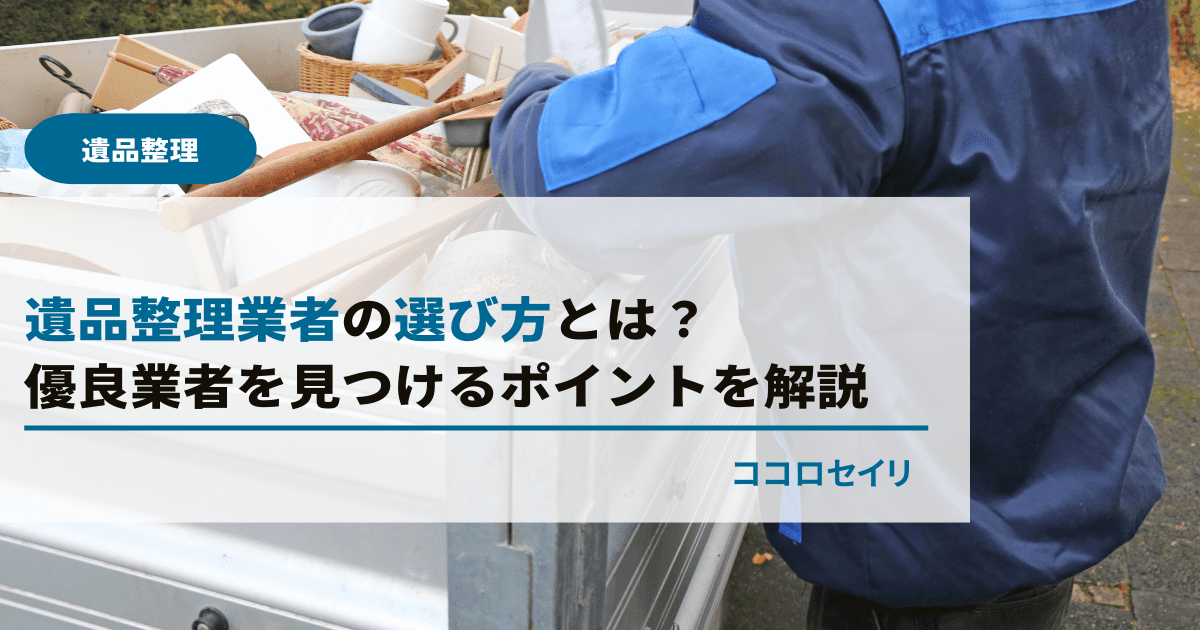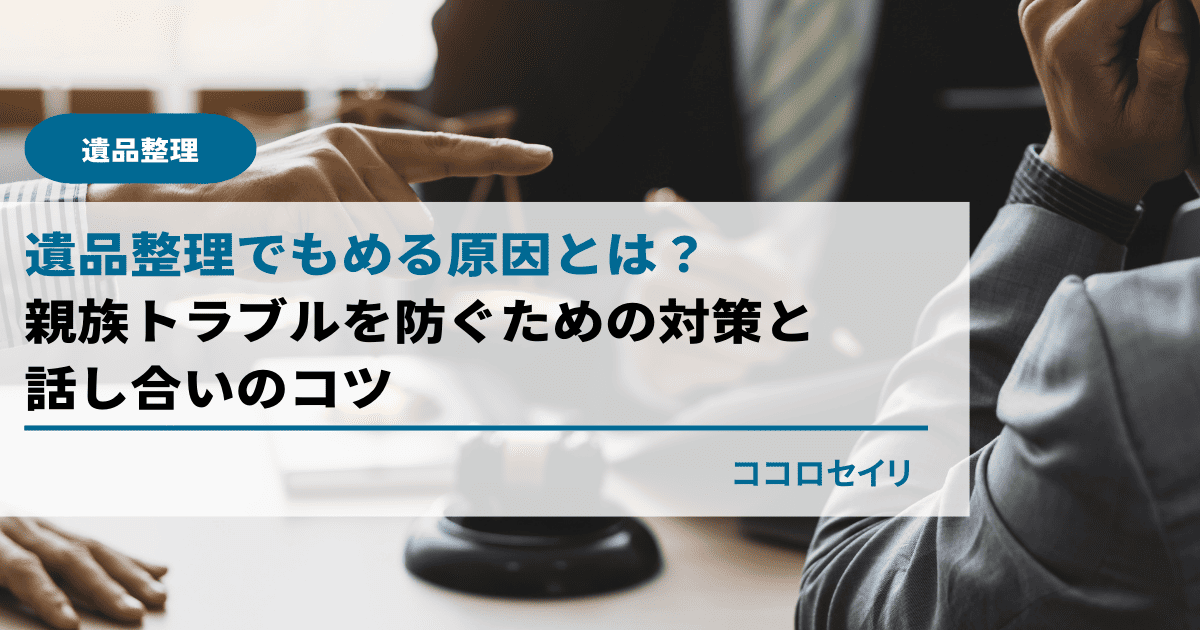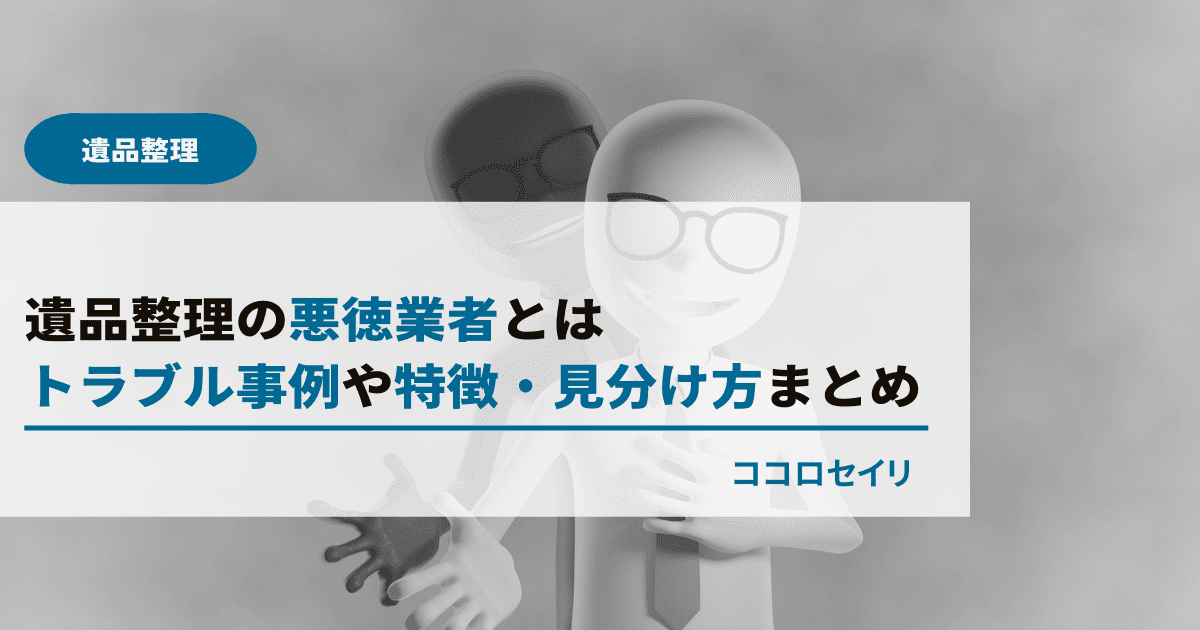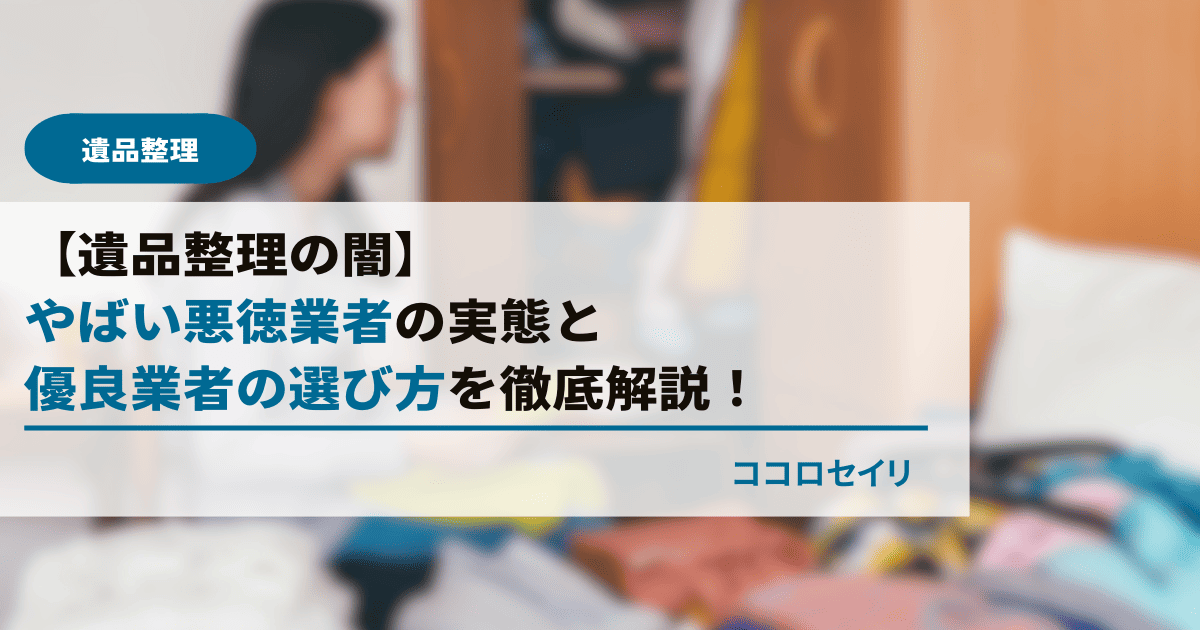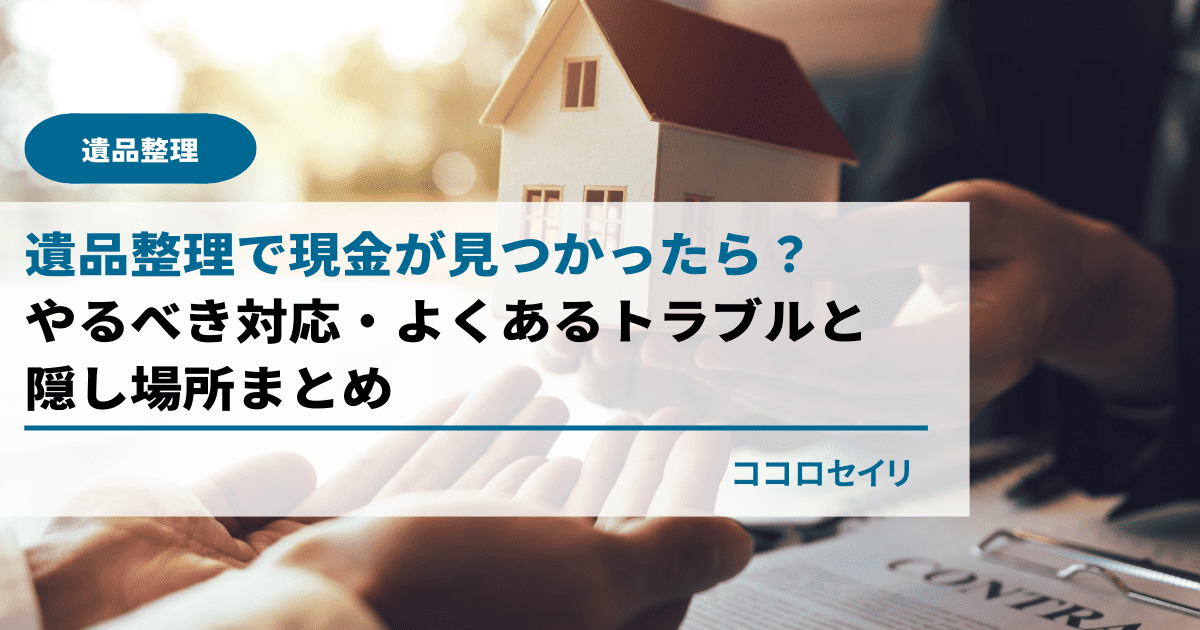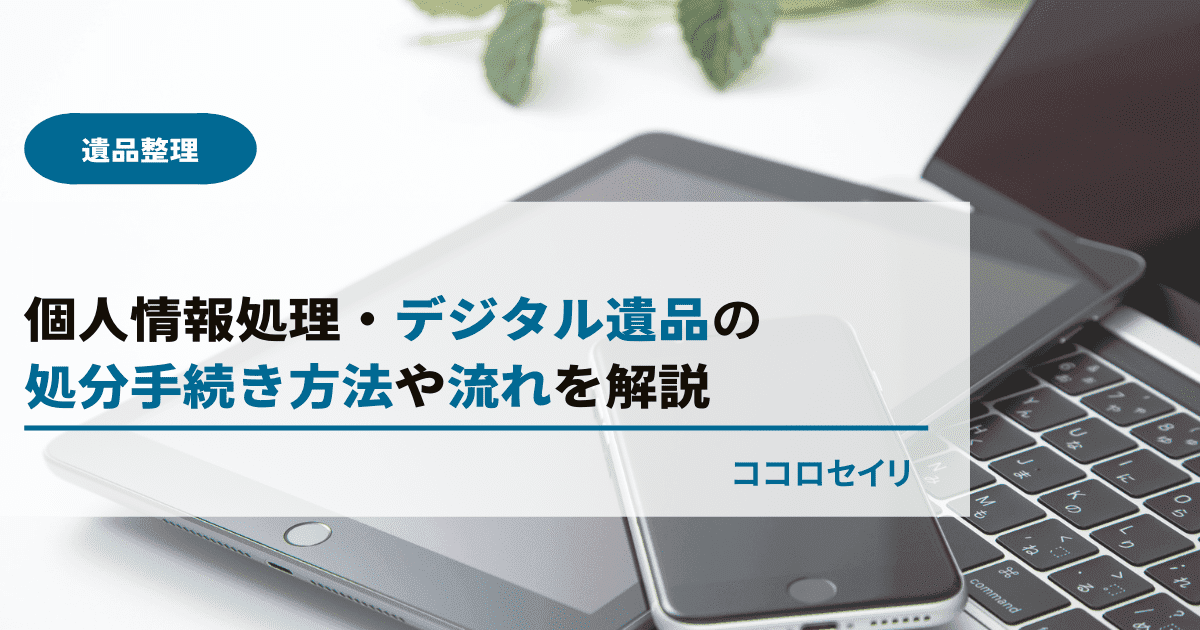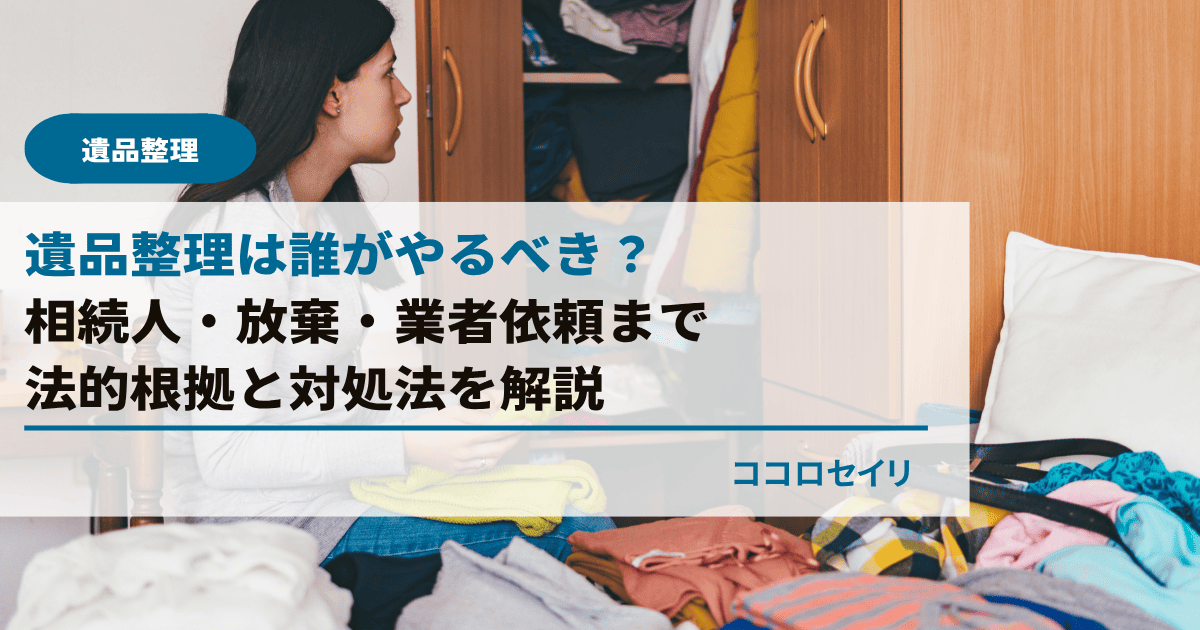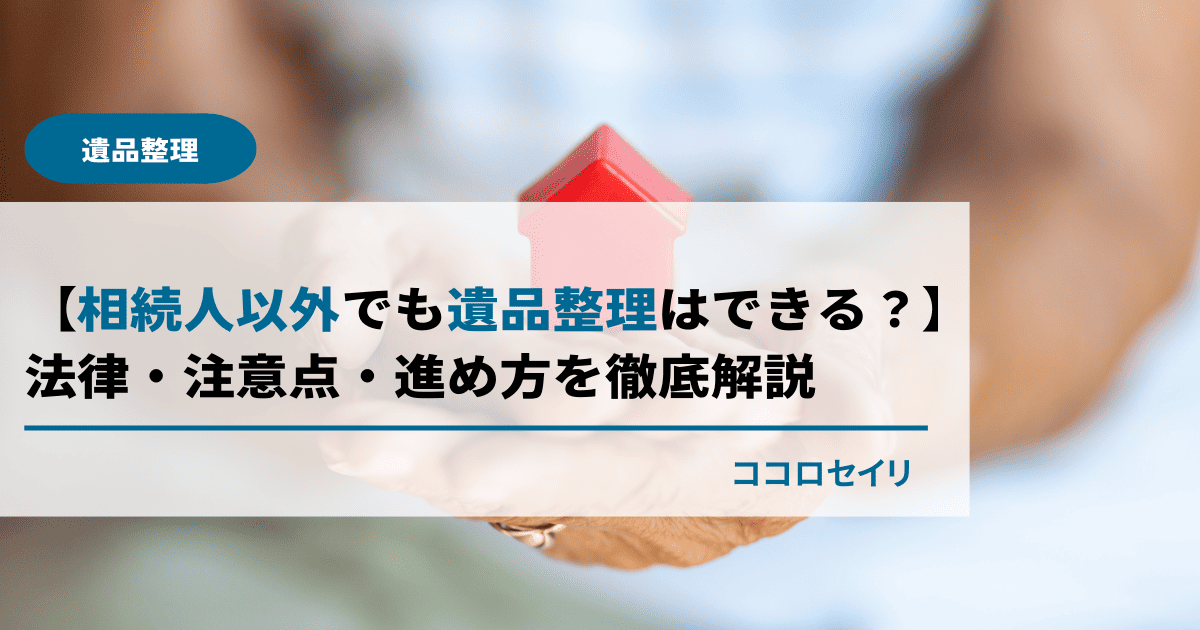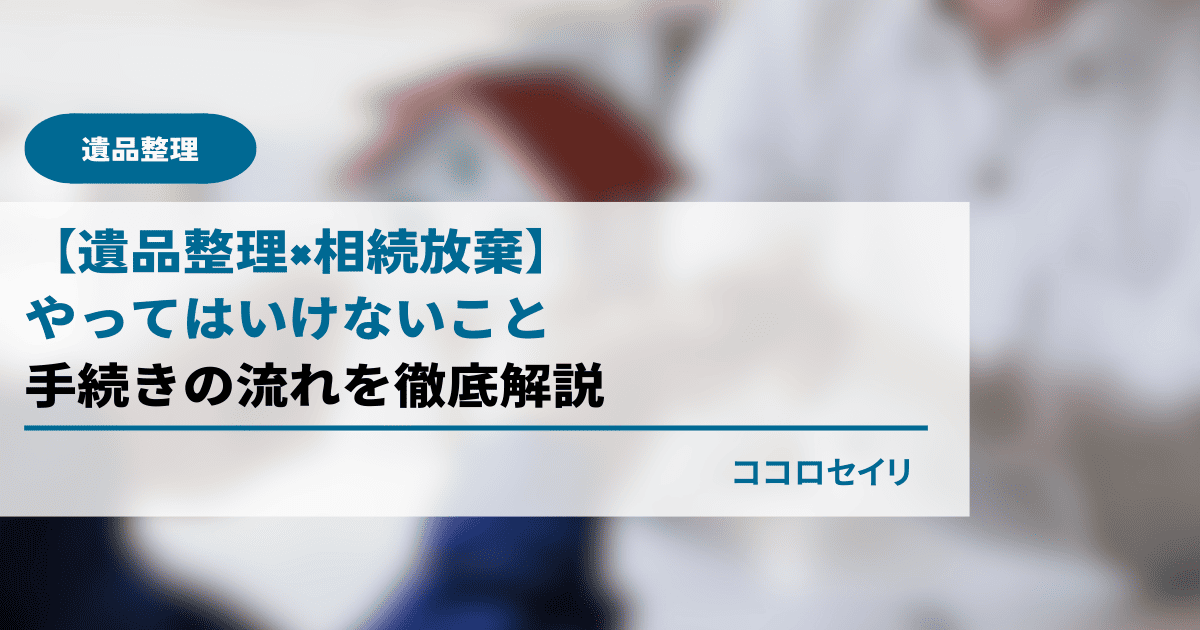大切な人を亡くした後、遺品整理にいつ手をつけるべきか悩んでいませんか?
「まだ気持ちの整理がつかない…」「何から始めればいいかわからない…」と、不安に思うのは当然のことです。
遺品整理には明確な期限がなく、進めるタイミングもご遺族の状況によってさまざまです。しかし、あまりに遅れてしまうと、賃貸の契約や相続手続きに影響が出たり、空き家の管理に負担がかかったりすることもあります。
そこで本記事では、遺品整理を始める適切なタイミングや、進め方、注意点を分かりやすく解説します。初めての方でもスムーズに進められるよう、遺品整理の流れやトラブルを防ぐポイントも具体的にご紹介しています。
「いつかやらなければ…」と思いながらも踏み出せずにいる方が、安心して遺品整理を始められるように。
あなたの気持ちに寄り添いながら、一歩ずつ進めるための手助けになれば幸いです。
豊富な実績を持つ遺品整理の専門店「株式会社ココロセイリ」の代表取締役社長
目次
遺品整理はいつから始めるべき?適切な時期
遺品整理をいつ始めるべきか悩む方は多いでしょう。
「すぐに片付けるべき?」「まだ気持ちの整理がつかない…」そんな思いの中で、なかなか手をつけられない方も少なくありません。
結論から言うと、遺品整理には明確な期限はなく、ご遺族の状況や気持ちに合わせて進めることが大切です。しかし、手続きを円滑に進めるため、また賃貸物件や税金の関係で一定のタイミングで進める必要があるケースもあります。
ここでは、遺品整理を始める一般的なタイミングを解説します。
それぞれの状況に合わせて、ご自身やご家族にとってベストな時期を見極めましょう。
葬儀後すぐ
最も早いタイミングで遺品整理を始めるのは、葬儀が終わった直後です。故人が亡くなった後、通夜や葬儀が行われ、参列者が帰ったあとに遺品整理に取り掛かるケースもあります。特に、故人が賃貸物件に住んでいた場合、退去に関する手続きが必要になるため、早めに動く方が多いようです。
このタイミングで遺品整理を進める最大のメリットは、親族が集まっていることです。形見分けを話し合ったり、貴重品を確認したりする作業がスムーズに進みます。また、賃貸物件の場合、契約が継続している間は家賃が発生するため、できるだけ早く整理を進めることで無駄な出費を抑えられます。
ただし、葬儀の直後は気持ちが落ち着かず、冷静な判断が難しい時期でもあります。大切な品を誤って処分してしまったり、親族間で意見が分かれたりすることも少なくありません。精神的な負担を考慮しながら、無理のない範囲で進めることが大切です。
諸手続きの完了後(亡くなってから1ヶ月~3ヶ月)
死亡届の提出や健康保険の手続き、銀行口座の凍結解除など、故人に関する手続きは多岐にわたります。これらの手続きが落ち着いた段階で、遺品整理を始める方も多いでしょう。
このタイミングでは、相続に関する重要な書類を整理しながら進めることができます。例えば、通帳や保険証券、不動産の権利証など、相続に関わる遺品を確認することで、財産の全体像を把握しやすくなります。また、役所や金融機関での手続きがひと段落しているため、気持ちにも余裕が生まれ、落ち着いて作業を進められるでしょう。
一方で、遺品整理を先延ばしにしすぎると、何をどのように分配するべきかの判断が難しくなることもあります。特に親族が遠方に住んでいる場合、再び集まる機会が限られるため、スケジュールを調整しながら進めることが重要です。
四十九日後
四十九日は、仏教の教えに基づく節目のひとつです。故人の魂が現世を離れ、成仏すると考えられており、四十九日法要を終えたあとに遺品整理を始める方も多く見られます。
このタイミングでは、親族が集まりやすいため、形見分けや遺品の処分について話し合うのに適しています。また、精神的な落ち着きを取り戻しやすい時期でもあり、冷静な判断のもとで作業を進めやすくなります。
一方で、四十九日までの間に故人の遺品をそのままにしておくことに抵抗を感じる方もいるかもしれません。特に、故人の住居が賃貸物件である場合や、早急に手続きを進める必要がある場合は、法要を待たずに整理を始めることも考慮する必要があります。
相続税の申告前(亡くなってから7~8ヶ月)
相続税の申告期限は、故人が亡くなった翌日から10ヶ月以内と定められています。相続財産の総額を確定させるためには、遺品整理を進めながら財産の詳細を確認することが不可欠です。
特に、通帳や有価証券、不動産に関する書類などは、相続手続きに直結するため、早めに整理することが求められます。財産の評価額を把握することで、税理士への相談もスムーズに進められるでしょう。
ただし、相続税の申告は専門的な知識が必要な場合が多いため、不明点があれば税理士や司法書士に相談しながら進めることが大切です。
賃貸物件の退去時期に合わせる
故人が賃貸物件に住んでいた場合、賃貸契約は相続人に引き継がれます。そのため、退去時期を考慮しながら遺品整理を進める必要があります。
契約内容によっては、月末までに退去しなければ翌月分の家賃が発生するケースもあるため、管理会社や大家に確認しながら進めるのがよいでしょう。また、賃貸物件の退去には、原状回復が求められることが多いため、片付けと同時に清掃のスケジュールも考慮する必要があります。
急いで整理を進める場合、業者に依頼することでスムーズに作業を終えられることもあります。費用面とのバランスを考えながら、最適な方法を選びましょう。
気持ちの整理が着いてから
故人の思い出が詰まった品を目の前にすると、なかなか処分の決断ができないこともあります。特に、親や配偶者を亡くした場合、遺品を見るたびに悲しみがこみ上げ、手をつける気になれないこともあるでしょう。
無理に急ぐ必要はありませんが、長期間放置すると、整理するのがより困難になることもあります。気持ちが落ち着くまで時間をかけても構いませんが、ある程度の期限を決めておくと、後悔のない形で進められます。
また、故人の部屋をそのままにしておくことで、気持ちが落ち着く方もいれば、逆に辛さを引きずってしまう方もいます。自分にとって最も納得できる形で進めることが大切です。
遺品整理の前にやるべき準備
大切な人を亡くした直後は、気持ちが落ち着かず、遺品整理にすぐに取りかかるのが難しいこともあるでしょう。しかし、いざ始めようとしたときに、「何から手をつければいいのかわからない」「あとから親族とトラブルにならないか心配」と感じることも少なくありません。
遺品整理はただ片付けをするだけではなく、故人の大切な思い出や財産を整理する作業でもあります。焦らず、落ち着いて進められるように、まずは準備を整えることが大切です。ここでは、遺品整理を始める前に確認しておきたいポイントについて解説します。
遺言書の確認(遺品の分配ルールを決めるため最優先)
遺品整理を始める前に、まず確認したいのが「遺言書の有無」です。遺言書には、遺産の分配方法や特定の品を誰に譲るのかなど、故人の意思が記されていることがあります。万が一、遺言書の内容に反して遺品を整理してしまうと、相続人同士でトラブルになることもあるため、慎重に確認することが大切です。
遺言書がありそうな場合は、自宅の金庫や引き出し、銀行の貸金庫などを探してみるとよいでしょう。また、公証役場で「公正証書遺言」として保管されているケースもあります。遺言書を見つけたときは、すぐに開封せず、家庭裁判所の検認手続きを行う必要があります。
もし遺言書が見つからなかった場合は、相続人同士で話し合いながら整理を進めることになります。その際も、お互いの気持ちを尊重しながら、納得のいく形で進めていくことが大切です。
相続人の特定(遺品の扱いについて親族間の認識を統一)
遺品整理を進める前に、「誰が相続人なのか」を明確にしておくことも重要です。故人の財産は相続人に権利があるため、遺品の中に価値のあるものが含まれている場合、誰がどのように扱うのかを事前に決めておく必要があります。
例えば、「大切な形見の品を勝手に処分されてしまった」「後から別の相続人が現れて揉めてしまった」といったトラブルが起こることもあります。こうした問題を防ぐためにも、親族間でしっかり話し合いをし、できるだけ全員が納得できる形で整理を進めることが大切です。
親族が遠方に住んでいる場合や、なかなか話し合いができない場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談するのも一つの方法です。焦らず、慎重に進めていきましょう。
財産や負債の確認(相続放棄を検討する必要があるか確認)
遺品の中には、現金や貴金属、不動産の権利書などの価値のあるものが含まれていることがあります。しかし、故人が残したのは「財産」だけとは限りません。借金や未払いの税金、ローンなど、負債が残っている可能性もあるため、しっかり確認することが大切です。
もし、故人が大きな借金を抱えていた場合、そのまま相続してしまうと、相続人がその負債を引き継ぐことになってしまいます。こうした事態を避けるためには、相続放棄の手続きを検討することも必要です。
相続放棄をする場合、故人が亡くなってから「3か月以内」に家庭裁判所に申請しなければなりません。遺品整理を始める前に、まずは財産の状況を把握し、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。
形見分けのルール決め(親族間のトラブルを防ぐ)
遺品整理の中でも、特に気をつけたいのが「形見分け」です。故人が愛用していた品を親族で分けることで、思い出を大切に残すことができますが、「誰がどの品を受け取るのか」で意見が分かれることも少なくありません。
たとえば、「母が大切にしていたアクセサリーが欲しい」「父の腕時計は長男が引き継ぐべき」など、それぞれに想いがあるため、話し合いなしに決めてしまうと、後々しこりが残ってしまうこともあります。
形見分けをスムーズに進めるためには、まずは親族全員で話し合いを行い、ルールを決めることが大切です。特に価値のあるものについては、公平に分配できるよう慎重に進めましょう。もし話し合いが難しい場合は、第三者を交えて調整するのも一つの方法です。
必要な道具の準備(作業をスムーズに進めるための準備)
遺品整理は、思っている以上に時間と手間がかかる作業です。いざ始めてみると、「捨てるものと残すものを分けるだけでも大変」「整理しながら写真を撮っておけばよかった」など、後から後悔することもあるでしょう。
できるだけスムーズに進めるためには、事前に必要な道具を準備しておくことが大切です。
例えば、ダンボールや収納ボックスを用意し、「残すもの」「形見分けするもの」「処分するもの」などに分類していくと、整理がしやすくなります。マーカーやラベルシールを使って、仕分けを明確にしておくと、後で見返したときに混乱せずに済むでしょう。
また、不用品の処分にはゴミ袋や軍手が必要ですし、大きな家具を動かす際には、作業しやすい服装や靴も用意しておくと安心です。遺品整理は長時間にわたることも多いため、水分補給のための飲み物も忘れずに用意しておきましょう。
遺品整理の具体的な進め方とスケジュール
遺品整理は、気持ちの整理とともに進めていく作業です。しかし、何から手をつければいいのかわからず、途中で手が止まってしまうこともあるかもしれません。
そこで、遺品整理をスムーズに進めるための具体的な流れと、目安となる作業期間について解説します。あくまで目安なので、自分のペースで進めながら、無理なく進行していきましょう。
遺品の仕分け(目安:1日~3日)
遺品整理の第一歩は、故人が残したものを「必要なもの」と「不要なもの」に分ける作業です。整理しながら故人との思い出がよみがえり、手を止めたくなる瞬間もあるかもしれません。無理に急がず、自分の気持ちと向き合いながら、少しずつ整理を進めていきましょう。
仕分けの際には、「形見として残すもの」「譲るもの」「売却・寄付するもの」「処分するもの」といったカテゴリに分けていくと、後の作業がスムーズになります。特に重要な書類や貴重品は、すぐに必要になることもあるため、紛失しないように別の場所に保管しておくのが安心です。
一人で進めるのが難しい場合は、家族や親族と協力しながら、故人の思い出を大切にしつつ進めていくとよいでしょう。
不用品の処分方法(目安:1日~1週間)
仕分けが終わったら、不要になったものの処分を進めます。
比較的小さなものや一般的なゴミは、自治体のルールに従って処分できますが、大型の家具や家電が多い場合は、粗大ゴミ回収やリサイクル業者に依頼する必要があります。処分するものの量や種類によっては、回収日を調整しながら進めることになるため、余裕をもったスケジュールを立てておくとよいでしょう。
また、状態の良い衣類や家具、家電は、リサイクルショップや寄付団体に引き取ってもらえることもあります。「すぐに捨てるのはもったいない」と感じるものがあれば、リユースを検討するのも選択肢の一つです。
不用品の量が多く、自力で処分するのが難しい場合は、不用品回収業者や遺品整理業者に依頼すると、短期間でスムーズに整理が進みます。業者を利用する際は、料金やサービス内容を事前にしっかり確認しておきましょう。
片付け後の清掃と整理(目安:数時間~1日)
遺品整理が終わった後は、部屋の清掃を行い、必要なものを整理整頓していきます。
長年使われていなかった家具の下や押し入れの奥など、普段は手が届きにくい場所にはホコリが溜まっていることが多いため、掃除機や雑巾で丁寧に拭き掃除をすると、気持ちもすっきりするでしょう。
また、今後その部屋をどう使うのかも考えながら、必要なものを収納していくことが大切です。家族が引き続き使うのか、それとも売却や賃貸に出すのかによって、片付け方も変わってきます。
もし、故人が住んでいた家を手放す予定がある場合は、不動産会社や専門業者と相談しながら進めるのもよいでしょう。
遺品整理を自分でやる vs 業者に依頼する
遺品整理を進めるにあたって、「自分たちで整理するべきか、それとも業者に依頼するべきか」と迷う方も多いでしょう。それぞれにメリットとデメリットがあるため、自分たちの状況に合った方法を選ぶことが大切です。ここでは、それぞれの方法について詳しく解説します。
自分で行う場合
自分で遺品整理を進める場合、故人の思い出にじっくりと向き合いながら作業を進めることができます。特に、故人が大切にしていたものを一つひとつ確認しながら整理したい方にとっては、自分で行うことに大きな意味があるでしょう。
また、業者に依頼する費用を抑えられるという点もメリットの一つです。作業のペースを自分たちで決められるため、時間のあるときに少しずつ整理を進めることも可能です。
しかし、自分たちだけで行う場合、どうしても時間と労力がかかります。特に、大量の荷物や大型家具がある場合は、搬出や処分に大きな負担がかかることもあります。また、気持ちの整理がつかないまま作業を始めてしまうと、途中で手が止まってしまうこともあるかもしれません。
さらに、遺品の中には貴重品や重要書類が紛れていることも多く、見落とさないよう注意が必要です。誤って処分してしまうと後で後悔することになりかねないため、慎重に作業を進めることが求められます。
業者に依頼する場合
遺品整理業者に依頼する最大のメリットは、短期間で作業が完了する点です。専門のスタッフが手際よく作業を進めてくれるため、時間がない方や遠方に住んでいて頻繁に整理に通えない方にとっては、非常に助かる選択肢となります。
また、重たい家具や家電の搬出、不用品の処分など、体力的な負担を減らせるのも大きなメリットです。遺品整理の経験が豊富な業者であれば、価値のある品物の買取やリサイクルなども提案してくれることがあります。
一方で、業者に依頼する際は費用が発生します。作業内容や部屋の広さによって金額は変動するため、依頼前に見積もりを取ることが大切です。相場を把握するためにも、複数の業者に見積もりを依頼し、料金やサービス内容を比較するとよいでしょう。
また、業者によっては作業が雑だったり、必要なものまで処分されてしまう可能性もあるため、信頼できる業者を選ぶことが重要です。口コミや評判をチェックし、事前にしっかり打ち合わせを行うことで、トラブルを防ぐことができます。
遺品整理でよくあるトラブルと対策
遺品整理は単なる片付けではなく、故人の思い出や財産を整理する大切な作業です。しかし、思いが詰まった遺品を扱うため、親族間の意見の食い違いや業者とのトラブルが発生しやすいのも事実です。ここでは、遺品整理でよくあるトラブルと、それを回避するための対策を解説します。
親族間のトラブル(形見分けの分配で揉める)
遺品整理を進める際、最も多いのが親族間のトラブルです。特に、形見分けに関する意見の相違や、故人の遺品を誰がどのように引き継ぐのかで揉めるケースが少なくありません。
例えば、「母が大切にしていた指輪を姉が持ちたいと言ったが、私も欲しかった」「父の思い出の品を処分するか残すかで親族間の意見が割れた」など、感情が絡むため冷静に話し合うのが難しくなることもあります。
対策としては、事前に親族でしっかり話し合い、ルールを決めることが重要です。 遺言書がある場合は、それに従って遺品を分配するとトラブルを防ぎやすくなります。遺言書がない場合でも、遺品整理を始める前に「誰がどの品を引き継ぐのか」を決めておくことで、争いを未然に防げます。どうしても意見がまとまらない場合は、第三者(弁護士や専門家)に相談するのも一つの方法です。
悪徳業者に騙される(見積もりの不透明な業者には注意)
遺品整理の業者に依頼する際、トラブルになりやすいのが「高額な請求」や「不当な追加料金」です。特に、事前の見積もりが曖昧だった場合、作業後に「予想以上の量があった」と言われ、高額な請求をされることもあります。
また、悪質な業者の中には、不用品の回収費を過剰に請求したり、貴重品を無断で持ち去ったりするケースも報告されています。「作業を依頼したのに、適当な対応で雑に扱われた」「見積もりよりもはるかに高額な請求を受けた」というトラブルも後を絶ちません。
こうしたトラブルを防ぐためには、信頼できる業者を選ぶことが何よりも大切です。 業者を選ぶ際は、遺品整理士の資格を持っているか、過去の実績や口コミを確認するようにしましょう。また、複数の業者から見積もりを取り、内容を比較することで、不透明な料金設定を避けることができます。契約前には「追加料金が発生しないか」「どこまで対応してくれるのか」を明確にしておくと、後々のトラブルを防ぎやすくなります。
貴重品を誤って処分(重要書類を見落とさないよう慎重に)
遺品整理の際、もう一つ気をつけたいのが「貴重品の誤廃棄」です。故人が大切に保管していた通帳や不動産の権利書、貴金属、印鑑などが遺品の中に紛れ込んでいることは少なくありません。しかし、膨大な荷物を整理する中で、誤って重要なものを処分してしまうケースも多く見受けられます。
「大切な書類が見つからない」「親族が必要としていた貴重品を誤って捨ててしまった」といった事態を防ぐためには、まず貴重品や重要書類を最優先で探し、整理することが必要です。 遺品整理を始める際は、故人がよく使っていた机の引き出し、金庫、本棚などを最初に確認しましょう。また、衣類や本の間など、意外な場所に貴重品が隠れていることもあるため、慎重にチェックすることが大切です。
業者に依頼する場合も、貴重品が紛れていないかを確認しながら進めてもらうように伝えましょう。作業前に「このエリアのものは処分しない」などの指示を出しておくと、誤廃棄のリスクを減らせます。
デジタル遺品の整理方法
現代では、多くの人がスマホやパソコンを日常的に利用しており、その中には大切なデータや個人情報が数多く含まれています。遺品整理では、故人の持ち物だけでなく、こうしたデジタルデータの扱いについても考えなければなりません。SNSアカウントやネット銀行の情報、サブスクリプション契約などを放置してしまうと、トラブルに発展する可能性もあるため、適切に対応することが大切です。
故人のスマホやPCのパスワード管理
故人のスマホやパソコンには、写真やメール、重要なファイルが保存されていることが多いため、これらのデータを適切に整理することが重要です。しかし、パスワードが分からないと、端末のロックが解除できず、データの確認や削除ができないケースもあります。
まず、故人が生前に使用していたパスワードを推測できる手がかりを探してみましょう。メモ帳や手帳に記載されている場合もありますし、よく使っていたメールアドレスや誕生日、記念日などを組み合わせたパスワードを設定していることもあります。
もし、どうしてもパスワードが分からない場合は、AppleやGoogle、Microsoftなどのアカウントサポートセンターに問い合わせを行い、相続人としてアクセスできる方法を確認しましょう。手続きには死亡証明書や戸籍謄本の提出が必要になることが多いため、事前に準備しておくとスムーズです。
SNSアカウントの削除や凍結
SNSアカウントは放置すると、不正アクセスや乗っ取りのリスクがあるため、適切に削除または凍結する必要があります。
FacebookやInstagramなどのSNSには、故人のアカウントを「追悼アカウント」として残す機能があるため、思い出として残しておきたい場合は、この設定を利用することもできます。一方で、完全に削除したい場合は、各プラットフォームのサポート窓口に連絡し、必要な手続きを行いましょう。
例えば、Twitter(X)やLINEでは、相続人が故人の死亡証明書や関係を証明する書類を提出することでアカウントの削除が可能になります。手続きには一定の時間がかかることがあるため、早めに対応するのが望ましいでしょう。
ネット銀行・サブスク契約の解約
故人がネット銀行を利用していた場合、口座がそのままになっていると、不正引き出しや未払いの自動引き落としなどの問題が発生する可能性があります。そのため、まずは故人の銀行口座を特定し、相続の手続きを進めることが大切です。
ネット銀行の場合、相続手続きには各銀行のサポート窓口への問い合わせが必要です。口座の解約には、死亡証明書や相続人であることを証明する書類(戸籍謄本など)の提出が求められることが多いため、事前に確認しておきましょう。
また、NetflixやAmazonプライム、Spotifyなどのサブスクリプション契約も、故人が亡くなった後も課金が続く可能性があるため、解約手続きを進める必要があります。サブスクの契約状況は、故人のメールアカウントに届く請求通知やクレジットカードの利用履歴を確認すると把握しやすくなります。契約ごとに解約方法が異なるため、公式サイトのサポートページを参考にしながら手続きを進めるとよいでしょう。
遺品整理が遅れるリスクと注意点
大切な人を亡くした後、すぐに遺品整理をするのは気持ちの整理がつかず難しいこともあるでしょう。しかし、長期間放置してしまうことで、思わぬリスクが発生する可能性があります。遺品整理を後回しにすると、金銭的な負担が増えるだけでなく、空き家の管理や防犯の面でも注意が必要です。ここでは、遺品整理が遅れることで起こりうる問題と、その対策について解説します。
家賃・固定資産税の負担が増加
故人が賃貸物件に住んでいた場合、亡くなった後も契約が継続されるため、相続人が家賃を支払う必要があります。解約手続きを行わなければ、数ヶ月間家賃を払い続けることになり、大きな負担となるでしょう。特に、都市部の賃貸物件では毎月の家賃が高額になりやすいため、早めの対応が求められます。
また、故人が持ち家を所有していた場合、固定資産税の負担が続きます。固定資産税は毎年1月1日時点での所有者に課されるため、相続手続きを進めないと相続人が支払い義務を負うことになります。相続放棄を考えている場合でも、手続きをしない限りは税金の請求が続く可能性があるため、早めに専門家に相談するのが賢明です。
空き家問題(特定空家指定による固定資産税の増額)
故人の住んでいた家が空き家になってしまうと、放置することで「特定空家」に指定されるリスクがあります。特定空家とは、管理が不十分で倒壊の恐れがあったり、衛生面で問題があったりする住宅のことを指します。自治体によっては、特定空家と判断された物件に対し、指導や勧告が行われるだけでなく、最終的には行政代執行による解体が実施されることもあります。
さらに、通常の住宅は固定資産税が軽減される措置が取られていますが、特定空家に指定されると、その軽減措置が解除され、固定資産税が最大6倍に増額される可能性があります。これは長期間空き家を放置した結果、予想以上の費用負担が発生することを意味します。特に、相続人が複数いる場合は、物件の管理や売却について早めに話し合いを進めることが重要です。
盗難・空き巣のリスク
故人の家が空き家の状態で長期間放置されていると、空き巣や不法侵入のリスクが高まります。特に、郵便物が溜まっていたり、雨戸が閉めっぱなしになっていたりすると、不在が明らかになり、犯罪のターゲットになりやすくなります。
また、空き家となった住宅は、火災や不法投棄のリスクも伴います。長期間放置された家では、電気やガスがそのままになっていることで火災の原因になることもありますし、不審者がゴミを不法投棄するケースも報告されています。こうしたリスクを避けるためには、定期的に家の状況を確認し、必要に応じて売却や解体、管理会社への委託などの対応を検討することが大切です。
遺品整理をスムーズに進めるためのポイント
遺品整理は、思った以上に時間と労力がかかる作業です。気持ちの整理がつかないうちに始めると、作業が進まなかったり、親族間で意見が合わなかったりすることもあります。そのため、事前に計画を立て、必要な準備を整えておくことが大切です。ここでは、遺品整理をスムーズに進めるための具体的なポイントをご紹介します。
早めにスケジュールを立てる
遺品整理は、1日で終わるような作業ではありません。特に、故人の住居が賃貸だった場合は、契約終了の期限が迫っていることもあるため、早めにスケジュールを決めることが大切です。
まずは、いつまでに整理を終える必要があるのかを明確にし、作業を何日間に分けて進めるのかを考えましょう。親族と一緒に行う場合は、全員の予定を調整し、無理のない範囲で日程を決めることがポイントです。
また、遺品整理は精神的な負担も大きいため、一気に片付けようとせず、少しずつ進めることを意識すると良いでしょう。部屋ごと、アイテムごとに整理する順番を決めておくと、効率的に進められます。
必要な道具を揃えておく
遺品整理をスムーズに進めるためには、作業に必要な道具を事前に用意しておくことが重要です。途中で道具が足りず、何度も買い足しに行くことになると、その分時間も手間もかかってしまいます。
特に必要になるのが、ダンボールやゴミ袋、ガムテープ、マジックペンなどの整理用品です。仕分けた遺品がどのような用途で残されるのか、あるいは処分するのかを分かりやすくするために、ラベルを貼ることもおすすめです。
また、大きな家具や家電を処分する場合は、運び出しの際に必要となる養生テープや軍手、工具なども揃えておくと、スムーズに作業が進みます。
業者に依頼する場合は相見積もりを取る
遺品の量が多い、整理する時間が取れない、力仕事が難しいといった場合は、遺品整理業者に依頼するのも一つの方法です。ただし、業者によってサービス内容や料金が異なるため、適切な業者を選ぶためには「相見積もり」を取ることが大切です。
相見積もりとは、複数の業者に見積もりを依頼し、それぞれの料金やサービス内容を比較することを指します。これを行うことで、適正価格を把握し、悪徳業者に引っかかるリスクを減らすことができます。
また、業者に依頼する場合は、事前にどのような作業をお願いできるのかを確認しておくことが重要です。不用品の処分だけでなく、貴重品の仕分けや供養、清掃まで対応してくれる業者もあるため、自分たちの状況に合ったサービスを提供してくれるところを選びましょう。
まとめ|遺品整理は適切なタイミングで計画的に行おう
遺品整理は、故人との思い出と向き合う大切な時間であると同時に、精神的・肉体的な負担が大きい作業でもあります。進めるタイミングや方法に正解はなく、ご遺族の気持ちや状況に合わせて無理なく進めることが大切です。
一方で、相続手続きや賃貸の退去期限、税金の負担など、一定のタイミングで対応しなければならないケースもあるため、事前にスケジュールを決めておくとスムーズに進められます。また、親族間のトラブルを避けるためにも、話し合いを重ねながら、納得のいく形で整理を進めることが重要です。
気持ちの整理がつかないうちに急ぐ必要はありませんが、長期間放置するとさまざまなリスクが発生する可能性があります。手がつけられない場合は、遺品整理業者のサポートを活用するのも一つの方法です。
大切な人の遺品整理を、あなたらしい形で進めていきましょう。
「遺品整理を始めたいけれど、何から手をつければいいかわからない…」
「親族と話し合いながら進めたいけれど、意見がまとまらない…」
「体力的にも時間的にも、自分たちだけでは難しい…」
このようなお悩みをお持ちの方は、【ココロセイリ】にご相談ください。
【ココロセイリ】は、ご遺族の気持ちに寄り添いながら、適切な方法で遺品整理をサポートする専門業者です。
- ご遺族の想いを大切に、形見分けや供養の対応も可能です
- 明確な料金体系、事前に見積もりをお出しし、追加料金は一切なし
- 遺品整理士による安心のサービス、経験豊富な専門スタッフが対応いたします
遺品整理に関するお悩みやご不明点があれば、お気軽にご相談ください。
豊富な実績を持つ遺品整理の専門店「株式会社ココロセイリ」の代表取締役社長