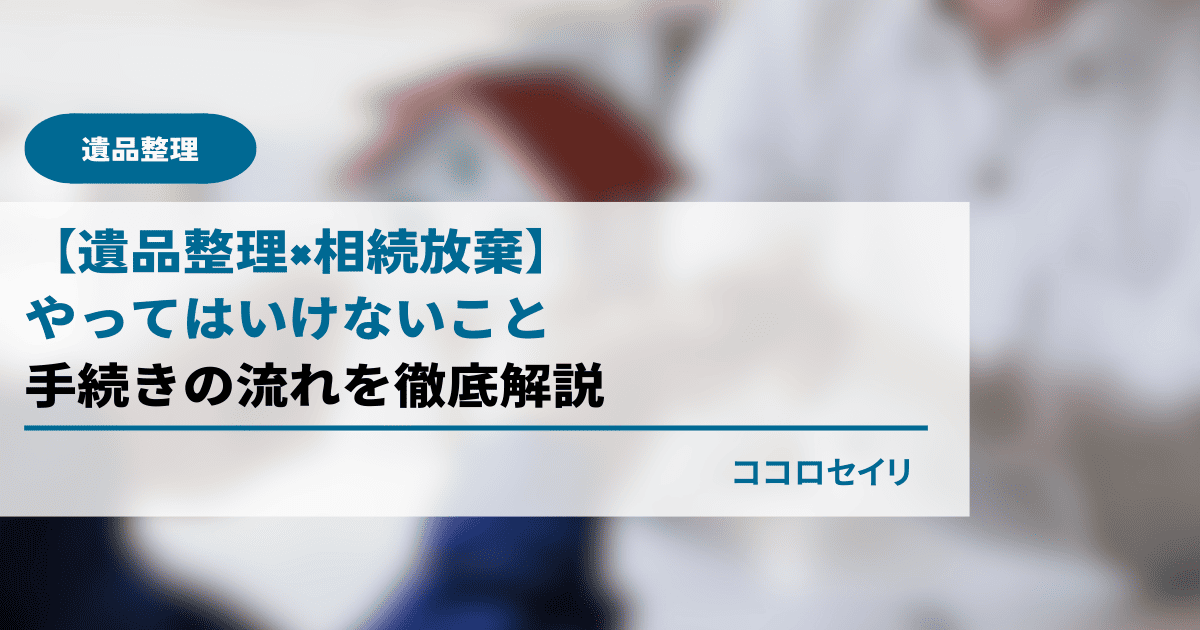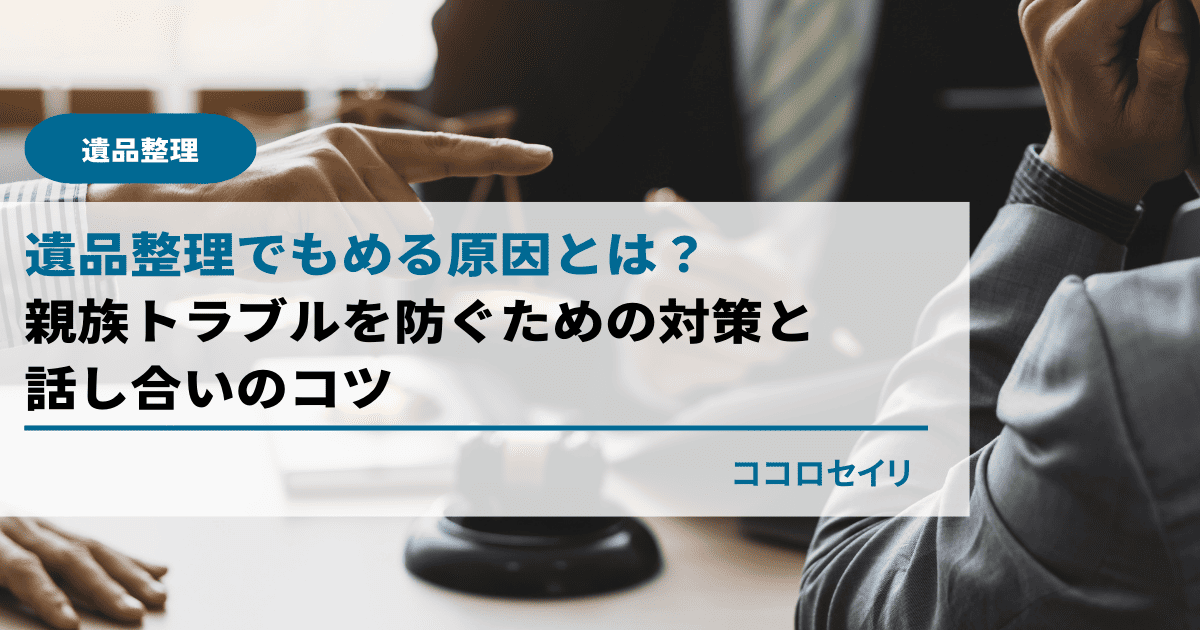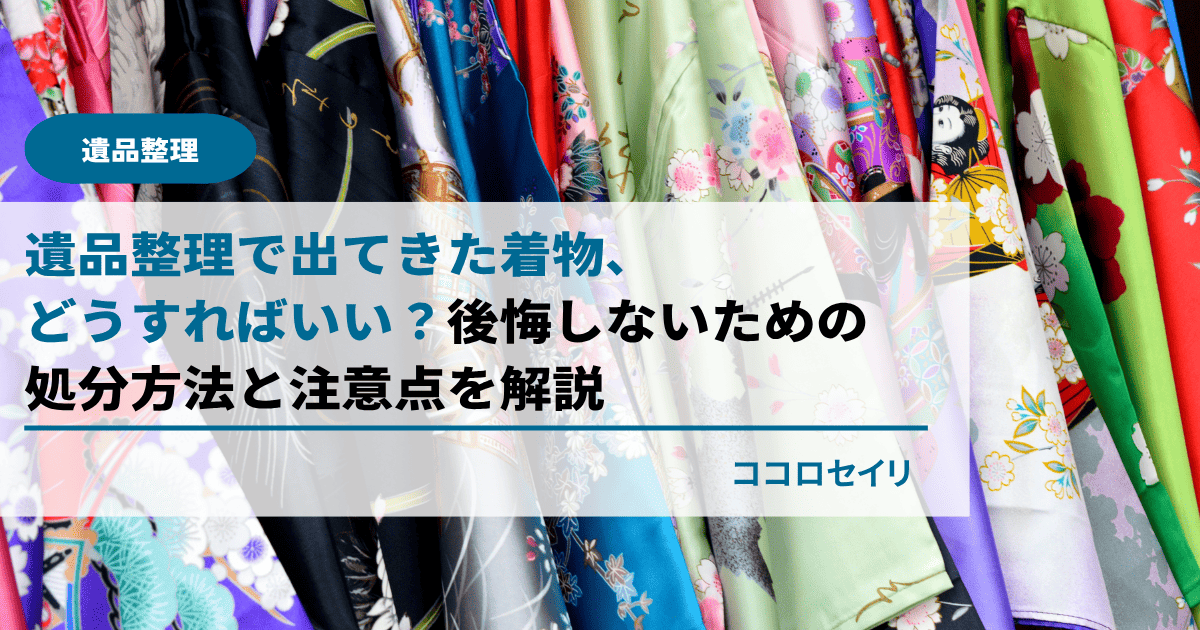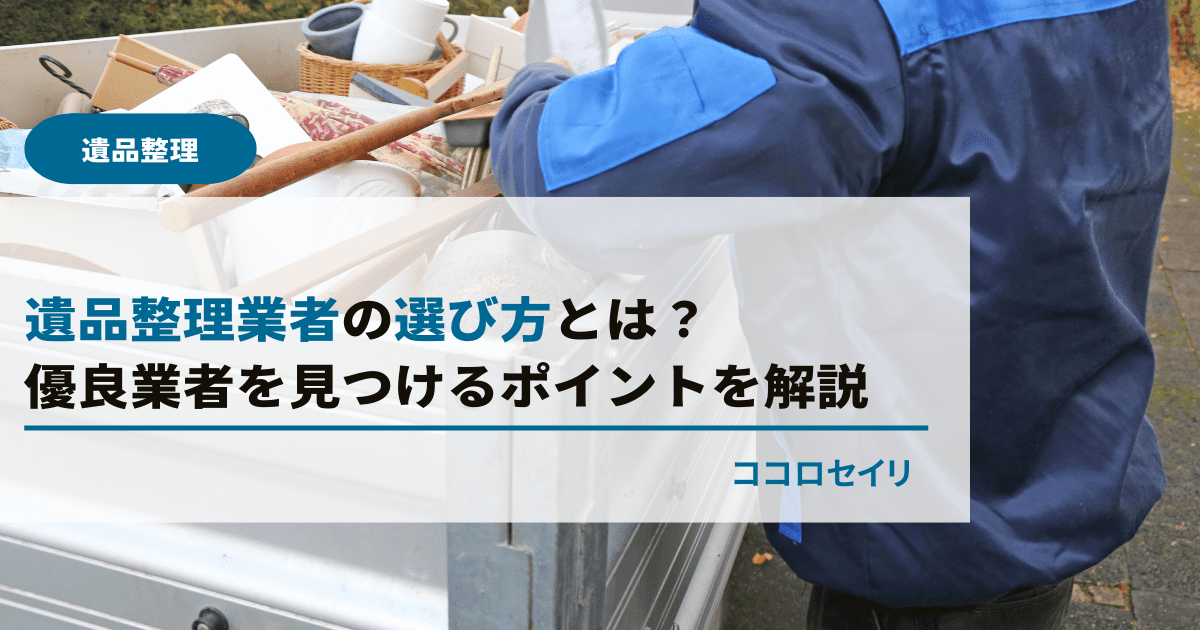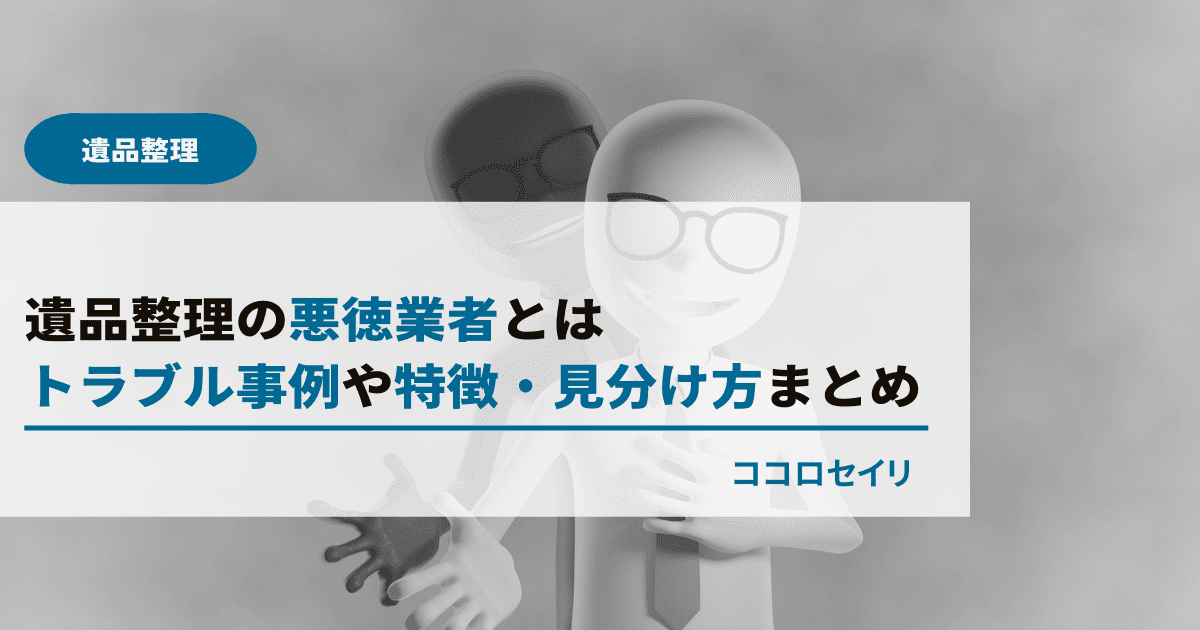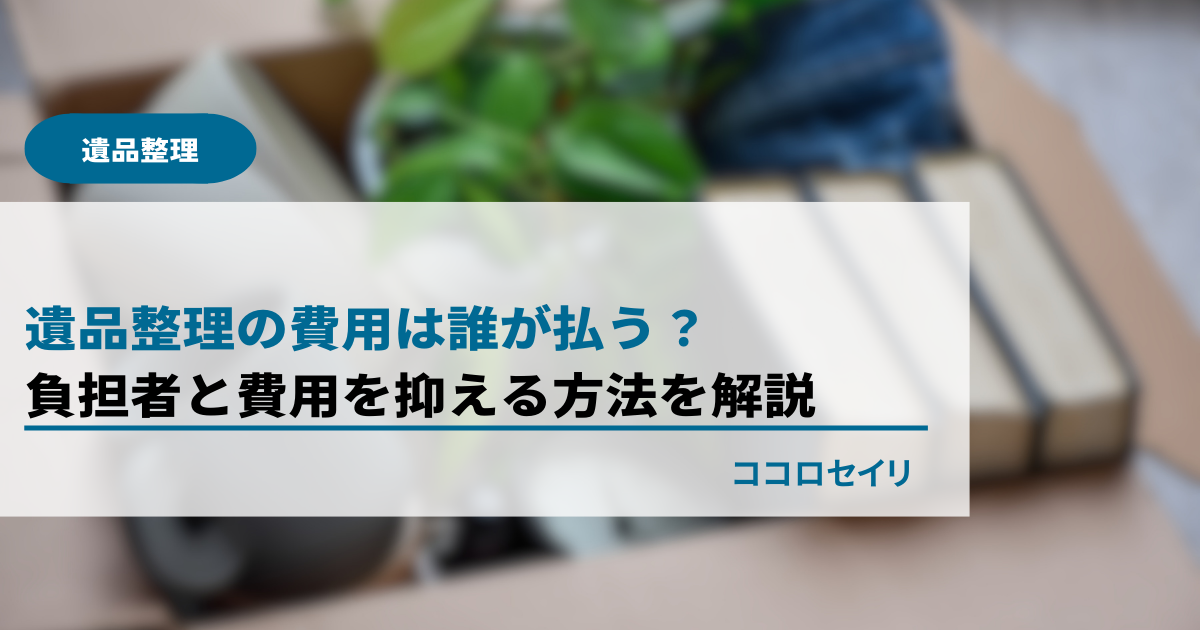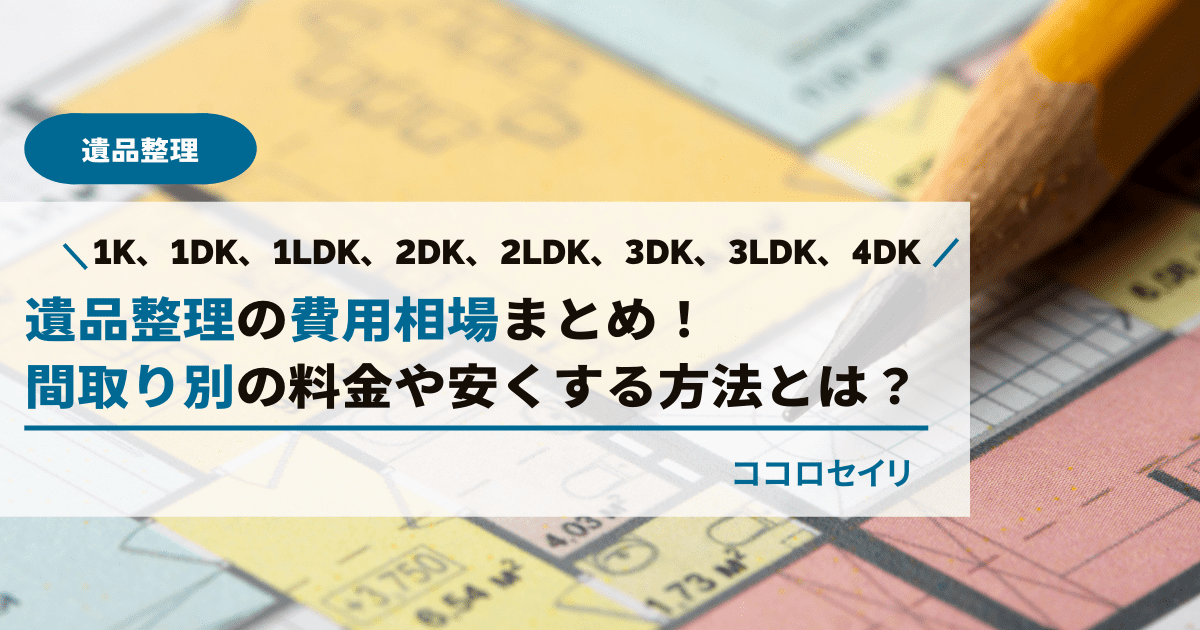親族が亡くなり、悲しみの中で進めなければならない遺品整理。しかし、故人に借金があった場合や、相続を放棄しようと考えていると、何をしていいのか分からず、不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
「相続放棄をすると、遺品整理はできない?」
「故人の荷物を片付けたら、相続放棄できなくなるって本当?」
「手続きを進める前に、やってはいけないことは?」
こうした疑問を抱えている方に向けて、本記事では相続放棄と遺品整理の関係、具体的な手続きの流れ、注意すべきポイントを詳しく解説します。
特に、相続放棄を予定している場合、誤った対応をすると「相続放棄が無効になる」リスクがあります。あとから取り消しができないため、慎重に進めることが大切です。
この記事を読めば、相続放棄を検討している方が、トラブルを避けながら遺品整理を進めるために必要な知識が得られます。ぜひ最後までお読みください。
※本記事は2025年2月時点で作成された記事です。法律関連の情報は日々更新されるため、士業の専門家にご確認いただくようお願いいたします。
豊富な実績を持つ遺品整理の専門店「株式会社ココロセイリ」の代表取締役社長
目次
相続放棄と遺品整理の関係とは?まず知っておくべき基礎知識
遺品整理は、故人が残した品々を整理し、処分や保管の判断を行う大切な作業です。一方、相続放棄とは、故人の財産(プラスの財産・マイナスの財産)を一切受け継がない手続きのことを指します。この2つの関係性を理解しないまま進めてしまうと、意図せず「相続を承認した」とみなされる可能性があるため、慎重に対応する必要があります。
相続放棄をすると、基本的には故人の財産に関する権利も義務も放棄することになります。そのため、相続放棄をした相続人が遺品整理を行うと、民法上「単純承認(=相続を受け入れたとみなされる状態)」と見なされる可能性があります。しかし、すべての遺品整理が禁止されるわけではなく、最低限の管理義務は残るため、どこまで手をつけてよいのかを事前に理解しておくことが大切です。
相続放棄とは?
相続放棄とは、相続人が被相続人(亡くなった人)の財産や負債を一切受け継がない手続きです。これは、主に故人に多額の借金がある場合や、財産を相続したくない特別な事情がある場合に選択されます。
通常、相続には以下の3つの選択肢があります。
- 単純承認(すべての財産と負債を相続する)
- 限定承認(財産の範囲内で負債を引き継ぐ)
- 相続放棄(一切の財産や負債を相続しない)
相続放棄をすることで、借金の返済義務を免れることができますが、同時にプラスの財産(預貯金・不動産など)も一切相続できなくなるため、慎重な判断が求められます。
参考:相続の放棄の申述
相続放棄の具体的な流れ
相続放棄は、相続の開始(被相続人が亡くなったこと)を知った日から3カ月以内に手続きを行う必要があります。以下が、相続放棄の一般的な流れです。
- 相続財産の調査
- 家庭裁判所への申立て
- 相続放棄の受理
- 次順位の相続人に権利が移る
相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったとみなされるため、債権者(故人の借金を請求する金融機関など)からの督促を受けることはなくなります。ただし、家族内で相続人が誰もいなくなった場合、自治体が財産管理人を指定し、最終的な処理を行うことになります。
相続放棄をすると、遺品整理はできない?
結論から言うと、相続放棄をすると原則として遺品整理はできません。
これは、民法第921条(法定単純承認)の規定により、相続人が遺産を勝手に処分すると「相続を承認した」とみなされるためです。特に、以下のような行為は注意が必要です。
- 貴重品(宝石・貴金属など)を処分する
- 実家の売却や解体を進める
- 故人の車や不動産の名義変更を行う
これらを行うと、相続を放棄したはずなのに「単純承認」と見なされ、借金などの負債も引き継ぐことになってしまいます。
ただし、相続放棄をしても「遺品の管理義務」は一定期間発生します。これは、次の相続人が遺産を引き継ぐまで、故人の財産を適切に保管する責任があるためです。
例えば、以下のような場合には、相続放棄をしても遺品を管理しなければならない可能性があります。
- 次の相続人が決まるまでの間、遺品をそのまま保管する必要がある
- 故人が賃貸住宅に住んでいた場合、退去の手続きを進めなければならない
- 相続放棄をした人以外に相続人がいない場合、財産管理人が決まるまで適切に管理する必要がある
管理義務の範囲は「最低限の保全」にとどまるため、相続財産を勝手に処分するのではなく、現状維持に努めることが重要です。
相続放棄を予定している人が遺品整理でやってはいけないこと
相続放棄を考えている場合、遺品整理の進め方には十分な注意が必要です。民法では、相続財産を処分すると相続を承認したものとみなされる「単純承認」 というルールが定められています。これにより、誤った対応をすると、相続放棄の手続きが無効になり、借金や負債も引き継ぐことになってしまう可能性があります。
ここでは、相続放棄を予定している人が絶対にやってはいけない行為について詳しく解説します。
相続財産を処分すると「単純承認」とみなされるケース
相続放棄を検討している場合、遺品や財産に手をつけることで「相続を承認した」とみなされるケースが多くあります。特に、高額な財産や貴重品を処分したり、財産を引き出したりする行為は厳禁です。
預貯金の引き出し、解約、名義変更
相続放棄を予定している人は、故人の銀行口座からお金を引き出したり、口座を解約したりすることはできません。銀行口座の名義変更も、相続を承認したとみなされる行為の一つです。
仮に、葬儀費用の支払いのために故人の預金を引き出した場合でも、法律上は「遺産を利用した」=相続したと判断される可能性があります。葬儀費用の精算は、相続放棄をしても支払うことが可能ですが、まずは相続放棄の手続きが完了するまで、預金に手をつけないことが重要です。
実家や賃貸物件の解約・売却・解体
故人が住んでいた実家や賃貸物件に関しても、相続放棄をする前に解約や売却、解体を行うと、相続を承認したとみなされるため注意が必要です。
- 実家の売却・解体 → 財産の処分とみなされるためNG
- 賃貸物件の解約 → 契約の解除行為が「相続を認めた」と判断される可能性がある
ただし、賃貸物件に関しては家賃の発生を避けるため、大家や管理会社と相談のうえ対応する必要があります。解約を行う場合も、相続放棄の手続きが完了してから行うのが安全です。
家具・家電・車・貴重品の処分
家の中にある家具や家電、故人の車、貴重品(宝石・金・美術品など)を勝手に処分すると、相続したとみなされる可能性があります。
特に以下のような行為には注意してください。
- 故人の車を売却する、または廃車手続きを行う
- 金銭的価値のある貴重品を譲渡・売却する
- 家電や家具を処分業者に依頼する
相続放棄を考えている場合、「遺品整理=処分」ではなく、「必要最低限の管理」に留めることが大切です。
デジタル遺品(SNSアカウント・サブスク契約・スマホデータ)の扱い方
最近では、デジタル遺品(SNSアカウント・サブスクリプション契約・スマホのデータ) の扱いも重要なポイントになっています。
- 故人のスマホを初期化・処分する
- SNSアカウントを勝手に削除する
- 有料サービスの解約手続きを行う
これらの行為も、相続財産の管理を超えた「処分行為」に該当する可能性があるため、相続放棄をする前には手をつけない方が安全です。
ただし、契約が継続することで負債が増える可能性のあるサービス(サブスクリプションなど)は、放置すると後々問題になるため、必要に応じて専門家(弁護士・司法書士)に相談することをおすすめします。
遺品整理の際にやってはいけない行動
相続放棄を考えている場合、相続財産の処分だけでなく、遺品整理の方法にも注意が必要です。ここでは、特に避けるべき行動を紹介します。
形見分けで遺品を持ち出す
遺品整理の際、故人の思い出の品を形見分けすることはよくあります。しかし、相続放棄をする予定であるにもかかわらず遺品を持ち出すと、相続を承認したとみなされる可能性があるため注意が必要です。
例えば、
- 貴金属や時計を形見として持ち帰る
- 故人の愛用品を親族同士で分ける
これらの行為は「遺産を受け継いだ」と判断される場合があります。相続放棄を検討している場合は、形見分けも慎重に進めるようにしましょう。
遺品整理の費用を故人の財産から支払う
遺品整理の業者に依頼する際、故人の預金や現金を使って費用を支払うことも、相続を承認したと見なされる可能性が高いです。
相続放棄を考えている場合は、遺品整理業者への支払いは自費で行うか、相続放棄の手続きが完了するまで待つようにしましょう。
借金・税金・入院費を故人の資産から支払う
故人に借金や未払いの税金、医療費がある場合、相続放棄を予定している相続人が支払いを行うと、相続を承認したとみなされる可能性があります。
仮に支払いを行う場合は、相続放棄の手続きが完了してから対応するようにしましょう。また、未払いの税金や医療費については、相続放棄後に債権者(税務署や病院など)へ連絡し、支払い義務がないことを伝えることが重要です。
相続放棄をしても遺品整理が必要なケース
相続放棄をすると、基本的に故人の財産や負債を引き継ぐことはありません。しかし、すべての責任から解放されるわけではなく、場合によっては遺品整理をしなければならないケースもあります。特に、賃貸物件に住んでいた場合や、特定の契約に関与していた場合には、最低限の管理義務が発生することを理解しておく必要があります。
賃貸物件の明け渡しのための整理
故人が賃貸物件に住んでいた場合、相続放棄をしても部屋をそのまま放置することはできません。 賃貸物件の契約は、相続人に引き継がれるわけではなく、貸主(大家・管理会社)と相続放棄者との関係は維持されないためです。
ただし、相続放棄をすると賃貸契約の責任もなくなるため、基本的には相続人ではなく大家や管理会社が物件の処理を行うことになります。しかし、明け渡しが完了するまでの間、故人の家財道具が残されている場合は、最低限の管理が必要です。
この場合、以下のような流れで対応するのが一般的です。
- 管理会社や大家に相続放棄の意思を伝える
- 大家側が対応できるか確認する
- 遺品整理業者に相談し、必要最低限の管理を行う
基本的に、賃貸物件の明け渡しに関する手続きは、貸主側の責任で処理されることが多いため、相続放棄をした場合は速やかに管理会社に相談することが重要です。
連帯保証人になっていた場合の責任
故人の借金や賃貸契約に関して、相続放棄をすれば支払い義務がなくなると考えがちですが、もし故人の借金や家賃の支払いの連帯保証人になっていた場合は、相続放棄をしても責任が残る可能性があります。
- 家賃滞納があった場合、連帯保証人が残りの賃料を支払う義務がある
- 故人がローンを組んでおり、連帯保証人として契約していた場合、その支払い責任が発生する
このようなケースでは、相続放棄をしても保証人としての義務が継続するため、弁護士や司法書士に相談し、法的に適切な対応を検討する必要があります。
大家や管理会社との対応方法
故人が賃貸物件に住んでいた場合、相続放棄後の対応として最も重要なのは大家や管理会社との円滑なコミュニケーションです。
- 相続放棄をすることを伝え、部屋の明け渡しについて相談する
- 家財道具の処分について貸主側の対応方針を確認する
- 賃貸契約の解除手続きを進める(契約状況によっては不要な場合もあり)
管理会社や大家が部屋の明け渡しを主導してくれるケースもあるため、相続放棄を考えている場合はできるだけ早めに相談し、対応方法を確認することが重要です。
故人が孤独死した場合の対応
故人が賃貸物件や自宅で孤独死した場合、相続放棄をしたとしても、特殊清掃などの対応が必要になるケースがあります。
孤独死の場合、発見が遅れることが多く、室内の腐敗臭や害虫の発生などが問題となることがあります。そのため、遺族が相続放棄をしても、大家や管理会社が特殊清掃を依頼しなければならない状況が発生することがあります。
この際、特殊清掃の費用負担については契約内容によって異なりますが、相続放棄をしていれば基本的に相続人には支払い義務はありません。ただし、連帯保証人になっている場合は費用負担が発生する可能性があるため注意が必要です。
相続放棄後の財産管理義務
相続放棄をしたからといって、すぐにすべての責任がなくなるわけではありません。法的には、「現に占有している財産の管理義務」が一時的に残ることがあります。
「現に占有」している遺品は処分できない?
相続放棄をすると、相続人としての権利を失いますが、その時点で誰も相続しない状態が続くと、財産の管理者が不在になります。そのため、次の相続人が決まるまでの間、最低限の管理義務が発生することになります。
例えば、以下のような場合は遺品の管理をする必要があります。
- 故人の持ち家が空き家になり、第三者に不法占拠されないようにする
- 故人の財産が盗難に遭わないように適切に管理する
- 相続放棄をしても、財産がどう処分されるか決まるまで保全する
これらの管理義務は一時的なものであり、最終的には裁判所が財産管理人を選任することで、正式な処分が行われることになります。
財産管理人が選任されるまでの対応
相続放棄をした場合、すべての相続人が相続放棄を行うと、財産を管理する人がいなくなります。 この場合、家庭裁判所が「財産管理人」を選任し、財産の処分や管理を行うことになります。
財産管理人が選任されるまでの間、故人の財産を放置するわけにはいかないため、最低限の保全措置を講じる必要があります。 例えば、
- 故人の家の鍵を管理し、無断で第三者が立ち入らないようにする
- 貴重品が盗まれないように保管する
相続放棄をする際には、「誰が財産管理を行うのか」「どのタイミングで管理義務が終了するのか」を明確にしておくことが重要です。
相続放棄後に遺品整理を進める際のポイント
相続放棄をした後でも、遺品整理がまったく不要になるわけではありません。相続放棄によって故人の財産を相続する権利や義務はなくなりますが、状況によっては最低限の管理や整理が必要となるケースがあります。ただし、誤った方法で遺品整理を進めると「相続を承認した」とみなされるリスクがあるため、注意が必要です。
ここでは、相続放棄後に遺品整理を進める際の具体的なポイントについて解説します。
相続放棄の手続きが完了してから整理を始める
相続放棄をした後に遺品整理を行う場合、まず重要なのは相続放棄の手続きが正式に完了していることを確認することです。相続放棄は家庭裁判所で手続きを行い、受理されて初めて法的に成立します。
相続放棄の手続きが完了する前に遺品を処分すると、「単純承認」とみなされ、相続放棄が無効になる可能性があるため注意しましょう。相続放棄の手続きが完了しているかどうかは、家庭裁判所から発行される「相続放棄申述受理通知書」で確認できます。
また、相続放棄が認められたとしても、他の相続人(兄弟姉妹など)が財産を引き継ぐ可能性があるため、遺品整理を勝手に進める前に、他の相続人と連絡を取ることが重要です。
価値のないもの(衣類・日用品など)は処分OK
相続放棄をした後でも、価値のないもの(衣類・日用品・消耗品など)については処分しても問題ないとされています。例えば、以下のような品目は遺品整理の際に処分しても問題になることは少ないでしょう。
- 古い衣類・タオル・寝具
- 使用済みの化粧品・シャンプー類
- 壊れた家具・不要な家電製品
- 食品や日用品(賞味期限切れのもの)
ただし、価値のあるものと判断される可能性のある遺品(骨董品やブランド品など)は、専門家に相談するか、他の相続人の了承を得てから対応することをおすすめします。
貴重品・現金・不動産などは勝手に処分しない
相続放棄をした場合、貴重品や財産価値のあるものを勝手に処分すると、「相続を承認した」とみなされる可能性があるため、特に慎重に対応する必要があります。
以下のものは、たとえ相続放棄をしていても処分せずに保管しておくべきです。
- 故人の現金・預貯金・証券類
- 不動産(持ち家・土地)
- 貴金属・骨董品・ブランド品
- 故人名義の車・バイク
- 保険証券・契約書類(賃貸契約書・光熱費の請求書など)
相続放棄後は、基本的に次の相続人(兄弟姉妹や遠縁の親族)が相続を引き継ぐ可能性があるため、財産価値のあるものは勝手に動かさず、そのままの状態で保管するのが原則です。
もし、すべての相続人が相続放棄をした場合は、家庭裁判所が「相続財産管理人」を選任し、財産の処分が進められることになります。
遺品整理業者に依頼する場合の注意点
相続放棄後に遺品整理を進める場合、自分で整理をするのが難しい場合は遺品整理業者に依頼するという選択肢もあります。ただし、業者選びには注意が必要です。
- 遺品整理を依頼できる範囲を明確にする
- 悪徳業者に注意する
相続放棄を予定している人が遺品整理をする際の注意点
相続放棄を考えている場合、遺品整理をどのように進めるか慎重に判断する必要があります。相続放棄をした後は、遺産を一切相続しないことになるため、財産に関する行動が制限されることを理解しておくことが大切です。
ここでは、相続放棄を予定している人が遺品整理を進める際に注意すべきポイントについて解説します。
相続放棄の取り消しはできない
相続放棄は、家庭裁判所に申請し、受理されることで正式に成立します。しかし、一度受理された相続放棄は取り消しができません。
そのため、以下のようなケースに注意が必要です。
- 相続放棄をした後に、故人に価値のある財産(不動産・預貯金など)が見つかった
- 他の相続人が相続を拒否し、誰も財産を引き継がなくなった
- 相続放棄したことによって、思わぬトラブルが発生した
相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったとみなされるため、後から財産を相続することはできません。 そのため、手続きを進める前に、遺産の全体像を把握し、本当に相続放棄をするべきか慎重に判断することが重要です。
葬儀費用は相続財産から支払えるが、慎重に判断する
葬儀費用は、相続財産から支払うことが認められるケースがあります。 しかし、ここで注意すべき点は、相続放棄を予定している人が故人の預金を引き出して支払いを行うと、相続を承認したとみなされる可能性があることです。
相続放棄を考えている場合、故人の預貯金には手をつけず、まずは相続放棄の手続きを優先するのが安全です。葬儀費用の支払い方法としては、以下のような方法を検討するとよいでしょう。
①親族で負担する
相続放棄をする場合、葬儀費用は基本的に親族が負担することになります。ただし、相続人全員が相続放棄をした場合、誰が負担するかトラブルになることもあるため、事前に話し合っておくことが大切です。
②生命保険の死亡保険金を活用する
故人が生命保険に加入していた場合、死亡保険金は相続財産に含まれないため、相続放棄をしていても受け取ることが可能です。 そのため、保険金を活用して葬儀費用を支払うという方法も考えられます。
③葬儀費用の負担を後から請求する
相続放棄後でも、葬儀費用を負担した人は、財産管理人に対して葬儀費用の返還を請求できる場合があります。 ただし、全額が返還されるとは限らないため、専門家に相談しながら進めるのがよいでしょう。
財産調査を行い、明確な記録を残す(通帳・督促状・契約書など)
相続放棄をするかどうか判断するためには、まず故人の財産状況を正確に把握することが重要です。 これは、相続放棄をすることで不利益を被らないようにするためでもあり、手続きの流れをスムーズにするためでもあります。
相続放棄をする前に調査すべき財産の種類
相続放棄をするかどうか判断するために、以下のような財産の有無を確認しましょう。
- 預貯金(銀行口座)
- 不動産(土地・建物)
- 生命保険(受取人が指定されているかどうか)
- 有価証券(株・投資信託など)
- 借金(ローン・カードローン・保証人の有無)
- 未払いの税金(固定資産税・住民税など)
- クレジットカードの残高・未払い料金
- 光熱費・家賃・携帯料金の未払い
財産調査を行う方法
相続放棄をする前に、以下の方法で財産状況を確認し、記録を残しておくと安心です。
- 通帳・銀行の明細を確認する
- 督促状・請求書をチェックする
- 不動産の権利関係を調べる
- 借金やローンの有無を確認する
財産調査を適切に行い、財産目録(一覧表)を作成しておくと、相続放棄の判断がスムーズにできるため、事前の準備をしっかり行うことが大切です。
遺品整理と相続放棄に関するよくある質問
相続放棄を考えている人の中には、「遺品整理を進めてしまうと相続放棄ができなくなるのでは?」と不安に思う方も多いでしょう。相続放棄と遺品整理の関係は複雑で、誤った行動をすると相続を承認したとみなされる可能性があります。ここでは、相続放棄と遺品整理に関するよくある質問について、簡潔に解説します。
形見分けをしたら相続放棄が無効になる?
形見分けをすると、「遺産を処分した」とみなされ、相続放棄が無効になる可能性があります。特に、貴金属や骨董品など価値のある品を譲る行為は「相続の承認」と見なされるリスクが高いため注意が必要です。
どうしても形見分けをしたい場合は、相続放棄の手続きが正式に完了してから行うのが安全です。相続放棄をする前に故人の遺品を譲り合うのは避けたほうがよいでしょう。
遺品整理費用は誰が負担する?
相続放棄をすると、故人の遺産を引き継がないため、遺品整理費用も相続放棄者が負担する必要はありません。
しかし、相続人全員が相続放棄をした場合、財産管理人が選任されるまでの間、賃貸物件の管理や遺品整理の負担が発生することがあります。賃貸住宅の場合は、大家や管理会社と相談し、明け渡しの対応を進める必要があります。
遺品整理費用について不安がある場合は、財産管理人が決まるまで待つか、弁護士に相談するのがよいでしょう。
相続放棄しても故人の荷物の処分を頼まれた場合は?
相続放棄をしても、次の相続人や大家などから「遺品を整理してほしい」と依頼されることがあります。
この場合、単なる「保管や管理」の範囲内であれば問題ありませんが、勝手に処分すると相続を承認したとみなされる可能性があるため注意が必要です。 処分を依頼された場合は、相続放棄をしたことを伝え、財産管理人が決まるまで待つようにするのが安全です。
すでに一部の遺品を処分してしまった!相続放棄できる?
相続放棄前に誤って遺品を処分してしまった場合、内容によっては「単純承認」と見なされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。
しかし、日用品や衣類など価値のないものの処分であれば、相続放棄が認められるケースもあります。 貴重品や財産価値のあるものを処分してしまった場合は、相続放棄が難しくなる可能性があるため、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。
まとめ|相続放棄と遺品整理の注意点を理解し、正しく手続きを進めよう
相続放棄を考えている場合、遺品整理の進め方には慎重な判断が求められます。 うっかり財産に手をつけてしまうと、相続を承認したとみなされ、意図せず借金や負債を引き継ぐリスクがあるためです。
この記事で解説したように、相続放棄をする際は、まず手続きを完了させてから遺品整理を行うことが重要です。特に、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 遺産を処分すると相続を承認したとみなされるため、勝手に処分しない
- 賃貸物件の明け渡しや財産管理義務が発生するケースがあるため、慎重に対応する
- 相続放棄をする前に、財産の調査を行い、記録を残しておく
- 遺品整理業者に依頼する場合は、信頼できる業者を選ぶことが大切
相続放棄と遺品整理の問題は、法律や契約状況によって異なり、専門家のアドバイスが必要になるケースも多くあります。
また、相続放棄を予定している方へ、相続放棄を考えているものの、
「遺品整理をどう進めていいか分からない…」
「賃貸物件の明け渡しや管理義務について不安がある…」
「法律に詳しくないので、トラブルにならないか心配…」
このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ【ココロセイリ】にご相談ください。
私たちは、相続放棄を予定している方の状況に寄り添いながら、適切な遺品整理のサポートを行っています。
- 相続放棄後の遺品整理の進め方
- 賃貸物件の明け渡しに関する対応
- 処分しても問題のない遺品の判断
「一人で悩まず、まずはご相談を。」
あなたの状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。お気軽にご連絡ください。
豊富な実績を持つ遺品整理の専門店「株式会社ココロセイリ」の代表取締役社長