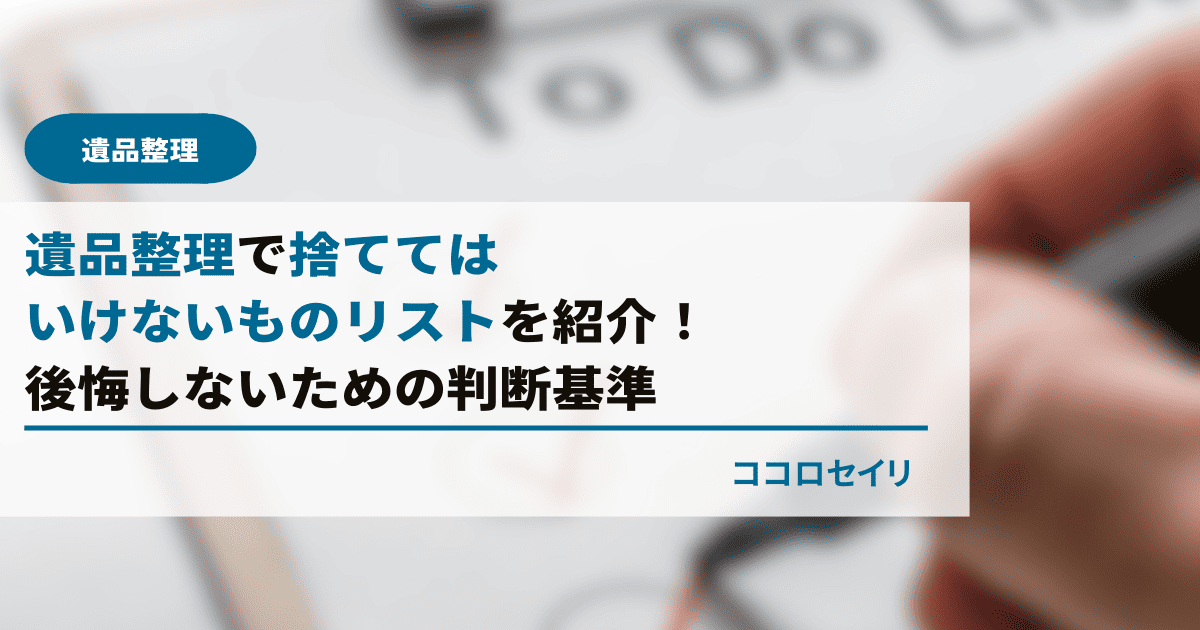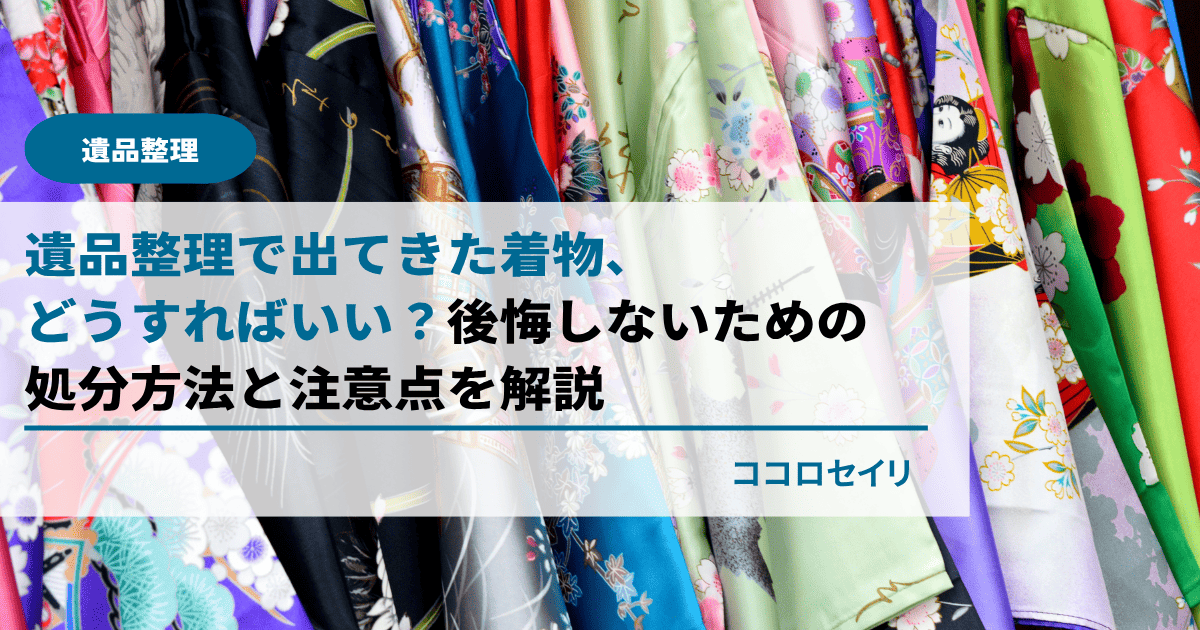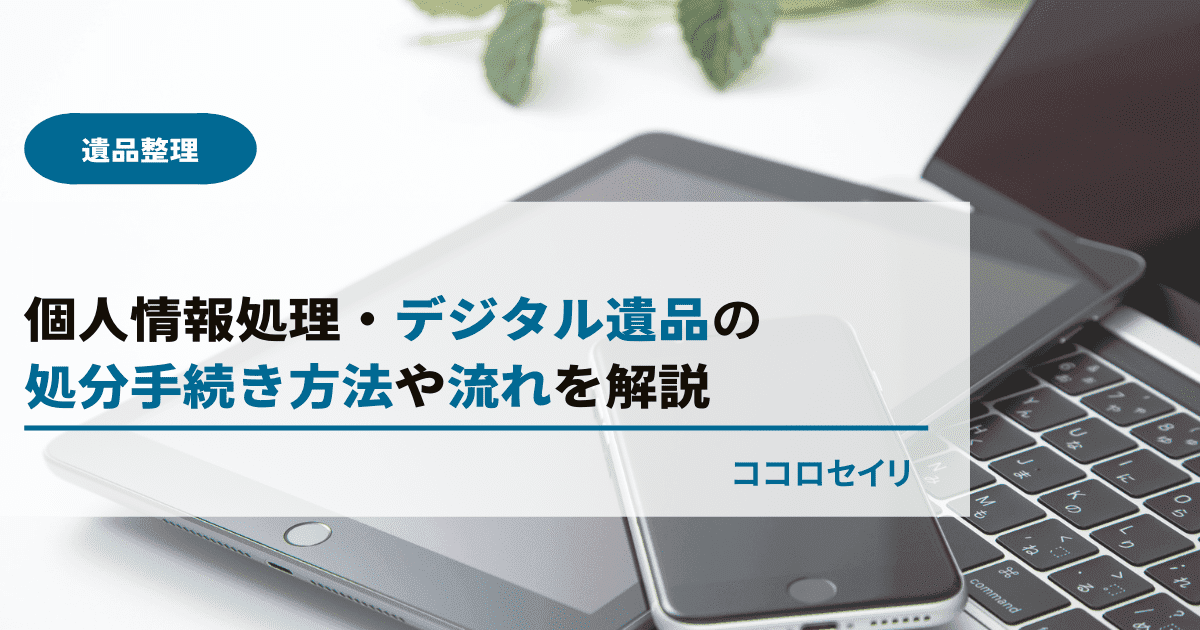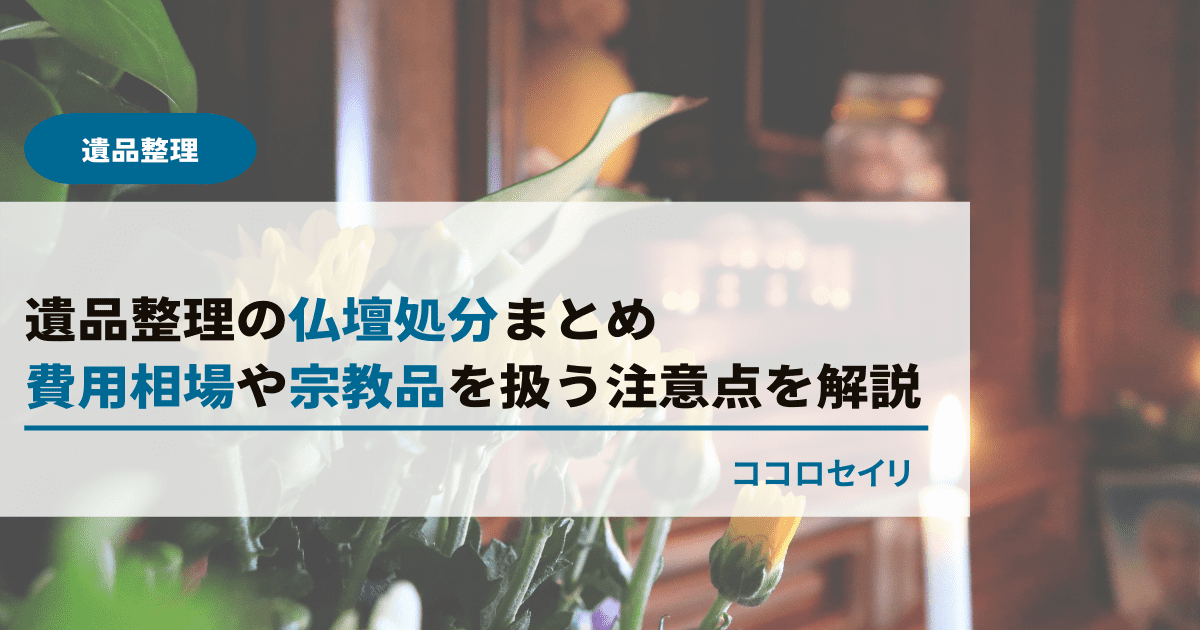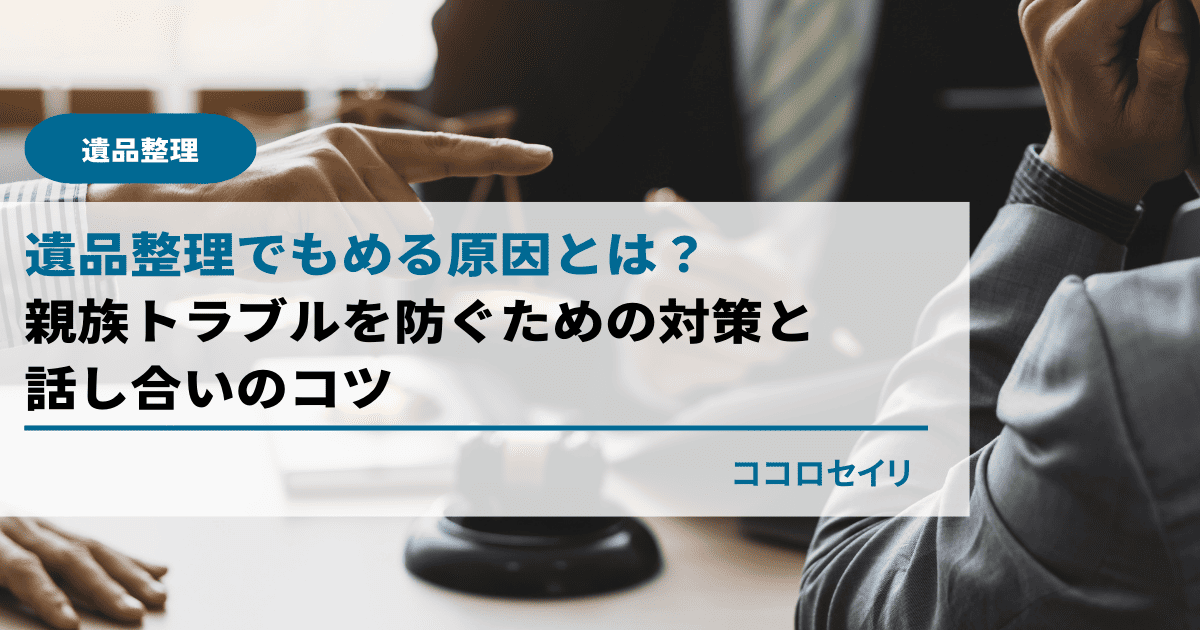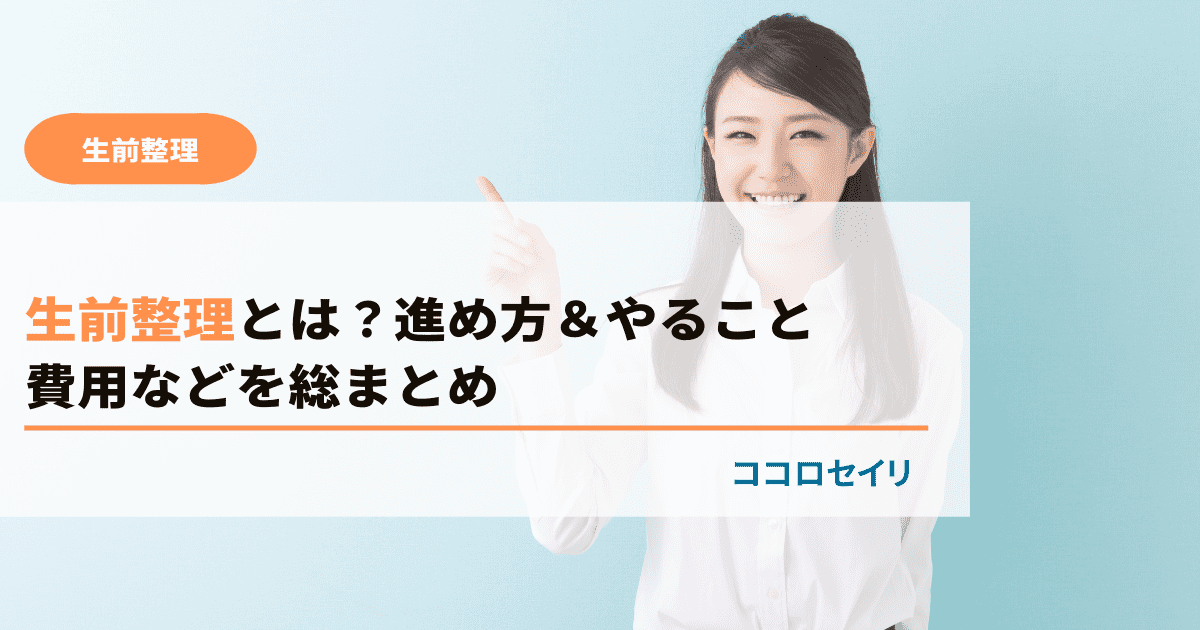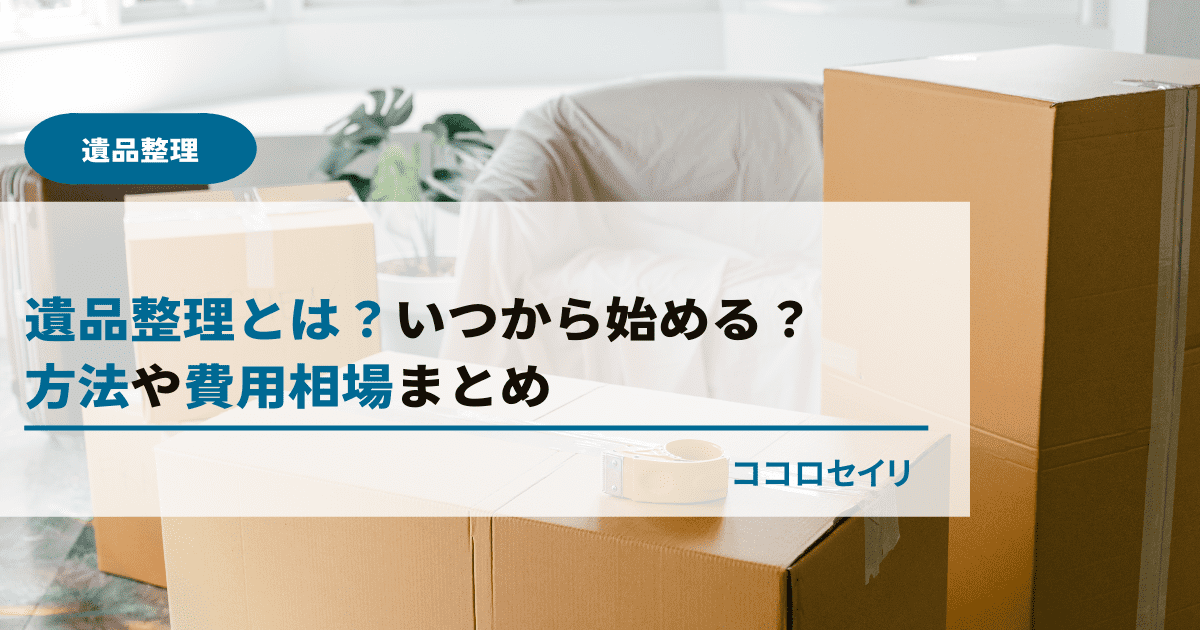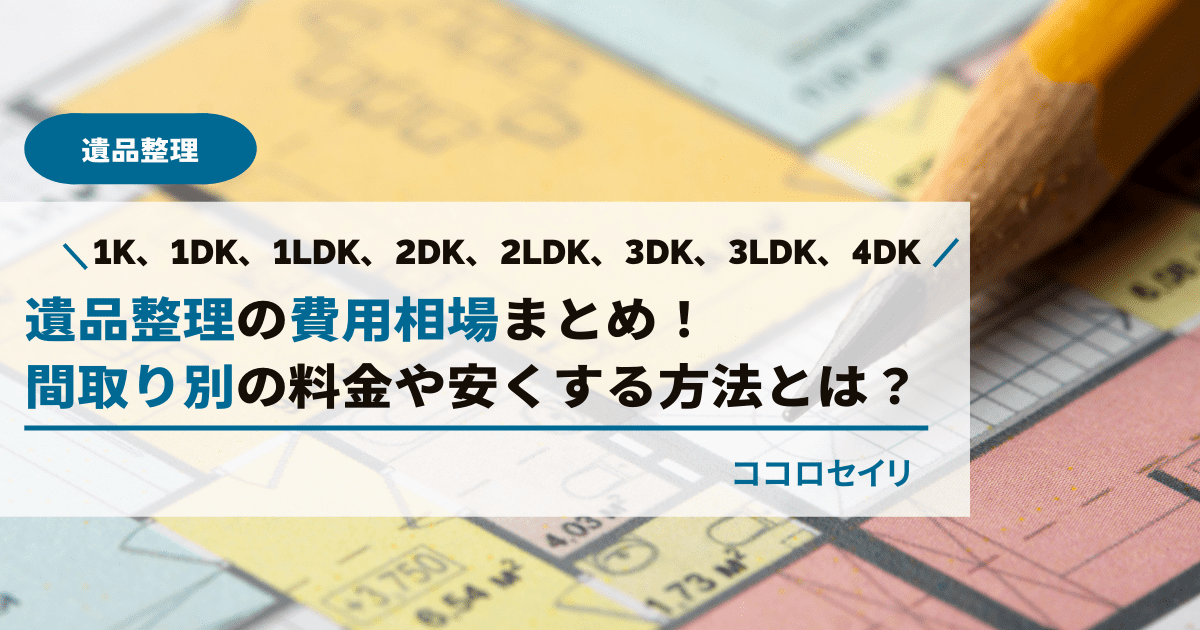大切な家族を見送った後、遺品整理を進めなければならない場面が訪れます。しかし、「どこから手をつければいいのか分からない」「何を捨ててよくて、何を残すべきなのか迷う」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
特に、「捨ててはいけないもの」を知らずに処分してしまうと、後から取り返しのつかないトラブルにつながることもあります。遺産相続に関わる重要な書類や、故人の大切な思い出が詰まった品物は、慎重に判断する必要があります。
この記事では、「遺品整理で捨ててはいけないもの」を分かりやすくリストアップし、法律・手続き・トラブル防止の観点から、後悔しない整理のコツを解説します。
「間違って捨ててしまわないか心配」「家族と意見が食い違って困っている」と悩んでいる方が、安心して遺品整理を進められるよう、わかりやすくお伝えしていきます。どうぞ最後までご覧ください。
また、『ココロセイリ』では、相続に関わる貴重品の仕分けや、供養が必要な品の取り扱い、不要品の適切な処分までサポートしています。 遺品整理に関する不安を解消し、ご遺族の負担を軽減するためのお手伝いをしていますので、安心してご相談ください。
豊富な実績を持つ遺品整理の専門店「株式会社ココロセイリ」の代表取締役社長
目次
遺品整理で捨ててはいけないもの一覧
遺品整理を進める際、故人の思い出や大切な品々を整理していくことになります。しかし、一度捨ててしまうと取り返しがつかないものも少なくありません。特に、重要な書類や貴重品は、後々の手続きや相続に関わるため、慎重に判断することが求められます。
遺品整理で捨ててはいけないものは、主に以下の3つのカテゴリーに分けられます。
法的な理由で捨ててはいけないもの
- 遺言書
- 現金
- 有価証券・保険証券
手続き上の理由で捨ててはいけないもの
- 通帳・キャッシュカード
- 印鑑・印鑑登録証
- 身分証明書・年金手帳・健康保険証・マイナンバーカード・パスポート
- ローンの明細
- 請求書・支払通知書
- 故人の仕事関係の資料
- 土地の権利書
- 賃貸契約書・光熱費の請求書・クレジットカードの明細
トラブル防止のために捨ててはいけないもの
- 遺書・エンディングノート
- 借りているもの(レンタル品・リース契約のもの)
- 鍵(自宅・貸金庫・車・貸倉庫など)
- 売却価値があるもの(貴金属・骨董品・ブランド品・コレクション)
- 思い出の品(写真・手紙・家族の記録)
- デジタル遺品(スマートフォン・パソコン・SNS・クラウドサービスのアカウント情報)
これらの品物を誤って処分してしまうと、遺産相続の手続きが滞ったり、親族間でのトラブルが発生する可能性があります。また、故人の大切な記録が失われ、思い出を振り返ることができなくなることもあります。
遺品整理を行う際は、焦らず、一つひとつ確認しながら進めることが大切です。 どの品物を残し、どの品物を処分すべきかを正しく判断するためにも、次の項目で詳しく解説していきます。
遺品整理で「法的な理由」から捨ててはいけないもの
法的な理由で捨ててはいけない遺品には、遺言書、現金、有価証券・保険証券があります。これらは相続手続きに直結するものであり、誤って処分すると法的なトラブルや手続きの遅延につながる可能性があるため、慎重に取り扱う必要があります。
遺言書
遺言書は、故人の意思を法的に証明する重要な文書です。遺産の分配方法や特定の相続人への指示が書かれているため、決して捨ててはいけません。遺言書の種類と保管場所は次の通りです。
遺言書には、以下の3つの種類があります。
- 公正証書遺言(公証役場に保管されている)
- 秘密証書遺言(公証役場で手続きされるが、本人が保管)
- 自筆証書遺言(個人の保管場所にあるが、法務局での保管制度も利用可能)
令和2年7月10日から始まった「自筆証書遺言書保管制度」を利用している場合、法務局に保管されている可能性もあります。遺言書を見つけた場合は、すぐに家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります。
また、相続手続きの途中で遺言書が見つかると、分配内容が変わる可能性があり、手続きをやり直すケースもあります。遺品整理を始める際は、最初に遺言書がないか確認しましょう。
現金
故人の遺品の中に現金が含まれている場合、それは相続財産にあたるため、勝手に処分することはできません。現金が見つかる可能性のある場所は次の通りです。
- 金庫やタンスの引き出し
- 本の間や洋服のポケット
- 靴の中や家具の裏
- 台所や冷蔵庫の中(封筒に入れて保管しているケース)
特に高齢者の場合、現金をへそくりとして思わぬ場所に隠していることも多いため、注意深く探すことが大切です。見つけた現金は相続人全員で確認し、相続のルールに従って適切に分配する必要があります。
また、金融機関の貸金庫に預けられているケースもあるため、銀行の取引履歴を確認し、該当する貸金庫がないか調べておくとよいでしょう。
有価証券・保険証券
有価証券や保険証券も相続財産に含まれるため、処分してはいけません。これらの書類がないと、相続手続きが大幅に遅れることになります。
有価証券とは?
- 株式(上場株・未上場株)
- 国債・社債
- 投資信託
故人が生前に株式や投資信託を所有していた場合、証券会社の口座を通じて管理されている可能性があります。証券会社からの取引明細や郵便物が残っていないかを確認しましょう。
保険証券とは?
- 生命保険証券
- 火災保険・自動車保険の証券
故人が生命保険に加入していた場合、受取人が保険金を請求できる可能性があります。ただし、保険証券がないと手続きがスムーズに進まないため、必ず確認が必要です。
また、火災保険や自動車保険の解約手続きをしないと、保険料が自動で引き落とされ続ける可能性もあるため、適切に手続きを行いましょう。
遺品整理で「手続き上の理由」から捨ててはいけないもの
遺品の中には、法的な理由ではなくても、相続手続きや各種届出のために保管が必要なものがあります。これらを捨ててしまうと、手続きに大きな支障が出ることもあるため、慎重に取り扱う必要があります。
故人の通帳やキャッシュカードは、口座凍結解除や相続手続きに必要となるため、必ず保管しておきましょう。
また、金融機関は、故人の死亡を把握した時点で口座を凍結します。そのため、預貯金を引き出すには、相続手続きを進める必要があります。具体的な手続きには、以下の書類が必要です。
- 故人の通帳・キャッシュカード
- 戸籍謄本
- 遺言書(ある場合)
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名・捺印が必要)
特に、キャッシュカードや通帳は、故人の財産状況を把握するためにも役立ちます。銀行ごとに手続きの方法が異なるため、事前に確認しておくとスムーズです。
印鑑・印鑑登録証
印鑑(特に実印)は、各種手続きで必要となるため捨ててはいけません。また、印鑑登録証(印鑑カード)も役所での手続き時に求められることがあるため、合わせて保管しておきましょう。印鑑の重要性は次の通りです。
- 相続手続きの際に使用(特に不動産の名義変更や銀行口座の解約手続き)
- 会社を経営していた場合、法人印も必要になる可能性
印鑑は小さいため、誤って捨ててしまうリスクが高いです。故人のスーツのポケットや書類ケースなどをしっかり確認しましょう。
身分証明書・年金手帳・健康保険証・マイナンバーカード・パスポート
故人の身分証明書や公的書類は、役所での各種手続きで必要になります。手続きに必要な主な書類は次の通りです。
- 健康保険証・マイナンバーカード:死亡届提出後に返却が必要
- 運転免許証:警察署または免許センターで返納手続きが必要
- 年金手帳・年金証書:年金受給停止手続きに必須
- パスポート:市区町村の窓口で失効手続きを行う
これらの書類は、死亡後の手続きが完了すれば不要になりますが、返却が必要なものがあるため勝手に処分しないように注意しましょう。
ローンの明細
故人が住宅ローンやカードローン、クレジットの分割払いを利用していた場合、それらの明細は重要な資料となります。相続放棄の判断に影響するものは次の通りです。
- ローン残債が多い場合、相続放棄を検討する必要がある
- 相続放棄の期限は「相続発生から3か月以内」
遺産だけでなく負債も相続対象となるため、故人が借金をしていたかどうかを判断するためにも、ローンの明細や契約書は必ず保管し、専門家に相談することをおすすめします。
請求書・支払通知書
故人の光熱費や電話代、クレジットカードの請求書などの支払い明細も、すぐに捨ててはいけません。確認が必要な主な費用は次の通りです。
- 光熱費・家賃の未払い(相続人が支払いを引き継ぐ可能性あり)
- クレジットカードの利用履歴(未払い残高の確認)
- サブスクリプションの解約手続き(Netflix、Amazon Primeなど)
特に、定期的に支払いが発生するサービスは、解約しないと利用料金が発生し続ける可能性があるため、すべての請求書を確認したうえで適切に対応しましょう。
故人の仕事関係の資料
故人が生前に会社勤めをしていた場合、または自営業を営んでいた場合、仕事に関する資料が出てくることがあります。捨てずに確認すべきものは次の通りです。
- 勤務先から貸与されていた書類・備品(会社に返却が必要)
- 取引先との契約書・請求書(業務上のトラブルを避けるため)
- 会社経営者の場合、会社実印や法人登記書類
万が一、捨ててしまうと未払い請求や契約問題が発生するリスクがあるため、一度関係者に確認するのが無難です。
土地の権利書
土地や不動産を所有していた場合、「権利書(登記済権利証)」は相続手続きに不可欠です。権利書がないと次のようになります。
- 不動産の名義変更ができない(相続登記に必要)
- 売却・貸出の手続きが進められない
土地の権利書が見当たらない場合、司法書士に相談すれば「登記情報」を取得できるため、焦らず対応しましょう。
賃貸契約書・光熱費の請求書・クレジットカードの明細
故人が賃貸物件に住んでいた場合、契約解除手続きのために賃貸契約書が必要になります。
- 家賃保証会社との契約確認(敷金の返還手続きなど)
- 解約時の条件を確認(違約金の有無、解約期限など)
また、光熱費やクレジットカードの支払いが残っている場合、契約解除を忘れると引き落としが続くため、各会社に連絡して対応しましょう。
遺品整理で「トラブル防止の理由」から捨ててはいけないもの
遺品整理を進める中で、思いがけずトラブルの原因となるものがあります。誤って処分してしまうと、親族同士の対立や業者との契約トラブルに発展する可能性があるため、注意が必要です。ここでは、特に気をつけるべき6つの遺品について詳しく解説します。
遺書・エンディングノート
遺言書とは異なり、法的な効力はありませんが、故人の想いが記された大切なものです。遺書・エンディングノートの主な内容は次のようになることが多いです。
- 遺品の扱い方に関する希望
- 供養の方法(お墓や納骨に関する指示)
- 家族や友人へのメッセージ
- 介護や延命治療に関する意思表示
- 金融機関や重要な契約情報
近年は、紙のノートだけでなくデジタル形式(音声・動画)で残すケースも増えています。スマートフォンやパソコンのデータの中に保管されている可能性もあるため、慎重に確認しましょう。
借りているもの
故人の遺品の中には、業者からレンタル・リースしている物品が含まれていることがあります。これらを誤って処分すると、違約金の請求やトラブルの原因となるため、注意が必要です。よくあるレンタル・リース品は次の通りです。
- Wi-Fiルーター
- ウォーターサーバー
- 医療機器(酸素吸入器・介護用ベッドなど)
- 車(リース契約)
- サブスクリプションサービス(衣類・家電など)
契約情報は、請求書や登録メールを確認することで把握できます。契約が残っている場合は、提供元に連絡して適切な返却手続きを行いましょう。
鍵
鍵がどこかに使われている可能性があるため、どんな鍵でも処分せずに保管しましょう。鍵が使われている可能性がある場所は次の通りです。
- 金庫
- 自宅・別荘・貸倉庫
- 車やバイク
- ロッカーや机の引き出し
金庫の鍵を捨ててしまうと、開錠のために専門業者に依頼する必要があり、高額な費用がかかることもあります。見つかった鍵は、どこで使われているものなのか慎重に確認しましょう。
売却価値があるもの
遺品の中には、一見価値がなさそうに見えても、高額で売却できるものが含まれていることがあります。誤って捨ててしまう前に、専門家に査定を依頼するのが賢明です。売却価値がある可能性が高いものは次の通りです。
- 貴金属(指輪・ネックレス・金貨)
- 骨董品(掛け軸・陶磁器・古書)
- ブランド品(バッグ・時計)
- 昔の切手やコイン
- 古いおもちゃやレトログッズ
特に骨董品や古いグッズは、素人では価値を判断しにくいため、リサイクルショップや専門業者に査定してもらうとよいでしょう。
思い出の品
遺品整理では、写真や手紙などの「思い出の品」の扱いが難しいものです。家族によっては、故人との大切な思い出が詰まった品を処分することに抵抗があることも少なくありません。思い出の品の具体例は次の通りです。
- 写真アルバム
- 手紙や日記
- 故人が愛用していた品(時計・メガネなど)
- 子どもの頃の作品(絵や作文)
処分するかどうか迷った場合は、家族と話し合って決めるのがベストです。また、思い出の品を捨てるのに抵抗がある場合は、写真をデータ化したり、供養してもらう方法もあります。
デジタル遺品
現代では、デジタルデータの中に故人の大切な情報が残されていることが多く、これを適切に管理しないと、トラブルの原因になります。デジタル遺品の例は次の通りです。
- スマートフォン・パソコンのデータ
- クラウドストレージ(Google Drive、Dropboxなど)
- SNSアカウント(Facebook、Instagram、X(旧Twitter))
- ネット銀行・仮想通貨の口座
- オンライン契約サービス
デジタル遺品は、ログイン情報が分からないとアクセスできず、管理が困難になることがあります。そのため、遺品整理の際はパスワードのメモやアカウント情報の有無を確認することが重要です。
また、SNSアカウントを放置すると、故人の情報がインターネット上に残り続けるため、削除または追悼アカウントへの変更を検討することも必要です。
供養が必要な遺品(仏壇・位牌・遺影・お守りなど)
遺品整理を進める中で、仏壇や位牌、遺影、お守りなどの供養が必要な品が出てくることがあります。これらは故人や先祖の魂が宿っているとされ、一般的なゴミと同じように処分するのは避けるべきです。正しい方法で供養し、感謝の気持ちを込めて整理しましょう。
仏壇・位牌
仏壇や位牌は、仏教において故人や先祖の魂が宿るものとされています。そのため、そのまま処分するのは適切ではなく、供養を行ったうえで適切に整理することが大切です。仏壇や位牌を処分する方法ついては次の通りです。
菩提寺(お世話になっているお寺)に相談する
- 位牌や仏壇を引き取ってもらえることが多い
- 「魂抜き(閉眼供養)」を行い、供養してから処分する
仏壇・位牌供養を専門とする業者に依頼する
- 供養証明書を発行してくれる業者もあり、安心して任せられる
- 仏壇の大きさによっては、出張供養を依頼できる
寺院や霊園の「合同供養」に参加する
- 全国の寺院で「仏壇・位牌供養」を実施していることがある
- 合同供養の後、適切な方法で処分される
仏壇を処分する際は、仏具や経本などの付属品も一緒に供養してもらうことを忘れないようにしましょう。
遺影(写真)
遺影は、故人の存在を感じられる大切な品です。特に、四十九日や一周忌までは飾っておくのが一般的ですが、その後の扱いに悩む人も多いです。遺影の供養・処分方法は次の通りです。
- お焚き上げ供養を依頼する(寺院や専門業者に依頼)
- 写真を小さく切り、塩で清めてから処分する(宗派によって異なるが、一般的な方法)
- データ化して保存し、写真自体は処分する(デジタル保存を活用)
遺影は家族にとっても思い入れの深いものなので、家族で相談し、納得できる形で整理することが大切です。
お守り・御札
故人が生前に大切にしていたお守りや御札は、単なる物ではなく、信仰心や祈りの気持ちが込められているものです。そのため、一般ごみとして処分するのではなく、適切な方法で供養することが望ましいです。お守り・御札の供養方法は次の通りです。
- 購入した神社・お寺に返納する(多くの寺社では「古札納所」がある)
- お焚き上げ供養を依頼する(全国の神社や寺院で受付)
- 郵送で供養を受け付けている寺社を利用する(遠方でも可能)
特に、お守りや御札には「1年間のご加護」という考え方があるため、毎年、神社やお寺に返納し、新しいものに替えるのが習慣とされています。
数珠・経本・仏具
故人が使っていた数珠や経本、仏具も、魂が宿るものとして大切に扱うべきです。処分する際のポイントは次の通りです。
- 数珠はお焚き上げ供養をしてもらうのが一般的
- 経本(お経の本)は仏壇供養の際にまとめて依頼できる
- 仏具は「仏壇供養」と合わせて整理するとスムーズ
数珠や仏具の処分に困ったら、仏壇店や仏具専門店に相談すると、適切な供養方法を案内してもらえることが多いです。
その他の供養が必要な品
遺品整理を進める中で、供養が必要なものが他にも見つかることがあります。例えば、以下のようなものです。
- 戒名の入った品(掛け軸・位牌以外の記念品など)
- 神棚や仏壇周りの装飾品
- 信仰に関する遺品(キリスト教の十字架や聖書など)
これらの品も、通常の廃棄物とは異なり、供養をしてから整理することが望ましいです。
捨ててはいけない遺品を処分したときに起こること
遺品整理を進める中で、「不要だろう」と思って処分したものが、後々大きな問題を引き起こすことがあります。特に、法的に重要な書類や、家族との関係に影響するものを誤って捨ててしまうと、トラブルや損害につながる可能性があります。ここでは、捨ててはいけない遺品を誤って処分した際に起こり得る問題について詳しく解説します。
親族同士でのトラブルになる
遺品整理を進める際、親族間の意見の食い違いは少なくありません。ある人にとっては価値がないと思えるものでも、別の人にとっては大切な思い出の品であることもあります。
例えば、故人が大切にしていた手紙や写真、愛用品を処分してしまった場合、「勝手に捨てられた」と感じた親族が不満を抱き、感情的な対立に発展するケースもあります。
また、故人の財産に関わる遺言書や通帳、土地の権利書などの重要書類を処分してしまうと、「相続の話し合いに必要だった」として、親族間の関係が悪化することも少なくありません。
損害賠償につながる
故人が契約していたレンタル品やリース品、会社から貸与されていた物品を誤って捨ててしまうと、契約違反となり、損害賠償を請求される可能性があります。
例えば、故人が使用していたWi-Fiルーター、ウォーターサーバー、介護用ベッド、リース契約の車などは、契約元に返却しなければなりません。
また、故人が勤務していた会社から貸し出されていたノートパソコンや業務用の資料、制服などを処分すると、会社から返還を求められたり、損害賠償を請求されたりするケースもあります。
中身を確認できなくなるリスクがある
鍵のかかった金庫や引き出し、USBメモリ、古いパソコンなどを処分してしまうと、大切なデータや財産の情報を永久に失ってしまう可能性があります。
例えば、金庫の中には通帳や権利書、貴重品が入っていることが多いですが、開けることができないまま処分してしまうと、故人の財産の一部が分からなくなり、相続手続きに影響が出る可能性があります。
また、USBメモリやパソコンのデータには、故人の金融資産の管理情報、デジタル遺品(仮想通貨のウォレット情報、ネット銀行のアカウント情報)が含まれていることもあります。これらを処分してしまうと、相続できるはずの財産を失うリスクが高まります。
引継ぎができなくなる
故人が管理していた重要な情報や契約を確認せずに遺品を処分すると、相続人や家族が必要な手続きを行えなくなることがあります。引継ぎができなくなる主な例は次の通りです。
- 銀行口座・クレジットカードの解約ができない
- 賃貸契約が残ったままになり、不要な家賃が発生する
- 電気・水道・ガスなどのライフラインが継続され、無駄な費用が発生する
- SNSアカウントが放置され、第三者に乗っ取られるリスクがある
特に、クレジットカードの解約ができないと、年会費や未払いの請求が続いてしまい、不要な出費が発生することがあります。また、家賃の自動引き落としが続くことで、余分な費用が発生し、相続財産が目減りする可能性もあります。
捨ててはいけない遺品を守る方法とは
遺品整理を進める中で、何を残し、何を処分すべきか迷うことはよくあります。特に、捨ててはいけない遺品を誤って処分してしまうと、相続トラブルや手続き上の問題が発生する可能性があります。遺品を適切に整理し、後悔のない形で進めるためには、事前の準備や慎重な対応が欠かせません。ここでは、捨ててはいけない遺品を守るための具体的な方法を解説します。
生前に親族で処分するものを話し合っておく
遺品整理でトラブルを防ぐためには、生前のうちに親族で話し合い、どの遺品を残すか決めておくことが重要です。話し合いで決めておくべきポイントは次の通りです。
- 貴重品や財産に関するもの(遺言書・通帳・土地の権利書など)
- 思い出の品(写真・手紙・愛用品など)をどうするか
- 供養が必要なもの(仏壇・位牌・お守りなど)の扱い
- リース品・レンタル品など契約があるものの整理方法
生前に話し合うことで、親族間で意見が食い違うことを防ぎ、スムーズな遺品整理が可能になります。また、事前にリストを作成しておくと、整理の際に迷うことが少なくなります。
遺書に従って整理していく
故人が遺書を残している場合、そこには「誰に何を相続させるのか」「どのように遺品を処分するのか」が記されていることがあります。遺書の確認方法は次の通りです。
- 自筆証書遺言 → 家庭裁判所での検認が必要
- 公正証書遺言 → 公証役場に保管されている
- エンディングノート → 法的効力はないが、故人の希望が記載されている
遺書が見つかった場合は、すぐに開封せず、法律に従って適切に処理することが大切です。特に、公正証書遺言がある場合は、弁護士や司法書士に相談しながら進めると安心です。
判断に迷うものはひとまず保留する
遺品整理を進めていると、「捨てていいのかわからない」「価値があるか判断できない」と迷うことがあります。そのような場合は、すぐに処分せず、一旦保留することが重要です。一時保管しておくべき遺品の例は次の通りです。
- 価値があるか不明な骨董品・貴金属(専門家に査定してもらう)
- 相続に関係しそうな書類や契約書(弁護士に相談)
- デジタル遺品(スマホ・パソコン)(中身を確認してから処分)
「迷ったら捨てない」が基本です。一度処分すると元に戻せないため、家族や専門家と相談しながら慎重に判断しましょう。
写真などはできる限りデータに残す
故人の思い出が詰まった写真や手紙などは、データ化することで、整理しながらも大切な記録として残すことが可能です。写真や思い出の品をデータ化する方法は次の通りです。
- スキャナーやスマホアプリを使ってデジタル保存する
- クラウドストレージ(Google Drive、Dropbox)に保存して共有する
- DVDやUSBメモリにバックアップを取る
遺品整理を進める中で、家族の思い出を形に残すことは大切です。写真をデータ化することで、物理的な整理がしやすくなり、親族間で共有しやすくなるというメリットもあります。
相続トラブルを避けるために専門家(弁護士・行政書士)に相談する
遺品整理では、相続の手続きや財産の分配でトラブルが発生することが少なくありません。特に、以下のようなケースでは、専門家に相談するのが安心です。専門家に相談すべきケースは次の通りです。
- 相続人同士で意見が対立している
- 遺産の分け方が不明確(遺言書がない・不動産が絡む)
- 借金や未払い金があるか分からない
弁護士や行政書士に相談することで、法的に正しい方法で遺品整理を進めることができ、後々のトラブルを回避できます。無料相談を行っている専門家もいるため、早めに相談すると良いでしょう。
遺品整理の優先順位を決めて進める(貴重品・思い出の品・処分品)
遺品整理は、一度にすべてを片付けようとすると大変な作業になります。そのため、優先順位を決めて整理を進めることが大切です。遺品整理の優先順位は次の通りです。
- 貴重品(遺言書・通帳・保険証券・土地の権利書など)
- 思い出の品(写真・手紙・故人の愛用品)
- 処分品(不要な衣類・家具・家電など)
この順番で整理を進めることで、大切なものを守りながら、スムーズに作業を進めることができます。
遺品整理業者にアドバイスをもらう
「自分たちだけで整理するのが難しい」「どこから手をつければいいかわからない」という場合は、遺品整理業者に相談するのも一つの方法です。遺品整理業者を利用するメリットは次の通りです。
- 不用品の処分から供養まで一括対応してくれる
- 貴重品の仕分けを手伝ってくれる
- 相続手続きに詳しい専門家と提携している業者もある
特に、高齢の親族だけで作業するのが難しい場合や、遠方に住んでいる場合は、業者のサポートを活用することでスムーズに進めることが可能です。
まとめ
遺品整理は、単なる片付けではなく、故人の思いを大切にしながら整理を進める大切な作業です。特に、法的な書類や貴重品、思い出の品などを誤って処分してしまうと、相続トラブルや手続きの遅延、思いがけない損害につながる可能性があります。
また、遺品整理を進める際には、親族との話し合いを大切にし、判断に迷うものはすぐに捨てず、保管や専門家への相談を検討することが重要です。
「どこから手をつければいいかわからない」「大切なものを誤って捨てたくない」と不安に感じる場合は、無理をせず、専門の遺品整理業者や弁護士・行政書士などの専門家に相談するのも一つの方法です。
また、遺品整理に不安を感じたら「ココロセイリ」にご相談ください
遺品整理は、精神的にも体力的にも負担が大きいものです。一人で抱え込まず、信頼できる専門家のサポートを受けながら進めることが、後悔のない遺品整理につながります。
「何を残して、何を処分すればいいのかわからない」
「相続手続きや供養の方法について詳しく知りたい」
「親族と意見が食い違ってしまい、整理が進まない」
このような悩みを抱えている方は、ぜひココロセイリにご相談ください。私たちは、ご遺族の気持ちに寄り添いながら、適切な遺品整理をサポートいたします。遺品の整理方法や供養、相続に関するアドバイスも行っておりますので、安心してご相談ください。
「大切な人の想いを大切にしながら、丁寧に整理を進めたい」 ー そんな方のために、私たちがサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。
豊富な実績を持つ遺品整理の専門店「株式会社ココロセイリ」の代表取締役社長