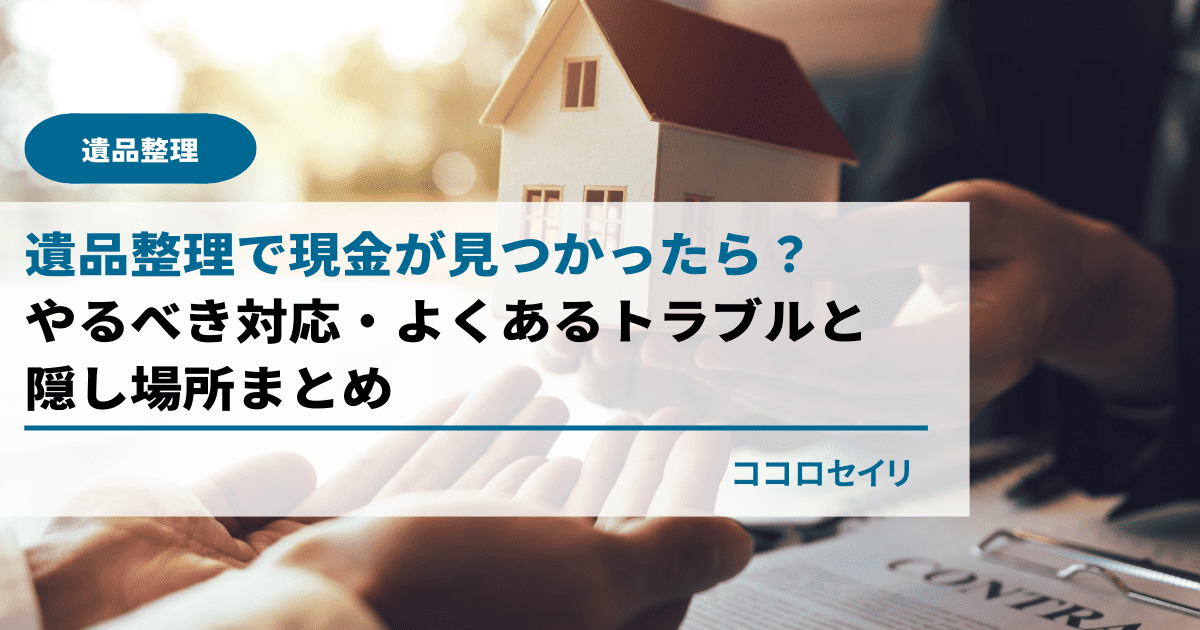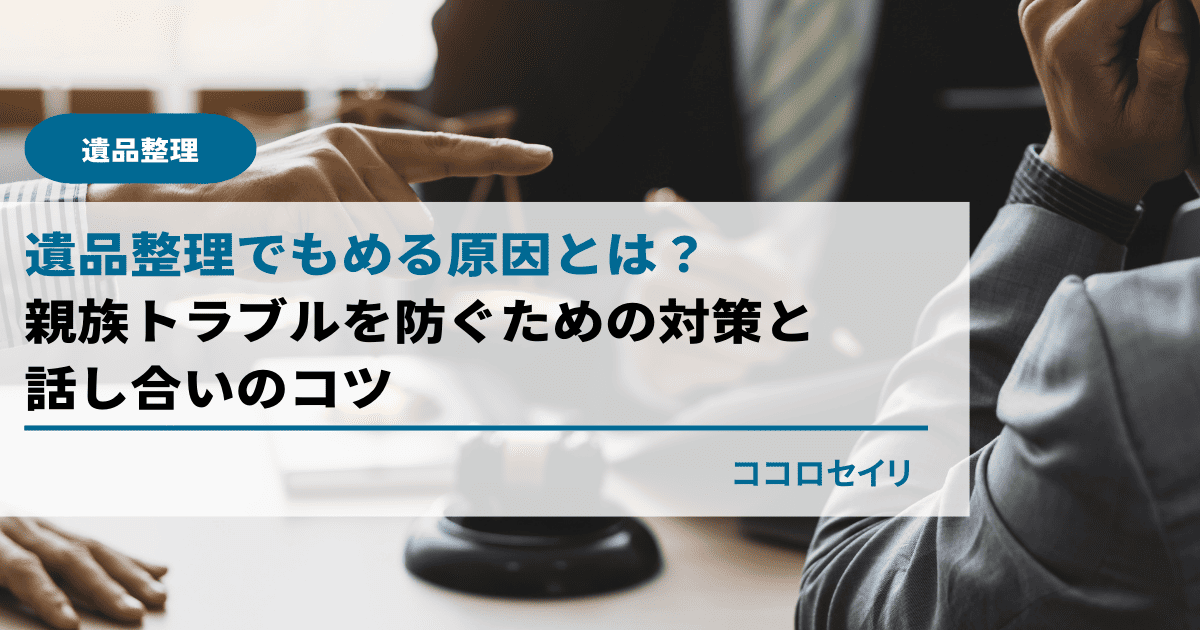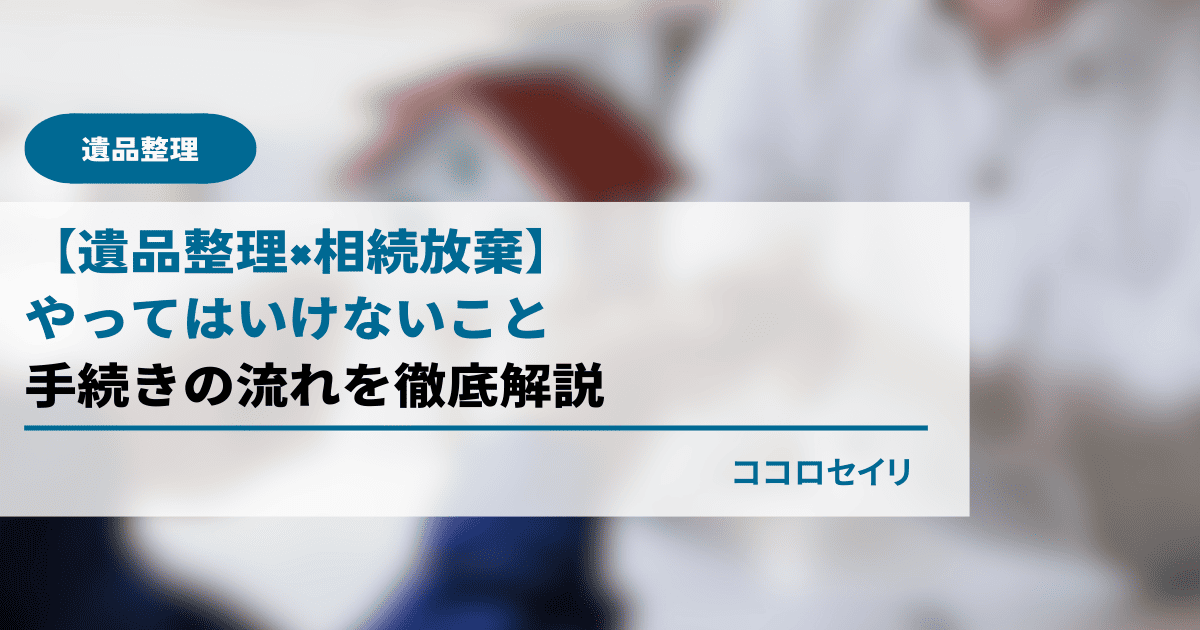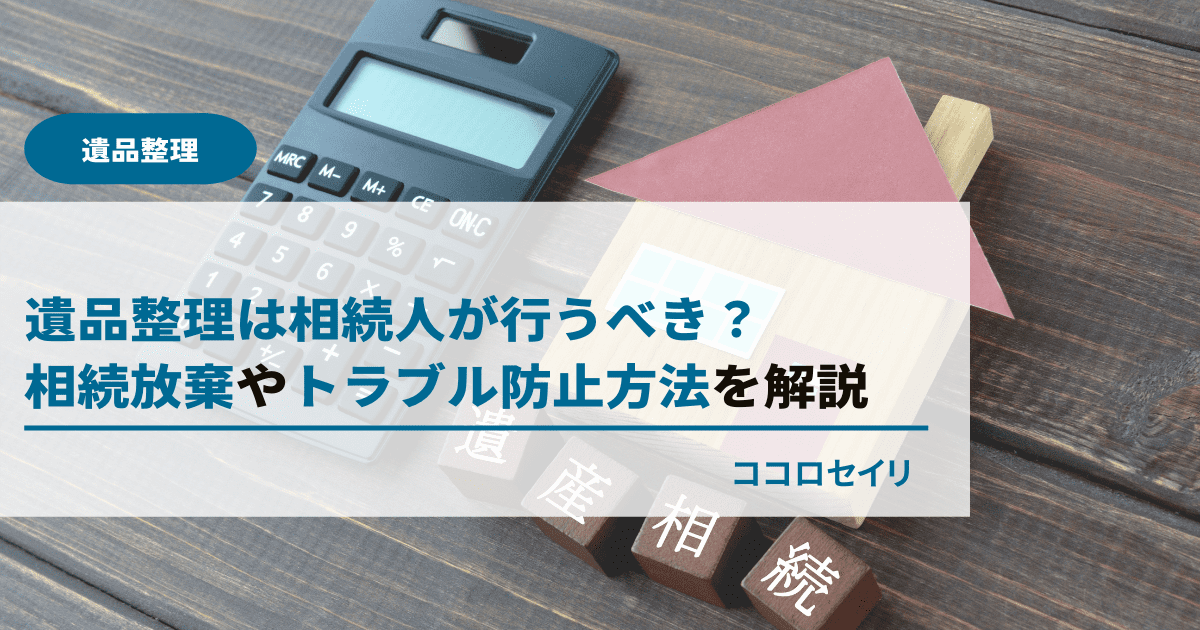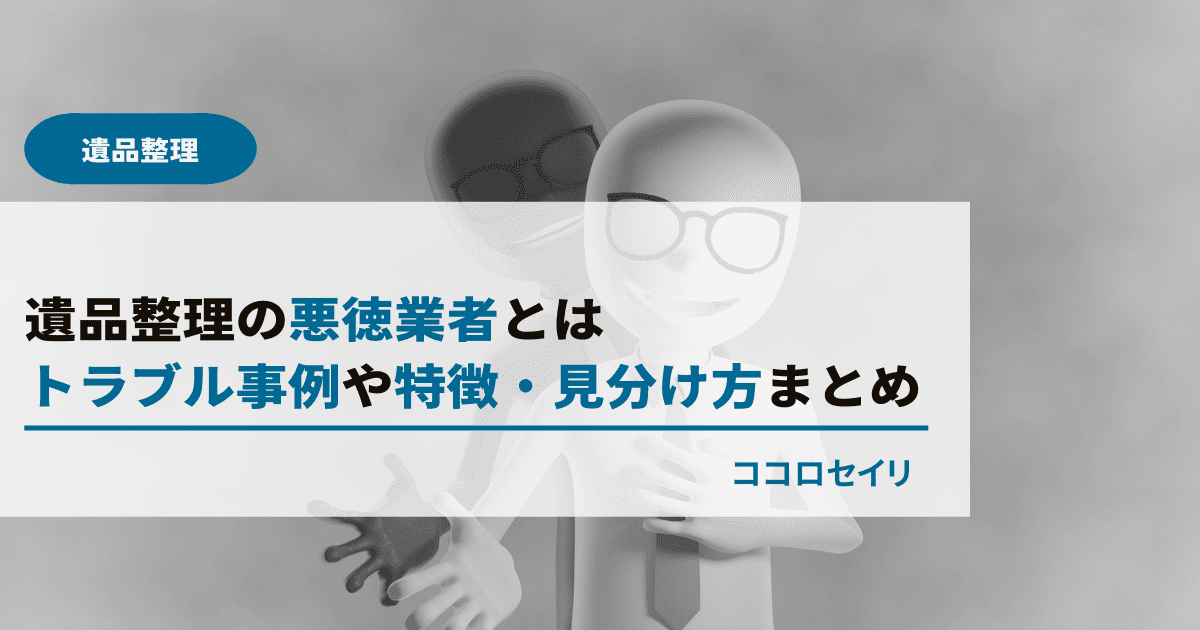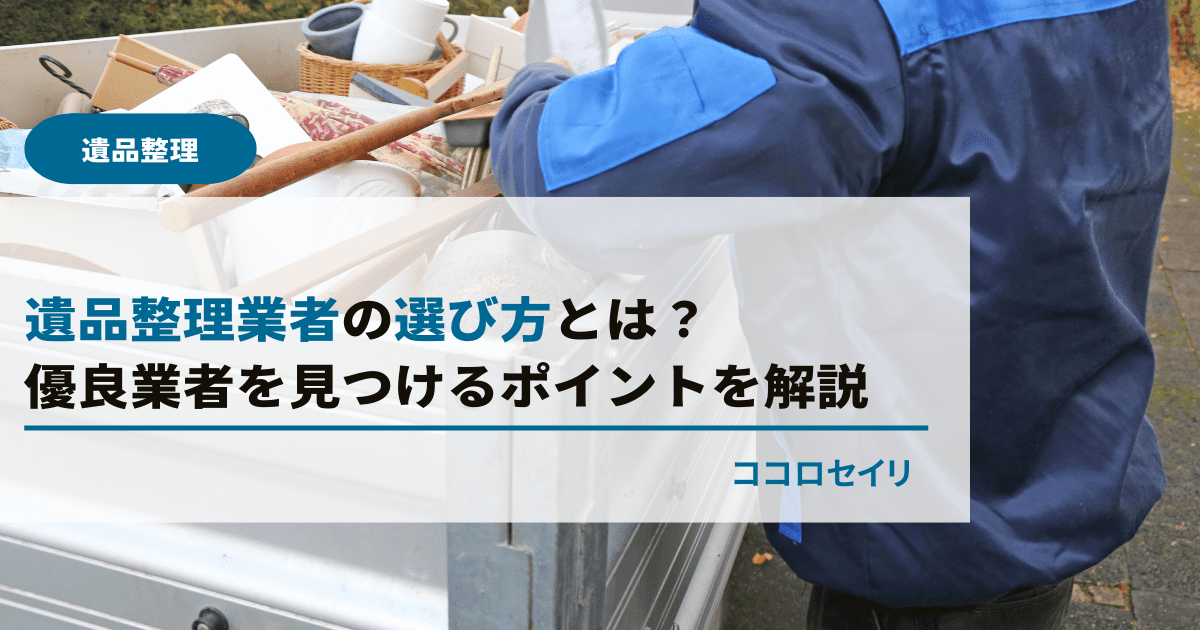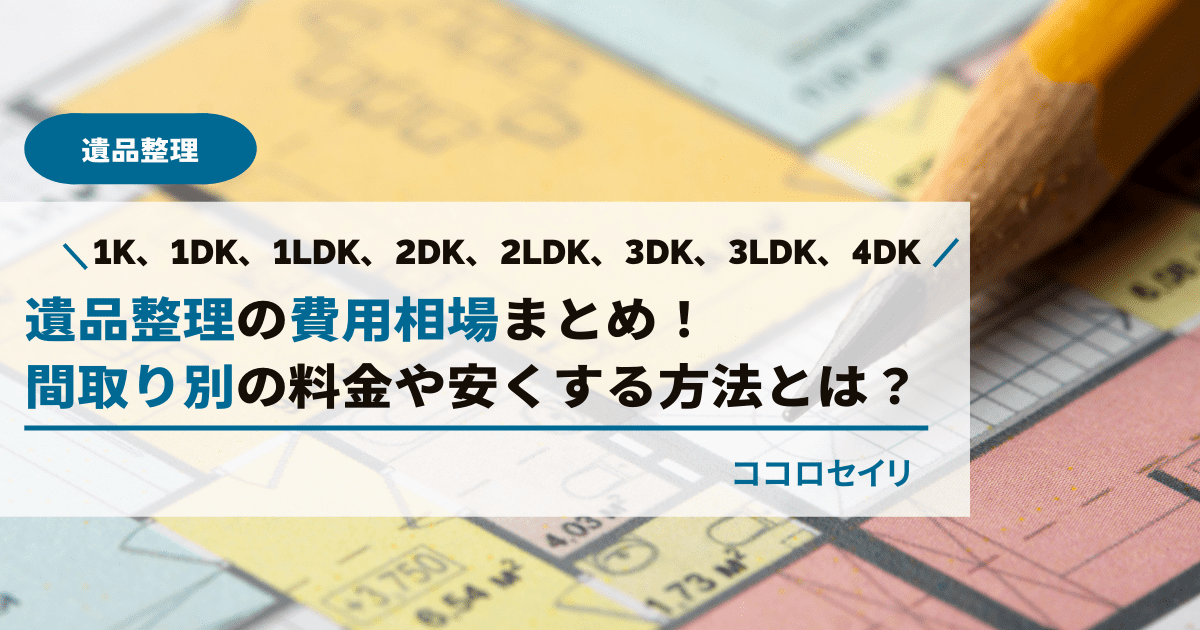大切なご家族を見送った後、遺品整理を進めていると──
「タンスの奥から封筒に入った現金が…」
「まさかと思っていたけど、冷蔵庫の隙間にお札が…」
こうしたケースは、決して珍しくありません。
実際に、現金主義だった高齢のご家族が「タンス預金」や「へそくり」を残していたことに気づくのは、遺品整理のタイミングであることが多いのです。
けれど、ふと出てきた現金をどう扱えばいいのか分からず、
「親族で揉めないか不安…」
「税金の申告って必要なの?」と戸惑う方も少なくありません。
この記事では、遺品整理で現金が見つかる理由から、見つけたときの正しい対応方法、ありがちなトラブルとその防止策までをわかりやすく解説します。
これから遺品整理を始める方も、すでに作業中の方も――
現金が出てきたときに、慌てず冷静に対処するための知識として、ぜひ最後までご覧ください。
豊富な実績を持つ遺品整理の専門店「株式会社ココロセイリ」の代表取締役社長
目次
遺品整理で現金が見つかるのは珍しくない
遺品整理をしていると、思いがけず現金が出てくることがあります。
「封筒に入った1万円札がタンスの奥から」「仏壇の引き出しに数十万円」など、驚くようなケースも少なくありません。
実際、遺品整理業者の現場では現金や通帳、貴金属の発見は日常茶飯事。とくに高齢の方が暮らしていた家では、その傾向が強いとされています。
なぜ現金が遺品の中から見つかるのか?
現金が遺品の中に紛れているのには、いくつかの理由があります。
- 「もしものとき」の備えとして現金を手元に置いていた
- 銀行口座を家族に知られたくなかった
- 自分の亡き後に家族の助けになるように…という思いから隠していた
こうした意図があったとしても、保管場所を家族に伝えないまま亡くなってしまうことが多く、遺品整理の際に“偶然”見つかるという流れになりやすいのです。
高齢者に多い「現金主義」「タンス預金」の実態
高齢世代の中には、銀行やカードよりも「現金で手元管理するほうが安心」と考える方が多くいます。
実際に、日本国内には数十兆円規模の“タンス預金”が存在するとも言われており、その大半は高齢者によるものだとされています。
「ATMの操作に不安がある」「手数料がもったいない」「通帳を他人に見られたくない」などの理由で、日常的に現金を自宅で管理する習慣がある方も少なくありません。
遺族でも把握していない“隠し場所”がある理由
へそくりやタンス預金は、家族にも言わずに隠されていることが多く、遺族にとっては完全な「未知の財産」になっているケースがほとんどです。
特に一人暮らしの方や、家計を完全に任されていたような場合は、
「現金が隠されている場所を知っていたのは本人だけ」というケースもあります。
そのため、タンスの奥や仏壇の引き出し、衣類のポケット、冷蔵庫の隙間など、“まさか”と思うような場所から現金が見つかることも珍しくありません。
現金が見つかりやすい場所10選
遺品整理を行う際に「どこを重点的に探せばいいか」が分かっているだけでも、現金や貴重品の見落としを防ぐことができます。
ここでは、実際の遺品整理現場で現金が見つかりやすい“10の場所”を紹介します。
1. タンスやクローゼットの奥・衣類のポケット
定番中の定番とも言えるのがタンスの引き出しや衣類のポケット。
封筒や小さな箱に入れた現金を衣類と一緒にしまっていたり、ジャケットやコートのポケットからお札が出てくることも珍しくありません。
使用頻度の低い衣類ほど、要チェックです。
2. 仏壇・神棚・お守り入れ
「神様やご先祖様が守ってくれる」という思いから、仏壇や神棚の引き出しに現金や貴重品を保管していたという高齢者は少なくありません。
お守り袋の中に数万円が入っていた、というケースも。
3. キッチンの引き出し・床下収納
キッチンは意外と“隠し場所”が多い空間です。
引き出しの奥や、普段開けない床下収納、米びつの中などに現金をしまっていたという例もあります。
料理道具や保存容器の中も、念のため確認しましょう。
4. 本の間・書類ファイルの中
現金を本に挟んで隠していた、あるいは重要な書類と一緒に保管していたという方も。
古い本やファイルをまとめて処分する前に、1冊ずつめくって中身を確認することが大切です。
5. バッグや財布、化粧ポーチ
生前使っていたバッグやポーチ、小銭入れなどにも現金が残っていることがあります。
お札や硬貨だけでなく、商品券や切手が出てくるケースもあるので、細かくチェックしましょう。
6. 押し入れや布団の下
押し入れにしまった布団や座布団の下、布団の間などから封筒に入ったお札が見つかることも。
「常に自分のそばにある場所」として就寝スペース周辺に現金を隠す人も多い傾向にあります。
7. 靴箱・工具箱・空き箱類
靴箱や空き箱、工具箱などに「とりあえずしまっておいた」現金がそのまま残っていることもあります。
缶や箱の中は、開けて中を確認してから処分しましょう。
8. 冷蔵庫の中や裏
「人目につかない場所」として冷蔵庫の隙間や、冷蔵庫の裏側に現金を隠していた事例もあります。
冷蔵庫の中の保存容器や封筒、製氷皿の下など、思わぬところからお金が出てくることも
9. 非常持ち出し袋や防災用品
防災意識が高い方ほど、非常用袋の中に現金や通帳、印鑑を入れておく習慣があります。
袋の中身は必ずすべて取り出して確認しましょう。
10. 畳の下・屋根裏・壁の裏など意外な場所
まさかの“隠し財産”が出てくるのが、畳の下や壁の裏、屋根裏などの人目につきにくい場所。
家の解体作業中に数百万円の現金が見つかったという事例も実在します。
こうした場所は、最後のチェックポイントとして慎重に探すと良いでしょう。
遺品整理中に現金が見つかったらやるべきこと
遺品整理の最中に現金が見つかると、驚きや戸惑いからつい慌ててしまいがちです。しかし、現金も法的には「遺産」として扱われる財産であるため、適切な対応をとらなければ思わぬトラブルにつながる可能性もあります。
ここでは、現金が出てきたときにすぐにやるべきことを順を追って解説します。
相続人全員に報告する
見つけた現金は、まず相続人全員に正直に報告することが最優先です。
「少額だから…」と黙ってしまうと、後にトラブルの火種になることも。
金額の大小にかかわらず、公平性と信頼関係を保つために報告は必須です。
特に、現金の存在が後から発覚した場合には、「隠していたのでは?」と不信感を抱かれる原因にもなります。
財産目録に記載して記録を残す
見つけた現金は「財産目録」に正確に記載しましょう。
財産目録とは、遺産の内容と金額を一覧でまとめた記録表です。
相続税の計算や、後の遺産分割協議にも使われる重要な書類です。
現金の保管場所、金額、封筒の有無などもメモしておくと後々の確認がスムーズです。
勝手に使わず「遺産分割協議」で決定する
現金が見つかっても、勝手に使ったり、特定の人だけで分け合ったりするのは厳禁です。
相続人全員で「遺産分割協議」を行い、分配方法について話し合い、全員の合意をもとに分けることが法的に必要です。
なお、遺言書がある場合は基本的にその内容に従いますが、遺言に明記されていない現金が見つかった場合は、相続人同士での協議が求められます。
相続税の申告漏れに注意する
見つかった現金も「相続財産」として相続税の課税対象になります。
たとえ封筒に入った数万円であっても、他の遺産と合わせて基礎控除額(3,000万円+600万円×相続人の数)を超える場合は申告が必要です。
申告漏れが発覚すると、追徴課税(無申告加算税や延滞税)などのペナルティが課されることもあります。
税理士などの専門家に相談し、期限内(相続開始から10ヶ月以内)に正しく申告しましょう。
よくある現金トラブルと防止策
遺品整理の現場では、現金を巡るトラブルが意外と多く発生しています。
金銭が関わることで、これまで良好だった家族関係にヒビが入ってしまうことも珍しくありません。
ここでは、よくある3つの現金トラブルと、それを未然に防ぐための具体策をご紹介します。
1. 見逃して処分してしまう
衣類や書類に紛れていた現金を、不用品と一緒に誤って処分してしまうケースは非常に多く見られます。
「まさかこんな場所に?」と思うような場所から現金が出てくることもあるため、確認不足によるミスが起こりやすいのです。
特に注意が必要な例は以下の通りです。
- ポケットやバッグの内ポケット
- 本の間や封筒に紛れたお札
- 空き箱や古い家電の中
対策は以下の通りです。
- 一点ずつ中身を確認しながら作業する
- 「現金が出やすい場所」のチェックリストを活用する
2. 親族が黙って持ち帰ってしまう
手伝いに来た親族が、見つけた現金を黙って持ち帰ってしまうケースも報告されています。
悪意があるとは限らず、「少額だから」「他に誰も気づいていないから」といった軽い気持ちで起こることもありますが、立派な窃盗行為に該当する可能性があります。
このようなことが起こると、後に現金の存在が発覚した際に相続人同士の信頼関係が壊れてしまうことも。
対策は以下の通りです。
- 遺品整理は相続人全員が立ち会う
- 財産目録をその場で共有しながら進める
- 高額な遺産が出た場合は即座に共有・記録
3. 遺品整理業者による着服
まれにではありますが、遺品整理業者による現金や貴重品の持ち去りといったトラブルも報告されています。
依頼主が不在の状態で作業を任せていると、確認ができない間にこっそり持ち帰られてしまうこともあるのです。
対策は以下の通りです。
- 作業には可能な限り立ち会う
- 作業前に「現金が出た場合は必ず報告する」と事前確認
- 遺品整理士の有資格者がいる業者や、実績・口コミのある業者を選ぶ
トラブルを防ぐためにできること
現金トラブルを避けるために、遺品整理の前後で以下のポイントを意識しましょう。
- 事前に「現金が出てくる可能性がある」ことを全員で共有する
- 財産目録をその都度つける習慣をつける
- 信頼できる遺品整理業者を選ぶ
- 「遺言書」や「エンディングノート」があるかを確認する
- 整理作業中はできるだけ1人にならず、複数人で進める
現金が見つかったときこそ、焦らず冷静に、そして誠実に対応することが大切です。
小さな配慮が、大きなトラブルを防ぐカギになります。
相続や税金の観点から見る「現金」の取り扱い
遺品整理で現金が見つかった場合、「とりあえず保管しておこう」「少額だし問題ないだろう」と軽く考えてしまう方もいます。
しかし、相続や税金の観点から見ると、たとえ1円でも“遺産”として法的に扱われる財産です。
ここでは、現金に関する相続手続きの基本や注意点を解説します。
現金も遺産として法的な取り扱いが必要
遺品整理で発見された現金は、預貯金や不動産と同様に「遺産」に該当します。
相続の対象となる財産であり、勝手に使ったり分配したりすることはできません。
現金が見つかった場合は、まず以下の対応が必要です。
- 相続人全員への報告
- 財産目録への記載
- 遺産分割協議で分け方を決定
これらを適切に行わないと、後々の相続トラブルや税務上の問題につながる恐れがあります。
金額の大小にかかわらず、見つけた現金はきちんと共有・記録するようにしましょう。
相続税の基礎控除と申告の注意点
現金も他の遺産と同様に、相続税の課税対象になります。
ただし、相続税には「基礎控除」が設定されており、一定額を超えたときにのみ課税されます。
【相続税の基礎控除額の計算式】
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の人数
たとえば相続人が3人いる場合、
3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
これを超える遺産があると相続税の申告が必要になります。
相続税の申告には期限(相続開始から10ヶ月以内)があり、遅れるとペナルティ(加算税や延滞税)の対象になります。
現金をはじめとする相続財産は、見つけ次第できるだけ早く財産目録にまとめておくことが大切です。
相続放棄との関係に注意(現金を使うと放棄できない)
相続人が「借金などマイナスの遺産を引き継ぎたくない」と考えて相続放棄を選ぶケースもあります。
しかし、遺品整理で見つけた現金を使ってしまったり処分してしまった場合は注意が必要です。
民法上、相続人が遺産を処分・使用すると、「相続する意思がある」とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。
これは「単純承認」と呼ばれる扱いで、意図せず相続人としての義務(=借金の支払いなど)も発生してしまうリスクがあります。
対策は以下の通りです。
- 相続放棄を検討している場合は、現金を含む遺産に一切手を付けない
- 遺品整理の前に、弁護士や司法書士に相談しておく
- 「触れない・使わない・勝手に処分しない」が原則
安心して任せられる遺品整理業者の選び方
遺品整理は、作業の量や精神的な負担の大きさから、専門の業者に依頼する方が増えています。
しかし近年では、悪質な業者による現金や貴重品の持ち去りといったトラブルも報告されており、「誰に頼むか」が非常に重要です。
ここでは、遺品や現金を安心して任せられる業者を選ぶためのチェックポイントを解説します。
実績・資格・口コミで選ぶポイント
信頼できる業者かどうかを見極めるうえで、まず注目したいのが「実績」「資格」「口コミ」です。
- 実績のある業者か:創業年数やこれまでの作業件数などをチェック。多くの依頼を受けている業者は、トラブルの回避ノウハウも豊富です。
- 資格の有無:「遺品整理士」や「古物商許可」などの資格を持っているか確認しましょう。特に遺品の買取も行う業者には古物商許可が必須です。
- 口コミや評判:GoogleやSNS、比較サイトなどで第三者からの評価を確認。利用者の声は、実際の対応の良し悪しを知るうえで参考になります。
>>ココロセイリのスタッフ紹介についてはこちら
>>ココロセイリの買取についてはこちら
>>ココロセイリの料金体系はこちら
見積もり時の説明内容をチェック
信頼できる業者かどうかは、見積もり時の対応にも表れます。
確認したいポイントは以下の通りです。
- 作業内容や料金の内訳が明確に説明されているか
- 追加費用が発生するケースについて事前に説明があるか
- 「現金や貴重品が出てきたときの対応」についてのルールがあるか
- 依頼者の希望(「写真は残しておいてほしい」など)を丁寧にヒアリングしてくれるか
説明が曖昧だったり、「とりあえず任せてください」といった対応の業者は要注意です。納得できるまで質問して、不安を解消する姿勢のある業者を選びましょう。
遺品や現金の取り扱いルールが明確な業者を選ぶ
遺品整理では、現金や貴金属、思い出の品など、価値のある遺品が見つかることも珍しくありません。
その際、依頼主に対してどのように報告・返却するかというルールが整っているかは重要な判断材料です。
優良な業者であれば、次のような対応をしてくれます。
- 現金や貴重品を見つけたら、すぐに依頼者に報告
- 発見物を写真で記録し、作業報告書を残す
- 貴重品の返却時には引き渡しリストを作成
逆に、取り扱いルールが不明瞭だったり、「高額な物は買い取りますよ」とすぐに提案してくるような業者は注意が必要です。
ルールの明確さ=誠実さの証明と考えて、業者選びを進めましょう。
まとめ|現金が出てきたときこそ、冷静な対応と信頼が大切
遺品整理を進める中で、思いがけず現金が見つかることは珍しくありません。
故人が生前に大切に保管していたお金だからこそ、丁寧かつ誠実に取り扱うことが求められます。
大切なのは、次の通りです。
- 現金が出てきたらまずは相続人全員に報告すること
- 財産目録に記載し、記録として残すこと
- 勝手に使わず、遺産分割協議で分配方法を決めること
- 相続税の申告や相続放棄のルールにも正しく対応すること
さらに、思わぬトラブルを防ぐためには、現金が見つかりやすい場所を知っておくことや、信頼できる遺品整理業者の選定も非常に重要です。
遺品整理は、ただの片付けではありません。
故人の想いを丁寧にたどる、人生の締めくくりとなる大切な作業です。
現金が見つかったときこそ、焦らず冷静に、そして家族や関係者との信頼関係を大切にしながら対応していきましょう。
そうすることで、遺品整理の時間が、家族にとって「前を向いて進む一歩」に変わっていくはずです。
ご家族だけで遺品整理を進めるのが難しいと感じたら、専門の遺品整理業者に相談するのも一つの方法です。
私たち「ココロセイリ」は、関西エリアを中心に、心を込めた丁寧な遺品整理サービスを提供しています。
現金や貴重品が見つかった際の報告・保管・引き渡し方法も明確なルールを設けており、安心してお任せいただけます。
- 遺品整理士の有資格者が在籍
- 相続に関するご相談も対応可能
- ご相談・お見積りはすべて無料です
「どこに相談すればいいか分からない」「親族での作業が難しい」
そんなときこそ、ココロセイリが一緒に悩みを整理します。
豊富な実績を持つ遺品整理の専門店「株式会社ココロセイリ」の代表取締役社長